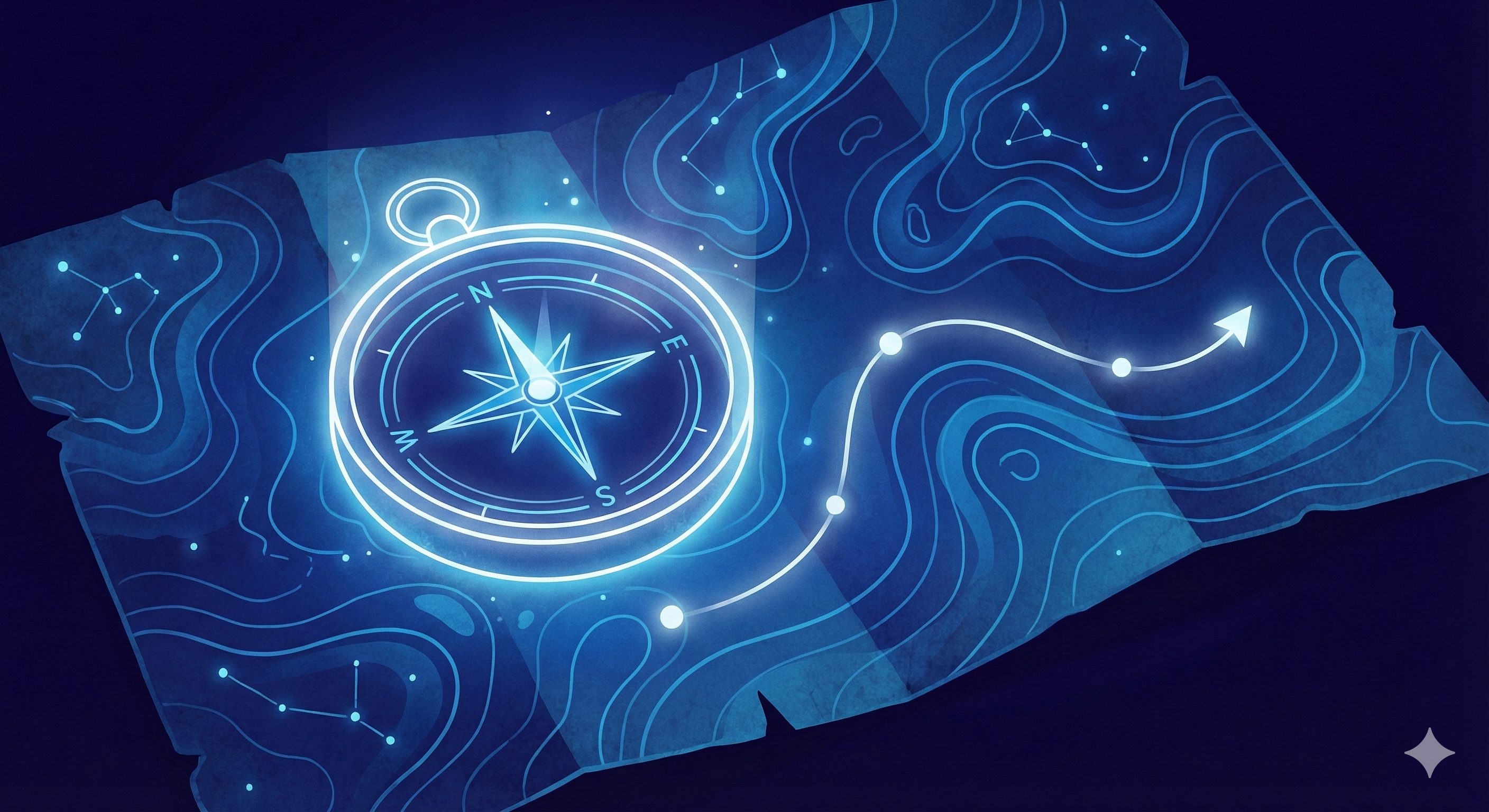・書籍タイトル: 教育論の新常識 格差・学力・政策・未来
・編著者: 松岡 亮二
・出版社: 中央公論新社(中公新書ラクレ)
・ご購入はこちらから: https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AB%96%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%B8%B8%E8%AD%98
・目次
第1部 「格差」:教育格差(日本社会が直視してこなかった「教育格差」 他) 第2部 「学力」:「学力」と大学入試改革(「論理国語」という問題 他) 第3部 「政策」:教育政策は「凡庸な思いつき」でできている(GIGAスクールに子どもたちの未来は託せるか 他) 第4部 「未来」:少しでも明るい未来にするために(データと研究に基づかない思いつきの教育政策議論 他)
教育の「当たり前」をデータで問い直す
「学校に行けないことは、人生の終わりだ」。そんなふうに思い詰め、焦りを感じている保護者の方も多いかもしれません。しかし、私たちが絶対視しがちな「学校」や「教育制度」は、実は完璧なものでも、盤石なものでもないとしたら?
本書は『教育格差』の著者であり教育社会学者の松岡亮二氏が編著者となり、20名以上の研究者や文科省官僚が、日本の教育のリアルを「データ」と「エビデンス」に基づいて解き明かした論考集です。 個人の経験談や精神論で語られがちな教育論議を排し、格差の実態や、政策決定の舞台裏を冷静に分析しています。これを読むと、今の学校システムが抱える構造的な課題が見えてきます。それは決して絶望するためではなく、親が「学校」というシステムを客観視し、過度な期待や依存を手放すための、とても良い材料になります。
ポイント: 「思いつき」や「感情論」ではない、客観的な視座を持つ
本書の核心は、日本の教育がいかに「データに基づかない、凡庸な思いつき」や「個人のエピソード」によって動かされてきたか、という事実の提示にあります。
・教育格差の現実: 日本は「生まれ」によって学歴や学力が左右される「緩やかな身分社会」であり、それは戦後一貫して存在していること。学校教育だけではその格差を埋めきれていない現実がデータで示されています。
・政策の迷走: 大学入試改革やGIGAスクール構想など、近年の教育改革がいかなる背景で進められ(あるいは迷走し)、そこにどれだけの根拠があったのかが、専門家や現役官僚によって赤裸々に語られています。
・エビデンスの重要性: 「私の時はこうだった」「あの子はこれで成功した」という個人の体験談ではなく、統計データに基づいた現状把握(EBPM)こそが、教育を良くするために必要だと説かれています。これは、我が子の教育を考える親の姿勢にも通じる視点です。
この本について
・独自の視点
本書の強みは、教育を「熱い想い」だけで語るのではなく、「冷徹なデータ」で語っている点です。また、研究者だけでなく、現役の文部科学省の官僚たちが実名で執筆に参加している点も画期的です。行政の内部から見た課題や葛藤が率直に綴られており、教育という巨大なシステムが、実は手探りで動いている人間臭い営みであることがわかります。
・相対評価
・評価軸の傾向 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 理論(抽象・データ)。個別の勉強法などではなく、教育システム全体の構造を扱っています。
・ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ(客観)。徹底して事実と数字に基づいています。
・今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくり(長期)。社会構造や制度の理解を促す内容です。
・当事者目線 ⇔ 支援者目線: 俯瞰的視点。親や教師という立場を超えて、社会全体を見る視点です。
・ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。現状の良い点も悪い点もフラットに分析しています。
・発達特性との関連度: なし。個別の特性への言及はなく、マクロな教育環境の話が中心です。
まとめ: 「学校」を相対化し、親の不安を「知る力」に変える
不登校に悩むとき、私たちはつい「学校に適応できない我が子」や「適応させられない自分」を責めてしまいがちです。しかし本書を読むと、学校という場所もまた、社会の変化や制度の疲労の中で揺れ動いている不完全なシステムであることがわかります。 親が教育の構造的な課題を知ることは、決して学校を批判するためではありません。むしろ、「学校にすべてを委ねなくていい」「学校だけが唯一の正解ではない」と、肩の荷を下ろすためです。 感情的な教育論に振り回されず、冷静な「知る力」を持つこと。それは、不登校という状況にある子どもを、親が「どうじず」に見守るための、太い精神的支柱となってくれるはずです。
ご購入はこちらから https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AB%96%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%B8%B8%E8%AD%98
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
ボクたちが学校や教育について語るとき、つい「自分の受けた教育」を基準にしてしまいがちです。「自分はこうやって頑張った」「昔はもっと厳しかった」。しかし松岡氏をはじめとする執筆陣は、そうした個人のエピソード(n=1、エヌイチの体験談)で教育を語ることの危うさを指摘します。
メディアなどで教育を論じている者の大半は『エリート』で、少なくとも大卒である。まるで、『エリート』たちで満席の、錆だらけのメリーゴーラウンドだ。(中略)『エリート』がこの『遊び』に興じている間に、多くの子供たちの可能性が消えてきた。(第1章より)
これはドキッとする言葉ですが、不登校の文脈でも同じことが言えるかもしれません。成功体験に基づいた「学校に戻ればなんとかなる」というアドバイスは、時として子どもを追い詰めます。
本書では教育政策が「凡庸な思いつき」でできている側面があることも指摘されています。
国の制度というと専門家集団によって熟考された精緻な設計を期待したいところですが、思いつきの政策論に基づいていることは残念ながら珍しくありません。」(まえがきより)
これを読むと、「学校の言うこと、国の決めたことが絶対だ」と思い込む必要はないんだな、と少し気が楽になりませんか?
制度も完璧ではないし、現場も試行錯誤している。だからこそ、私たち親は「学校任せ」にするのではなく、子どもにとって何が最善か、家庭という最小単位の現場で、オーダーメイドの「自立への道」を考えていけばいい。 「凡庸な教育格差社会」である日本において、学校外のルートを含めて子どもの可能性をどう広げていくか。そんな戦略的な視点を、ボクたち親こそが持つべき時なのかもしれません。 学校というシステムを「神聖視」せず、ひとつの「社会機能」としてクールに見つめる。その視点が、親子の心の余裕につながります。