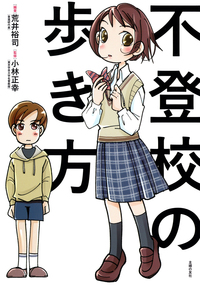書籍タイトル: 不登校の歩き方
著者: 荒井裕司
出版社: 主婦の友社
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/hoXhZkD
学びは楽しいはずが「罰を受ける場所」に
著者は、かつて不登校だった青年の「学校は罰を受ける場所」という言葉の衝撃から本書の執筆を開始しています 。本来、学びは楽しいものであるにもかかわらず、なぜ学校が苦行の場になってしまうのか 、という問いが根底にあります。
本書は、著者(登進研代表)の長年のセミナー記録(延べ1万人、Q&A 3500例)に基づき 、不登校体験を「回復に向かう一歩」として捉え直す視点を提供します 。不登校に対する基本的な考え方、学校とのつきあい方、発達障害との関連など、多岐にわたる悩みが詰まった一冊です 。
ポイント:不登校は「能力」と「回復のプロセス」
著者は、不登校になった子どもたちを「このままでいいと思っている子はひとりもいない」と断言します 。学校に行くふり(仮面登校)をしたり、心身ともに疲れきっていても 、それは「しがみつくエネルギー」が尽きたための一時的な休憩であり 、回復のプロセスは学校に行けなくなったときから既に始まっている 、という希望のメッセージを核とします。
- 不登校は能力である:「不登校になることができる能力」は、「自分が自分であるということを守る能力」であり、より大きなダメージから自分を守るための安全弁である 。SOSを発信できたのは、親への信頼感が育っている証拠でもある 。
- 回復の歩き方:回復のプロセスは、高い山から**ベースキャンプへ「下山する勇気」であり、それも回復のプロセスの一つである 。親の役割は、目の前でゴロゴロしているわが子を責めず、「まさにあれは回復のプロセスだったんだ」**と振り返る視点を持つこと 。
- 回復のサイン:子どもがお風呂に入る回数が増える、靴の手入れをしはじめる、アニメやマンガのキャラクターを夢中になって描く、ゲームの内容が育成系に変わるといった行動は、外の世界や他人の目を意識し、エネルギーがたまり、心が安定してきた証拠です 。
- 親の姿勢:”子の側”に立つこと。熱心な教師が家庭訪問に来た際も、子どもが会いたくないなら、担任には「しばらくは私との連絡だけで」と伝え、学校との関係がこじれても、わが子を守る姿勢を優先すべきです 。
この本について
・独自の観点
書籍の強みは、当事者経験という強い共感性を持ちながら、フリースクール運営者という立場から、学校外の学びと居場所について、具体的な選択肢と知見を提供している点にあります。
・相対評価
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや方法(具体)に特化 。不登校中の具体的な時間の使い方や回復サイン、居場所探しなど、日常で役立つアドバイスが豊富です。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェット(感情)。当事者の心情を代弁し、保護者へは共感と温かい励ましを与えるトーンです 。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 長期。不登校は「長期戦」であることを前提とし、焦らず、人生全体を視野に入れた対応を推奨します 。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 両者の融合。当事者としての「経験」と、支援者としての「客観的な知見」をバランスよく提供します 。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ポジティブ(肯定的)。不登校を「回復の一歩」や「自分を守る能力」として肯定的に捉え直すメッセージが核となっています 。
- 発達特性との関連度: 3。ADHD、感覚過敏といった特性を持つ子どもの困難に触れ、サポート方法(イヤーマフ、環境調整)を具体的に解説しています 。
まとめ:不登校という旅を自分らしく「歩ききる」
本書は、不登校という状況を「旅」に例え、親に対して「子どもが自分らしい人生を歩み始めるための準備期間」として捉えることを促します。
親が不安や焦りを手放し、子どもが学校の外で獲得する「自由な時間」と「ゆるやかな繋がり」の価値を認めること 。そして、子どもが自らの意志で動き出すまで、「信じて待つ」という最も難しい親の役割を果たすこと 。
当事者からのこのメッセージは、保護者が抱える罪悪感を和らげ、不登校という困難を「旅の経験」として受け入れ、子どもと共に自分らしい人生を歩み続けるための、温かい指針となるでしょう。
ご購入はこちらから (出版社公式ページURL)
https://amzn.asia/d/aGmifDA
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
改めて、「不登校」とは一本の”道”なのですね。多少悪路でも、また他者と大きくルートが異なっても、その行く先はどこかへと繋がっていて、道中には様々な景色があり、また考えたり歌を歌ったりもする。そういう「歩き方」は、当たり前ですが人により、子どもの数だけ大きく違ってくる。ただ、それだけのことなんです。
著作内には、不登校当事者や先生方ふくめかなりの箴言・名言ぞろいで、またマンガも入っていて読みやすく、じっくり文字を追わなくてもサラサラっと重要なエッセンスが吸収していけます。もちろん読後はポジティブ、なによりいつも「子どもの側」であるのがとても好印象です。
たとえば「親は我が子の専門家」「ときどき行方不明になろう」「親がベースキャンプになる」「答えを求めないやり方で、さりげなく情報をなげかける」など、これらは支援における重要なキーワードで、これらは”なぞるだけ”でも道中とても役に立つはずです(精神的に大変なときほど、文字は吸収しづらいものです)
さらに印象に残ったところとして、以下も不登校本人の”ジレンマ”を見事に言語化していると思いました。
ちょっと変な言い方ですが、”並の覚悟”では不登校にはなれません。大きな覚悟をもって、子どもは「不登校」という道を選択しています。大人の目からは、「甘えている」「怠けている」と見えることもありますが、本人は他の選択肢がみえないくらい追い詰められています。
多くの子どもにとって、「学校に行く」のは普通のことでしょう。その普通のことができない自分は普通ではないわけです。安全なレールの上を自らの意思で外れた(外れざるを得なかった)ことから、将来への「不安」におそわれます。
一方で、不登校によって嫌な出来事を避けることができた「安心感」も同時に感じてしまうのが、不登校の難しいところです。(P.34、小栗貴弘氏)
なかで著者は、最後に保護者による「肯定的なかかわり」が、これまで以上に重要になってくると締めくくります。”道中”は長く入り組んでいて、心のエネルギーも尽きてしまいがち…でもそんな背中を「肯定感」で押してくれるのが、また本著の良さでもあるかと。ぜひ、道中必携の一冊として