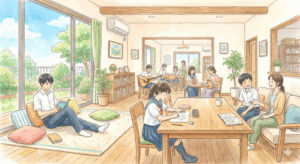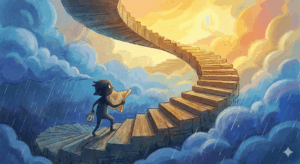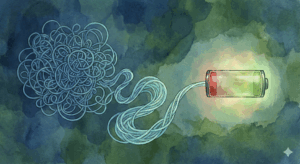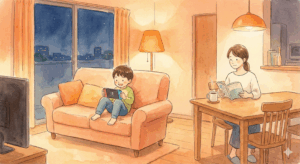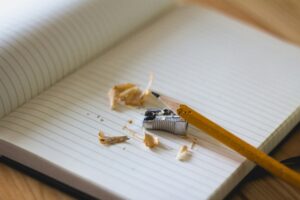不登校の現状と学習への不安
不登校は、現代の日本社会が抱える深刻な教育課題の一つです。文部科学省の調査によると、令和5年度には小・中学校の不登校児童生徒数が過去最多の346,482人に達し、高校でも不登校生徒数は68,770人と過去最多を記録しています。
この増加傾向は、不登校が特定の学齢期の問題ではなく、どの年齢の子どもにも起こりうる現象であることを示唆しています。特に、不登校の子どもたちの半数以上にあたる55.0%が90日以上欠席しており、これは子どもたちの「学習機会」を長期にわたって奪うことにつながります。
不登校の子どもたちの多くは、学校を休んでいることに対して「ほっとした・楽な気持ちだった」(小・中学生ともに約70%)、「自由な時間が増えてうれしかった」(約66%)といった肯定的な感情を抱いています。この安堵の裏側には、大きな不安も潜んでいます。特に中学生では、「勉強の遅れに対する不安があった」と回答した生徒が74%と非常に高い割合を占めています。また、「進路・進学に対する不安」も中学生の約7割(69%)に上り、保護者も「子どもの進路や将来について不安が大きかった」(中学生の保護者で78%)と回答しています。
また不登校のきっかけが何であれ、子どもたちが「学校に行きづらくなる理由」として最も多く挙げたのが「勉強が分からない」(中学生で42%)でした。これらのことから、不登校の子どもと保護者が、学習の遅れと将来への不安という二重のプレッシャーにさらされている状況がわかります。
多様な教育機会と支援体制
不登校は誰にでも起こり得るものとして捉え、文部科学省をはじめとする支援者や教育機関は、「学校に登校する」という結果のみを目標とせず、子どもたちが自らの意思で社会的自立を目指すことを支援の基本的な考え方としています。特に、自宅での学習が中心となる不登校の状況では、多様な学習機会と支援体制の活用が重要になります。
公的支援機関・施策
公的な支援機関として、教育支援センター(適応指導教室)が設置されており、不登校の子どもに個別学習や相談の機会を提供しています。また、不登校特例校(学びの多様化学校)の整備も進められており、個々のニーズに応じた柔軟な教育を提供しています。夜間中学は、義務教育を十分に受けられなかった多様な人々が学べる場として充実が図られています。学校内では、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)の配置が進められており、心理面や環境面からのサポート体制が強化されています。
民間・学校外連携
不登校の子どもと保護者の意思を尊重し、民間機関とも連携して支援する方針が打ち出されています。学校外の多様な学びの場であるフリースクールなどは、文部科学省が定める一定の要件を満たせば、在籍校での出席認定や成績評価の対象になり得ることが法律上認められています。
自宅学習(ホームスクール)
不登校の子どもが自宅で学習する「ホームスクーリング」は、子どものペースや興味・関心に合わせた個別最適な学びを実現する手段として注目されています。しかし、その実践には社会性の担保や教育の質、そして保護者の大きな負担といった課題も伴います。
個別指導
家庭教師や個別指導塾は、不登校の子どもと相性が良いとされています。完全マンツーマン指導により、子どもの理解度やペースに合わせてさかのぼり学習から受験対策まで柔軟に対応できることが大きなメリットです。このような指導は、生徒一人ひとりに合わせた授業を行うことで、必要な知識を効率的に習得できるのが特徴です。
学習管理/コーチング
不登校の生徒が自宅学習を継続し、モチベーションを維持するためには、学習管理やコーチングが非常に重要です。専門の学習サービスでは、生身の支援コーチが、志望校から逆算した学習計画の進捗を管理し、励ましのサポートを提供しています。
推奨教材・アプリ
文部科学省は、自宅でのICT等を活用した学習活動を「出席扱い」と認める制度を設けています。この制度を利用するには、保護者と学校の連携や、訪問等による対面指導といった7つの要件を満たす必要があります。令和5年度には、不登校児童生徒のICT学習の出席扱いが10,467人に達し、制度の利用が広がっています。
自宅学習におすすめの通信教育としては、無学年方式で出席扱い実績が多数ある「すらら」や、買い切り型で発達障害・学習障害に配慮された「天神」、低価格で映像授業が豊富な「スタディサプリ」などがあります。学習継続のためには、これらの教材に加えて、学習時間記録・分析機能を持つスケジュール管理アプリの活用も有効です。
不登校からの進路と具体的な事例
不登校の時期は、単なる休養だけでなく、自分を見つめ直すための積極的な意味を持つことがあります。支援の最終目標は、社会的自立を目指すことです。
通信制高校
不登校の子どもにとって、通信制高校は有効な選択肢です。通信制高校の最大のメリットは、通学が強制されず、自宅で学習可能で自分のペースで学べることです。また、体調に合わせて無理なく進められるため、不登校からの再スタートに適しています。通信制高校卒業生の高等教育機関への進学率は**45.7%**に上っており、進学を希望する場合は、受験サポート体制が充実した学校を選ぶことが重要です。
大学進学
不登校を経験した子どもが大学進学を目指す際、学力で評価される一般入試だけでなく「総合型選抜(AO入試)」も有効な選択肢となります。総合型選抜では、単なる学力だけではなく、不登校期間中に培った活動実績や個性、学習への熱意をアピールすることで合格の可能性を高めることができます。
不登校を「新たな学び」のチャンスに変える
不登校は、学校の画一的なカリキュラムや人間関係から一度距離を置き、自分自身を見つめ直すための貴重な機会となり得ます。この期間を「せっかくの機会」として、子どもが本当に好きなことや興味のある分野に深く没頭することで、学校では得られないユニークな強みや経験を身につけることが可能です。
- プログラミングを極める
-
不登校中に独学でプログラミングを始め、オリジナルのアプリやゲームを開発した生徒がいます。彼は、学校の授業の進度や内容に縛られることなく、自分のペースで高度な技術を習得しました。この成果が、IT系の専門大学や学部への総合型選抜で、学習への熱意や実践的なスキルをアピールする上で大きな武器となりました。
- 探究活動に没頭する
-
特定の社会課題や科学分野に強い関心を持つ生徒は、不登校期間を利用して、独自の探究活動に没頭することができます。例えば、地域のごみ問題についてフィールドワークを行い、その解決策を提案するレポートをまとめるなどです。このような探究活動は、総合型選抜で「主体性」や「思考力」を評価してもらうための重要な材料となったそうです。
- 趣味から専門分野へ
-
カードゲームやアニメ、韓国語などの趣味に没頭したことが、その後の進路につながる事例もあります。カードゲームを通じて戦略的思考を養ったり、韓国語学習を通じて語学力を身につけたりといった経験は、面接や小論文で自己PRの材料として活用でき、大学の求める多様な人物像に合致する可能性があります。またとある生徒は不登校期間に大好きだったテーマパークに通い詰めることで、マーケティングに関する新たな可能性を発表し見事合格を勝ち取りました。
これらの事例は、不登校という状況をネガティブに捉えるのではなく、学校外だからこそ得られる「個別最適な学び」の機会として活用することで、将来の選択肢を広げられることを示しています。親は、子どもを学校に戻すことだけに固執せず、子どもが自分らしくいられる場所と時間を提供することが、その後の大きな成長につながる鍵となります。
まとめ
不登校の経験は誰にでも起こり得るものであり、その支援はなにも「登校再開」を唯一の目標としないことで、新たな可能性やキャリアを開拓することがあります。こと「自宅学習(ホームスクール)」は子どもの特性やペースに合わせた個別最適な学びを実現する一方で、社会性や経済的な興味関心や課題意識をも育む可能性があります。また敢えて学校の外側から、半強制的な「勉強」としてでなく、自主的な「学習」として対象を見つめ直してみることで、後の高度専門やキャリアにつながる探究的な学習態度や教養を身につけられるかもしれません。
親子だけで問題を抱え込まず、この機会だから得られる多様な教育機会(ICT学習、個別指導、通信制高校、特例校など)や公的・民間の支援体制の情報を集め、積極的に外部の専門家に接続し相談・体験の機会を増やしてみることをお勧めします。
参考文献
- 宮良淳子、柴裕子、市江和子「不登校からフリースクールを経て再登校を決めた経験者の心理的プロセス」(日本看護研究学会雑誌、2022年)
- 今井さやか、大川一郎「塾職員が行う学習以外の相談支援の検討」(心理学研究、2020年)
- 松下丈宏「『非通学型』の公教育の可能性と課題―ホームスクーリングを事例に一」(日本教育行政学会年報、2019年)
- 前原健二、滝沢潤「『非通学型』学校の展開と公教育制度の論点」(日本教育行政学会年報、2019年)
- 宮口誠矢「学校外で保障されるべき「最低限の義務教育」の構成」(東北大学、2020年)
- 菊池ほの香、相模健人「不登校児童生徒の類型と回復過程に着目したフリースクールスタッフの支援に関する研究」(愛媛大学教育学研究科心理発達臨床、2024年)
- 小川幸裕「不登校問題におけるスクールソーシャルワークに関する研究」(帯広大谷短期大学紀要、2003年)
- 近藤真理子、田中義和、藤本文朗「ひきこもりの人々と歩む課題」(日本の科学者、2022年)
- 生田久美子、下村一彦、村田美穂、尾崎博美、宮寺晃夫「スクールとしてのホーム/ホームとしてのスクール」(教育思想史学会年報、2005年)
- 松久眞実、八木利津子、野津喬「今日的な不登校支援にかかわる現状と課題」(帯広大谷短期大学紀要、2024年)