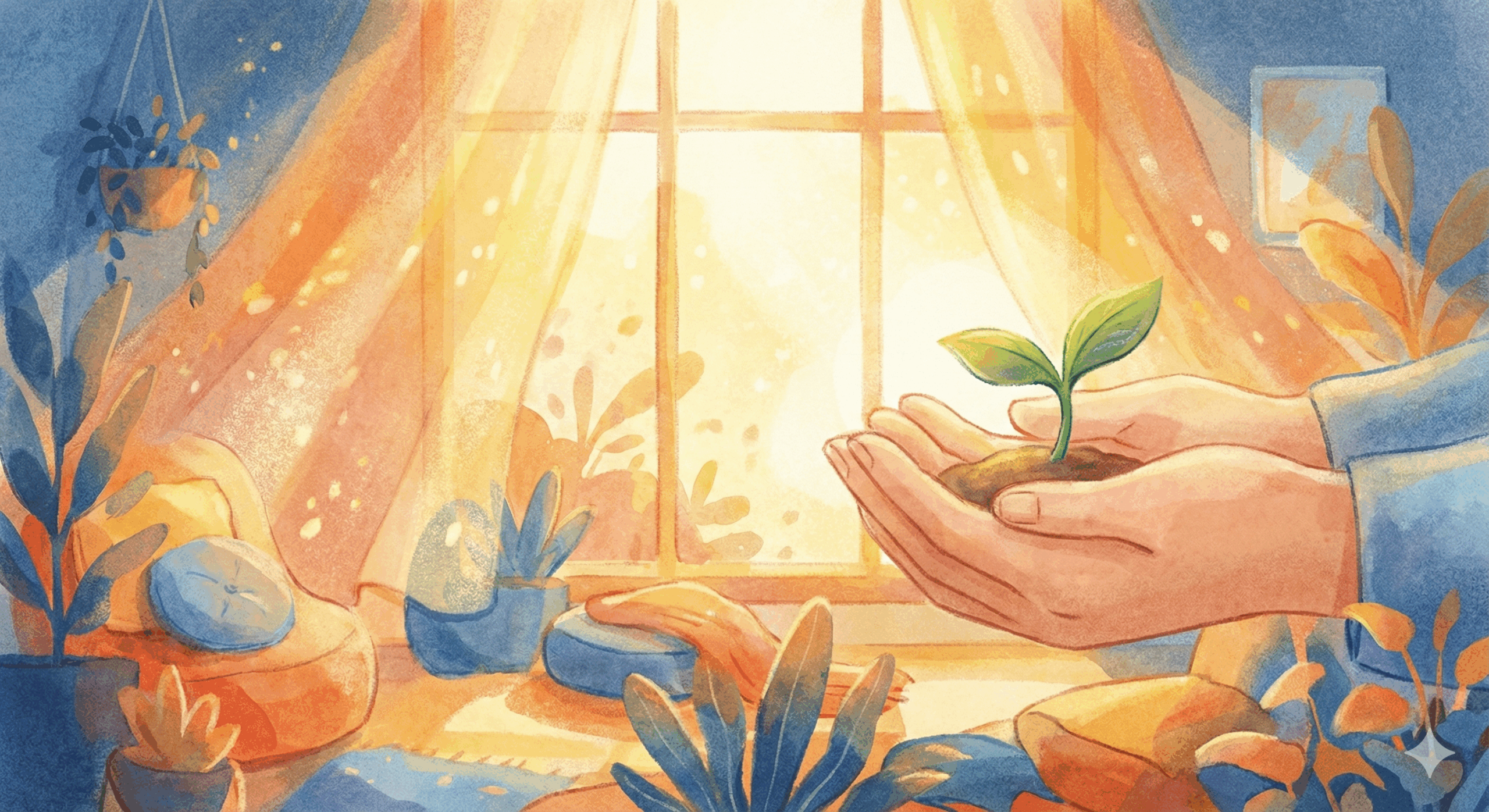【編集部より】
この記事は、3万人の中高生と関わってきた専門家(ジェネレーター)と、元不登校の当事者スタッフが共同で監修・執筆しています。
「きれいごと」ではない、現場のリアルな知見に基づいた情報を掲載しています。
1. 導入:見過ごしてしまいがちな「サイン」から、不登校の始まりを感知する
朝、「お腹が痛い」「頭が重い」という突然の子どもの一言が、実は不登校の始まりを告げるSOSかもしれません。
多くの不登校当事者の親が「あの時気づいていれば…」と後悔するポイントなのですが、不登校のサインは非常に巧妙で複雑に入り組んでいて、普段から観察・関与があり”愛情深い”コミュニケーションを保持しているご家庭であっても、見過ごしてしまうほど複雑です。
この章では、私(※筆者 スガヤ)自身および当サイト勉強会参加者の体験に加え、登校回避行動の研究や、学校現場の知見に基づき、見過ごされがちなサインを体系的、かつ具体的に解説していきます。
大切なのは、サインを「見つける」ことだけでなく、その裏側にある子どもの「心の状態」を理解し、何を「しないか」という初期対応の原則を学ぶことです。
以下に詳しく解説しますが、「まず、全面的に受け容れる」ことの重要性だけ、予めこの時点で強調してお伝えしておきます。
2. 身体的なSOS:登校時間に現れる心身症的傾向
「思春期だからよくあること」というのは、親として一番判断に迷うポイントです。
しかし、私の経験や周囲の話を聞くと、子どもは「本気で行けない時のSOS」と「ただの愚痴」を使い分けていることがあります。
ある元当事者のスタッフ(スミレ)は、「本気のSOSを出した時、母が学校を休ませてドライブに連れて行ってくれた。その『逃げ道』があったからこそ、翌日からまた頑張れた」と語っています。
「行きたくない」という言葉の裏にある切実度を見極めるには、普段から家庭が「弱音を吐いてもいい安心できる場所」になっているかが重要だと感じます。
不登校の予兆として最も多く見られるのが、「身体的な不調」です。これらは、学校への心理的なストレスが身体症状として現れる「心身症的傾向」です。
朝、腹痛や頭痛を訴えることが増え、しかし念の為病院を受診しても「異常なし」と診断されてしまいます。この場合、ほぼ間違いなく「学校がしんどい」という心の叫び(SOS)です。特に症状が登校時刻になるとピークに達し、週末や長期休暇では症状が出ないという傾向が見られる場合、「心理的要因」が強く関わっています。
ある保護者は、ご自身の経験を振り返りこう語ってくれました。
「うちの子は、朝はぐずっても、私が厳しく言えばすぐに登校したんです。でもいつ頃からか?、だんだん怒りも泣きもせず、ただ静かに行って帰ってくるように。あのときは『思いが通じた、厳しく言ってよかった』と安堵したのですが…今思えば、あれは心身が防衛のために感情をシャットダウンしはじめている状態だったのですね」
このとき「一旦登校した」という事実に安心するのではなく、”子どもの心のエネルギーが完全に枯渇し、抵抗する力すら失っていきつつある”という可能性を疑う必要があります。この時点こそが、重要な「不登校の初期サイン(予兆)」です。
【専門家の視点:医療につなぐ前に】 「発達障害ではないか?」「うつではないか?」と不安になった時、すぐに病院へ行く前に家庭でできるケアがあります。精神科医が教える具体的な親の対応については、『思春期に心が折れた時 親がすべきこと』の紹介記事をご覧ください。
3. 行動・感情の異変:見過ごされがちな「カモフラージュ」
(編集長:スガヤより)
不登校の子の部屋に遊びに行ったことがありましたが、心に余裕がない時の部屋は、かなり荒れてましたね。
しかしのちに書籍で調べたら、これは「だらしない」のではなく、自暴自棄になっていたり「片付ける気力(エネルギー)さえ枯渇している」状態と知りまして、しばらく放置するよう保護者に伝えました。
部屋が散らかり始めたら、叱るのではなく「エネルギー切れのサインかも?」と捉え直し、休息を促す視点が重要です。
「心のエネルギー切れ」としてのサインは、身体だけでなく「行動」や「感情」の微妙な変化にも現れていきます。特に「親に心配をかけたくない」という優等生的な子どもほど、その顕れ(サイン)を”偽装(カモフラージュ)”してしまう傾向が強く、より注意が必要です。
見過ごされがちな行動の予兆/サイン
- 感情表現の乏しさ(静かなシャットダウン):以前は反抗していたり、怒りや泣きで不満を表現していたりした子どもが、急に「良い子」になり、感情の起伏を示さなくなる状態。
- 生活リズムの乱れ:夜更かしが増え、朝なかなか起きられない、日中の活動量が極端に減る。
- 行動習慣の急激な乱れ:たとえば「部屋が乱れる」(「以前は”きれい好き”だったのに、お菓子のゴミや衣類が散乱した状態を放置し始めました」という体験談に基づきます)、「ゲームへの没頭」など、かつての行動習慣/ルールが保持されない。
独自サイン:「明るい自己否定」と口癖の危険性
(元当事者スタッフ:スミレより)
私自身、高校1年の時に英語の成績別クラス分けで「一番下のグループ」になった経験があります。正直くやしくて、とても恥ずかしかったです。
私はクラスの雰囲気が良かったので乗り切れましたが、もし「成績が全て」というプレッシャーの中で孤立していたらと思うと、心が折れてしまうのも痛いほど分かります。
(元当事者スタッフ:スミレより)
高校3年の受験期、私は一度だけ限界を超えて保健室に駆け込んだことがあります。その時、先生に「いつも明るいスミレさんが、そんなに抱えていたなんて」と驚かれました。
当事者ですら、自分の限界なんて分からないことがあります。表面的な明るさは、親や周囲に心配をかけまいとする「精一杯の仮面」かもしれません。
また「精神」的なサインが、ネガティブな形だけでなく、一見明るく前向きな言葉の裏に潜んでいることがあります。同じく体験談に基づき、具体的に紹介しますと
- 「口数が極端に減った。反抗期でも何でも、『学校嫌だ!』とか言葉で表現してくれていたのに、直前は逆に明るくて、一切の不満を言わなくなった」
→子どもが親への不満を内側に閉じ込め、感情を偽装している可能性があります。 - 「明るい感じで『自分はダメだから、まだまだ頑張らないと』なんてコメントが食事中に出ていた」
→一見前向きなこの言葉は、過度なプレッシャーと自己否定が裏側にあることを示しています。
他にも、不登校につながりやすい代表的な口癖を以下にリストアップします。これらの言葉が出たときは、表面的な意味だけでなく、その裏に潜む「疲弊感」に気付いてあげるきっかけとしたいところです。(ただし、気付いたからといって「なぜ?」と問い詰めないことが大切ですことが大切です)
- 「自分はダメだから、まだまだ頑張らないと」
- 「人生楽しくない」「何しても楽しくない」(無気力感)
- 「楽になりたい」「誰にも会いたくない」(疲弊と孤立)
- 「疲れた学校行きたくない」
4. 保護者の初期対応:何を「しないか」が重要
(元当事者スタッフ:ぜりーより)
不登校を体験して、数人から「なぜ行けないの?」と聞かれて、一度も明確に答えられませんでした。高校を卒業した今でも、上手く説明できません。
強いて言えば「空気」という感じです。
(編集長:スガヤより)
そもそも「なぜ?」は”詰問のなぜ”など言われます。問われるとつい、責められているようにプレッシャーを感じてしまうのですね。
保護者はつい理由を知りたがりますが、「言いたくない」のではなく「自分でも分からない」のが正解だと知るだけで、お子さんへの接し方は大きく変わるはずです。
お子さまのサインに気づいたとき、最も大切なのは「何をすべきか」ではなく、「何をしないか」を明確にすることです。初期の対応がその後の回復プロセスに大きく影響します。
3つの初期対応原則
一言で言えば「まず、全面的に受け容れる」なのですが、詳しく分解すれば以下のようになります。
- 判断せず、理解せず(ただ見守る/観察する):
お子さまの言動を「わがまま」「怠慢」だと判断したり、不調の「原因」を特定しようと理解を急いだりしない。ただ「そう感じたんだね」「つらいね」と受け止め判断を保留し、”ありのまま”の我が子を観察する姿勢に切り替えます。 - 刺激せず(「登校刺激」を避ける):
学校へ無理に連れて行こうとしないことはもちろん、「なぜ行かないの?」といった理由を問い詰める質問も、子どもにとってはプレッシャーとなります。学校を休むことを「疲れた体の当然の権利」として認め、しばらく休ませましょう。 - 締め出さず(「安全基地」を提供する):
家庭を、学校という「外の世界」から逃れて心身のエネルギーを回復できる「安心できる安全基地」にしてください。今は子どもの心が「エネルギー切れ」を起こしている状態なのですから、一時的に「匿う(かくまう)」ことが大切で、そうやって子どもに「安心」というチャージを与えましょう。
あくまで不登校とは子どもの自身の問題であり、保護者を含めた”外部”による解決はありません。なので基本は「受け容れる」ことから始まり、また終わっていきます。
子どもの様子がおかしいと感じた時、つい発達特性や特定の病名を探してしまいがちです。 しかし安易に医療につなぐ前に、まずは家庭でできることがあります。精神科医が教える『親が家庭でできるケア』については、こちらのブックガイド(思春期に心が折れた時 親がすべきこと)が非常に参考になります。
5. 次の一歩:早期支援の視点
一方保護者として、だからといって「放置しない(関与しつづける)」ことが大切です。(以降のステップは、続編記事で詳しく掘り下げるのですがカンタンに)初期の対応で家庭の安心が確保されたら、次のステップは「早期支援につなぐ」です。
その大方針は「孤立しない」こと、かつ「重層・複眼・多様」を保持するよう努めることが大切です。
- 重層:「外部」との素早い連携: 不登校は「家族」だけで解決できる問題ではありません。学校のスクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)、また地域の教育支援センターなど、外部専門機関への相談窓口を確認し、素早く連携の準備を始めましょう。多くは無料で利用できますが、状況によっては有料の専門カウンセラーを頼る手段もあります
- 複眼:「複数」依存先の確保: 自律とは「複数の依存先があること」と定義されるとおり、依存先は”特定”しないこと。できるだけ異種、複数を確保しましょう(こと「SNS」は、複眼的な言説が摂取できそうですが実は”真逆”なので要注意)。すぐコンタクトをとらず、いまはリストアップするだけでもよいです
- 多様:「柔軟」な視点の導入: 特定の言説や判断に惑わされず、いまは変動かつ曖昧な状況に対して「ネガティブ・ケイパビリティ(不確実で答えの出ない状況に耐え、性急に結論を出さない姿勢)」を保ちましょう。特に不登校の状態は、初期段階から様々変容していきます。子どもの心の状態(または子どもからの要求)を、逐次変容する”心もよう”として広く、柔軟に受け止めましょう。
この時点で、「子どもが”不登校になってしまう”のでは?!」という心配や不安が大きくのしかかると思います。ですが”あせらず・あわてず”が大事です。むしろ心配されている「不登校」は、実は子どもの特性について改めてその発達段階や独特さを捉え直したり、また家族や社会との関わり方を再定義しよりよい生き方を模索する機会になったりもします。
現時点では、まずは目の前の子どもをありのままに受け容れ、「心のエネルギー」をただ静かに回復させてあげるよう努めていきたいところです。
(元当事者スタッフ:まる より)
不登校のサインは、終わりではなく「生き方を見直すチャンス(始まり)」でもあります。
学校に行けなくても、私は万博に登壇しました。スミレさんは大学院に通い教員を目指してますし、ぜりーさんは演劇など、未来はいくらでも選べます。
保護者が焦ってしまうほど、子どもは不安になりますから、”どっしり”構えて、まずは不安を抱きしめてあげてほしいです。
→【さらに詳しく知りたい!】概要と初期対応がシンプルにまとまったこちらの入門・ガイド書籍がオススメです(イラスト付きで読みやすい◎)。
ーこれでわかる不登校
ー不登校の歩き方
ー登校しぶり・不登校の子に 親ができること
ーNPOカタリバがみんなと作った 不登校—親子のための教科書
参考文献
・Kearney, C. A. (2007) 登校回避行動の定義と身体症状の関連 出典の知見: 登校回避行動の類型化、特に身体症状を伴う回避行動に関する知見
国立成育医療研究センター:不登校の理解と支援(公的機関の見解) 出典の知見: ・子どものSOSの気づき方、連携の重要性、アセスメントの必要性。
参照リンク: こどものSOSに 気づいたら(国立成育医療研究センター)
・日本小児保健協会:生活リズムと健康(睡眠不足や生活の乱れの根拠) 出典の知見: 睡眠覚醒リズムの確立の重要性、夜型化と情動面・学力面への影響。
参照リンク: 生活リズムの確立と睡眠(文部科学省・日本小児保健協会)
・三島 浩司ほか:登校回避行動の予防的介入研究(早期発見の重要性) 出典の知見: 予兆への対応を含めた初期段階からの組織的・計画的な支援の必要性。
参照リンク: 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文部科学省)
・不登校の前段階にある子どもの状態を示すモデルに関する研究(サインの予兆の根拠) 出典の知見: 不登校に至る前の段階で現れるサイン(口癖や行動の異変)のモデル化に関する知見