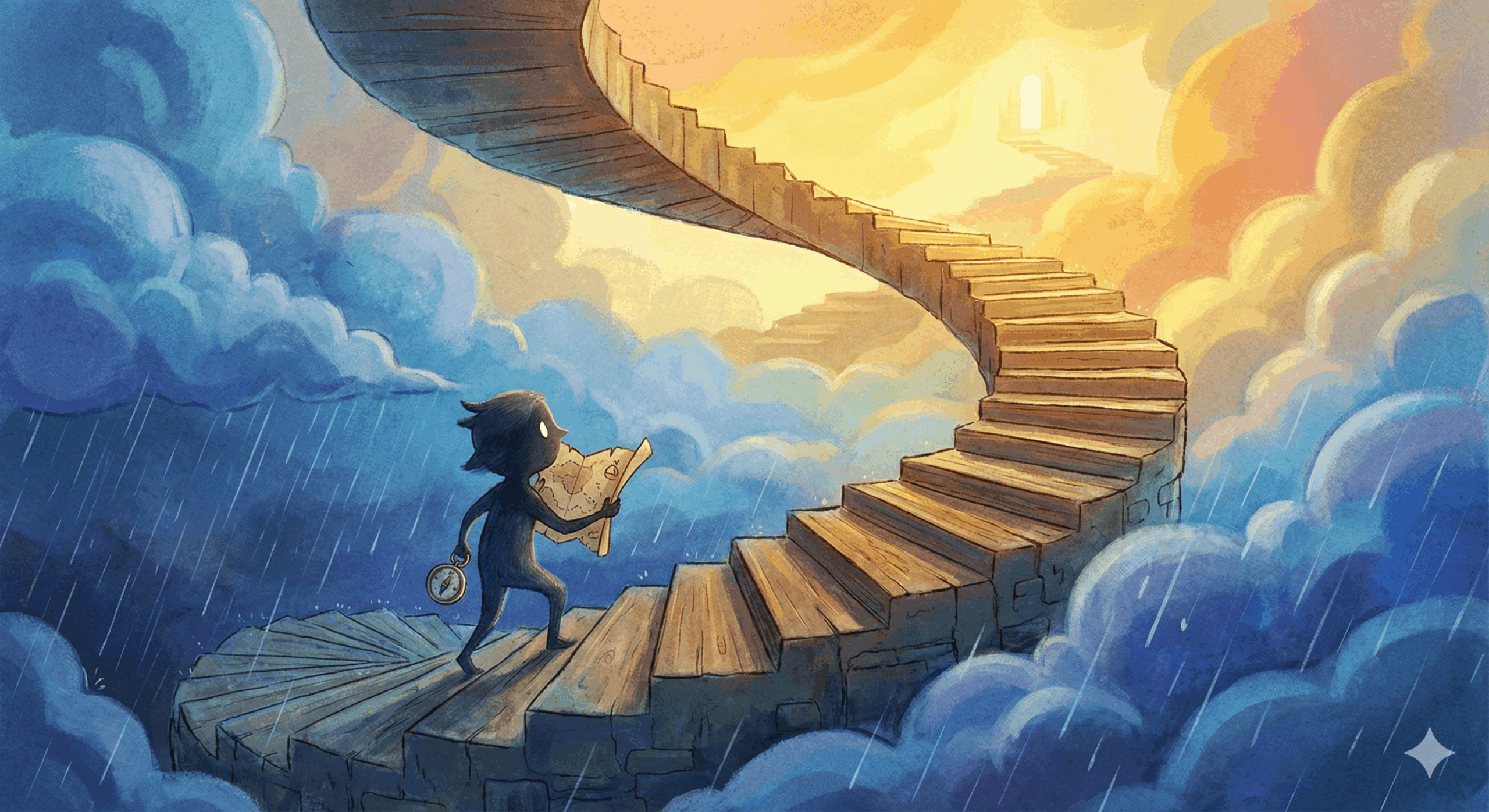【編集部より】
この記事は、3万人の中高生と関わってきた専門家(ジェネレーター)と、元不登校の当事者スタッフが共同で監修・執筆しています。
「きれいごと」ではない、現場のリアルな知見に基づいた情報を掲載しています。
不登校の回復は一直線ではありません。「混乱」と「受容」を行き来する子どもの心の内側を、経験者と専門家の視点で「地図」のように読み解きます。
前回までで、不登校が「誰のせいでもない」、複雑な複合因子から生じた「心のエネルギー切れ」であることを理解しました。では、この「エネルギー切れ」から、子どもの心はどのように回復に向かうのでしょうか?
焦りや不安を抱える保護者にとって、子どもの心の状態が「今どこ(どのへん)にあるのか?」を知ることは、支援のタイミングを見極める上で最も重要です。回復のプロセスは決して一直線ではなく、前進と後退を繰り返す「螺旋階段」のようなものです。
(…と言ってもこの「螺旋階段」が身の回りになく、勉強会ではなかなか通じないこともあります。このとき「ジグザグの坂(登りも下りも”まさか”もある)」または「だまし絵(戻るようで進んでいる)」とも表することがありますが、ともかく「一進一退」「三歩進んで二歩下がる」くらいのイメージとご理解ください)
この章では、不登校からの回復におけるそんな「一進一退」、つまり「”混乱”と”受容”」という心理学的なバランスを学び、子どもの心が休養から自ずと「自ら立つ(自立)」へと向かう「心の地図」を描いていきます。このとき回復の鍵となるのは、「居場所とつながり」です。どのようにして子どもの主体性を引き出し、次の一歩へと繋がっていくのでしょうか?
「子どものペース」に則り、心理学的な地図を頼りに共に次の段階へと進んでいきましょう。
1. 回復を導く2つの心理状態:「混乱」と「受容」
不登校からの再登校を考えるうえで重要となる心理状態として、「混乱」と「受容」の2つが示されています(山本奨, 2024)。
混乱(ネガティブな支配状態)
「混乱」とは、子どもが不安や落ち込み、後悔といったネガティブな感情に支配されている状態を指します。この時期の子どもは、「将来のことを考えると怖くなる」「あのとき学校に行っていれば…と後悔する」といった感情に囚われ、精神的に非常に不安定です。
ただしネガティブばかりでなく、「突然ご機嫌になったり親に甘えてみたりという”不可解”な行動」が多く見られたことも、保護者からの体験談として多く寄せられています。
不登校の初期、私の心の中はまさに嵐でした。
「学校に行かなきゃ」という焦りと、「でも体が動かない」という絶望。親に当たったり、急に甘えたりしたのは、自分でも制御できない不安を誰かに受け止めてほしかったからです。
あの時、親が動じずにただ「そこにいていいよ」としてくれたことが、何よりの救いでした。
【この時期の対応】
ただ心身の疲弊を癒す「休息」と「安全基地」の提供が最優先。混乱を深掘りせず、不安な気持ちを否定せず共感的に受け止め、揺蕩うように”受け止める(認める)”ことが大切です。こと上記のような「不可解な行動」についても、決して咎めたりせず、黙って受け容れてあげましょう。表現が混乱しつつも多様であるのは、ある意味「安心できているおかげ」でもあります。
受容(現実を受け止める姿勢)
「受容」とは、子どもが現実を受け止め、問題に前向きに向き合おうとする姿勢です。具体的には、「今の自分を受け入れようとしている」「目の前の課題に集中しようとしている」といった心の動きが見られます。
保護者からの体験談では、「突然、段ボールで工作し始めた」「絵を書くことに数日夢中になっていた」などの報告が寄せられています。上記のような心の動きが、具体的な言動として表出することもあるようです。
娘が少し元気を取り戻し始めたのは、学校に行かなくなって数ヶ月経った頃でした。
突然「お菓子作りがしたい」と言い出し、キッチンで黙々とクッキーを焼き始めたんです。
勉強でも登校でもないけれど、「あ、エネルギーが溜まってきたな」と直感しました。親としては「勉強したら?」と言いたくなりますが、そこをグッとこらえて「美味しいね」と一緒に食べたことが、次の一歩に繋がった気がします。
【この時期の対応】
受容の姿勢が見え始めたら、「小さな成功体験」を積み重ねる機会(家での役割、趣味の深掘りなど)を提供し、「主体性」を尊重することが回復の大きな後押しとなります。たとえば上記「工作」なら、「ちょうど〇〇が欲しいと思っていたの、お願いしても良い?」と機会を与えてあげることも有効です。
心理状態の組み合わせと再登校の可能性
研究では、この「混乱」と「受容」のバランスによって、子どもの再登校への可能性や適切な支援のタイミングが整理されています。
- 「混乱」が低く↓「受容」が高い↑: 再登校の可能性が最も高い段階。
- 「混乱」が高く↑「受容」も高い↑: 不安を抱えつつも前向きに向き合おうとしており、次の一歩へ踏み出すチャンスがある段階。
- 「混乱」が低い↓: まだ現実に向き合えていない段階であり、まずは「混乱」が高まる(=問題と向き合う)過程を経て、徐々に「受容」が育つことが期待されます。
大事なのは「家にいても混乱している」ではなく、「家が安心できるから混乱もできる」という点で、混乱は回復に向けた重要なステップのひとつということです。
2. 回復のプロセス:「心の螺旋階段」モデル
不登校からの回復は、海野和夫氏らの研究モデル(前駆期から再登校期までの5段階など)で整理されることが多いですが、その道のりは決して一直線ではありません。
「螺旋階段」としての回復
回復は、あたかも「同じところをぐるぐる回っているように見えても、実は少しずつ前に上に進んでいっている螺旋階段」だと表現されます。
- 「揺り戻し(後退)」はごく普通のこと: 一度「もう大丈夫」と思って学校やフリースクールに行き始めた子が、すぐにまた休んでしまう「揺り戻し」は必ず起こります。これは決して失敗ではなく、心身が新しいストレスに慣れようとするための「必要な調整期間」です。
「せっかく学校に行けたのに、また休んでしまった…」と落ち込む親御さんは多いですが、これは脳科学的にも正常な反応です。
新しい環境(刺激)に触れれば、脳は疲れます。休むことは「後退」ではなく、次の登校に向けた「クールダウン(調整)」です。
「行けた事実」よりも「疲れたと言えたこと(自己管理能力)」を評価してあげてください。
- 「小さな一歩」の評価: 大切なのは、目標達成の「結果」ではなく、「行こうとしたこと」「話してみたこと」といった「過程」を評価することです。フリースクールに一度だけ行ってやめてしまったとしても、保護者が「行こうとしただけですごい」という一言をかけることで、子どもはまた挑戦する勇気を取り戻します。
3つの回復段階(家庭内での変化)
不登校からの回復は、一般的に「休息期」→「動揺期・探索期」→「再適応期」の3つのステップで進行します。
- 休息期(充電期): 心身の疲弊が最も強く、寝て過ごしたり、ゲームに没頭したりする時期。無理な登校刺激は厳禁です。
- 動揺期・探索期: エネルギーが回復し、外の世界に少しずつ興味を示し始めるが、感情が不安定になる時期。「何かしたい」という小さな意欲の芽を大切に育てます。
- 再適応期(自立期): 社会的な活動への参加意欲が高まり、学校以外の学びの場(フリースクール、通信制など)や進路を具体的に検討し始める時期。
ただこの「階段」も「段階」も、注意したいのは回復を急ぎたいばかりについ”前のめり”に理解されがちな点。とある保護者も「”次”はいつ来るのか?と、返って心が休まらなくなってしまった」と指摘していて、くれぐれも回復の”目安”くらいに理解(メタ認知)しておくと、保護者も余計なストレスから解放されやすいでしょう。
🎹 コラム:音楽と創造がもたらす「心の回復」
精神的に不安定な時期、言葉による対話(カウンセリング)が難しいお子さんにとって、「音楽」や「ものづくり」が回復の糸口になることがあります(ミュージックセラピー/芸術療法)。
好きな曲を聴いて涙を流すこと(カタルシス)や、自分の今の気持ちを歌詞や絵にして表現することは、言葉にならない感情を外に出す「デトックス」の効果があります。
当サイトが提供する「Music Creation PBL」などは、単なる音楽教育ではなく、こうした「自分のくすりをつくる(自己治癒)」プロセスを、専門のジェネレーターと共に体験する場でもあります。無理に話さなくても、音や作品を通じて心が回復していく道もあることを、ぜひ知っておいてください。
3. 回復の鍵:「居場所」と「主体性」の確保
文部科学省が再三強調するように、不登校支援のゴールは「学校への再登校」ではなく、生徒が自分の進路を前向きに考え、社会的に自立していく「過程」を大切にすることです。その鍵となるのが、「居場所」と「主体性」です。
学校以外の居場所の重要性
フリースクールやオンライン支援は、子どもが「自分らしくいられる」環境を提供し、心の回復を後押しします。
- フリースクールの役割: 学校や家庭でのストレスから解放され、「強制されない安心感」の中で自己肯定感を回復させるシェルター的役割を担います。
- オンライン支援の可能性: 外出が苦手な子でも自宅から社会との接点を持てます。チャットでの交流やオンライン学習は、対人不安の強い子どもや発達特性を持つ子どもにとって、無理のない「つながり」を築くための有効な手段となります(櫻井裕子, 2022)。
私が再登校できたのは、皮肉にも「学校に行かなくても生きていける」と知ったからでした。
ボランティアや習い事で、学校以外の大人と関わるうちに、「学校は世界のほんの一部なんだ」と気づき、肩の荷が降りました。
「学校に戻すため」ではなく、「世界を広げるため」に外の居場所を使ってほしいと思います。
上記手段(概念)は、保護者世代にはあまり馴染みがなかったこともあり、保護者によっては「行くと戻れなくなるのでは?」と不安もあるようです(実際に「気軽に行かせてもよいのか?」という相談も多いです)。
しかし大事なのは「選択肢が複数ある」という安心感であり、また相対的に「学校」を捉え直せる点です。こと「自由過ぎる空間で過ごすことで、返ってもう一度”規律”を求め始めた」という反作用も指摘されていて、最も大切なのは「子どもが自主性を取り戻す」点であることを、再確認しておきましょう。
小さな成功体験と自己肯定感の回復
回復のきっかけは、必ずしも大きな出来事である必要はありません。子どもが主体的に何かを「できた」という”小さな成功体験の積み重ね”が、失われた自己肯定感を回復させます。
- 家庭での役割: 「野菜を切ってくれる?」「ペットのご飯をお願いね」など、家庭内で小さな役割を任せることで、「自分は役に立っている」という実感を得られます。
- 趣味や没頭の時間の肯定: ゲームやアニメ、漫画などに没頭する時間は、現実のストレスから離れる「心の治療」の時間です。これを「遊び」として否定せず、「集中力」や「創造性」として認めてあげる姿勢が次へのエネルギーとなります。保護者に余裕があれば、一緒に体験しながら、関連情報を共有するのもよいでしょう(そのことで「以前より仲良くなれた」という)。
- 日記や手帳による記録: この時期、勉強会で最も好評だったのが「日記」や「手帳」による”記録”でした。小さな変化を客観的に記録できるだけでなく、「書くほどに心が落ち着いた」「子どもの美点に改めて気づけた」という喜びの声が寄せられています。ストレスでなければ、認知療法の側面からも試してみることをお勧めします。
保護者としては、この時期に子どもの「したい」という小さな意欲を見逃さず、過度な干渉をせずに「見守る姿勢」を続けることが求められます。この信頼こそが、子どもが自らの力で困難を乗り越え、自分らしい人生を歩み始めるための最大の力となるのです。
🏫 「偏差値」ではない基準で、場所を選びませんか?
フリースクールやオルタナティブスクールを選ぶ際、パンフレットの条件だけで決めてはいけません。
大切なのは、「そこに行けば、うちの子の目が輝くか?」という一点です。
編集長が実際に現地へ足を運び、理念と熱量を確認した「心から信頼できる学び場」だけを紹介する特集コーナーを公開しました。
場所選びの参考に、ぜひ覗いてみてください。
結びと次回予告
この章を通じて、不登校からの回復が「ジグザグの山道」であり、心が「混乱」から「受容」へと進む非直線的なプロセスであることをご理解いただけたかと思います。最も大切なのは、不安な気持ちを抑えつけず、主体性を尊重し、「安全基地」として機能し続けることです。
しかし、理論が分かっていても、現実に子どもの前で「見守る」ことは非常に難しいものです。「どう声をかければいいのか?」「スマホやゲームの制限はどうすべきか?」という具体的な行動への不安は尽きません。
次回の章では、いよいよ「保護者が今日からできる具体的な支援策」に焦点を当てます。
- NGな声かけと、子どもの心を動かす魔法の言葉
- 昼夜逆転を無理なく治す「家庭内でのルール作り」
- 学校との連携で気をつけたい「3つの落とし穴」
次章で具体的なアクションプランを学んで、保護者の”不安”を”自信と行動”に変えていきましょう!
参考文献
- 文部科学省「不登校に関する実態調査」
- 国立成育医療研究センター「不登校の理解と支援(PDF)」
- 山本 奨『不登校児童生徒の再登校傾向に応じた教師による支援』
- 櫻井 裕子『オンライン居場所支援が不登校の子どもの行動や思考の変容に与える影響』
- 海野 和夫『不登校を克服する』(文春新書)