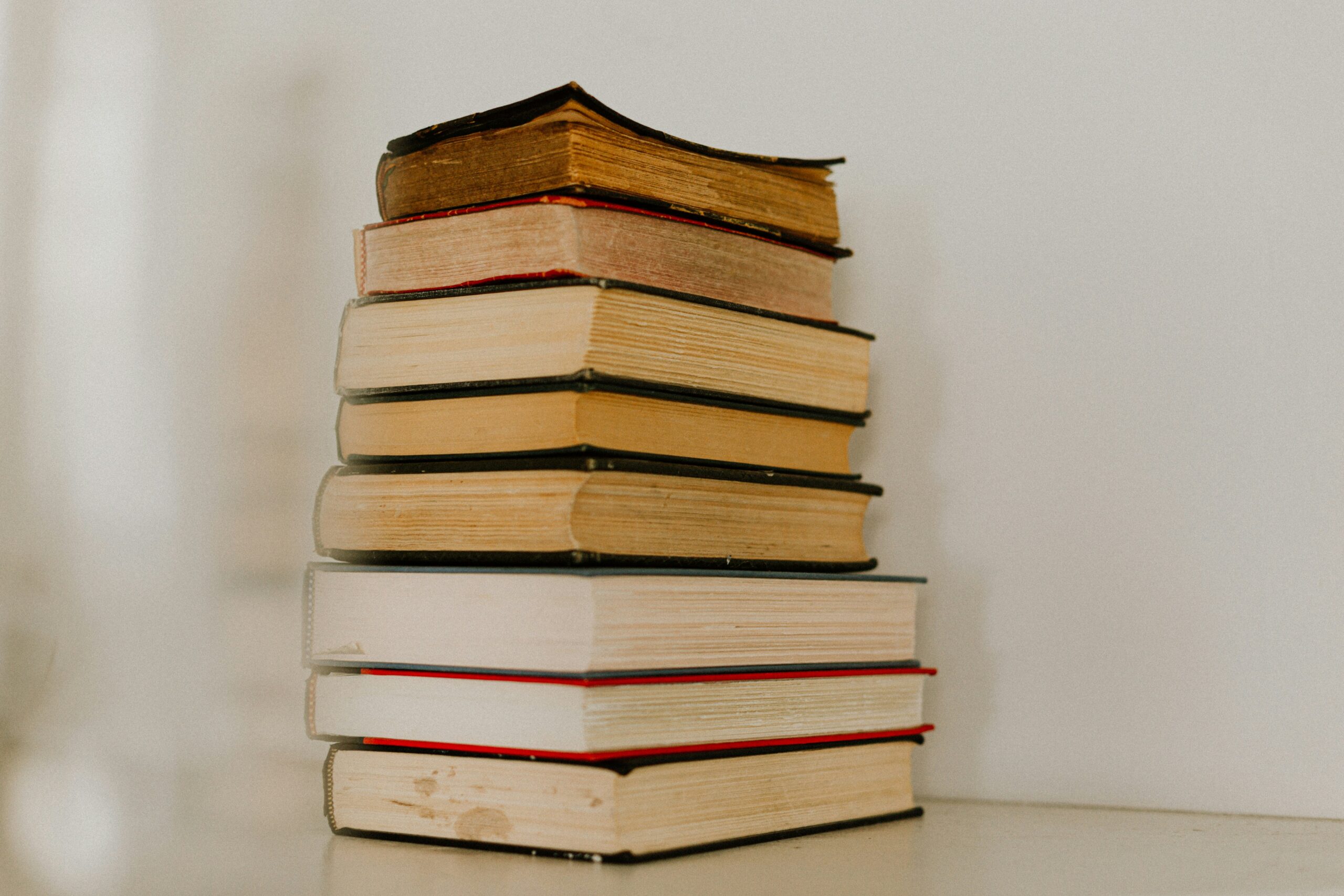https://www.diamond.co.jp/book/9784478116548.html
掲載情報
書籍タイトル: NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書
著者: NPOカタリバ、成田慶一(臨床心理士・公認心理師)他
出版社: [(出版社名)]
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/aC3iMh5
親の最初のひと言が未来を決める
「学校に行きたくない・・・・・・」。ある朝、お子さんが、そうつぶやいたら、あなたは、まず第一声、なんと声をかけますか。
この本では、このつぶやきに対する親の「最初のひと言」が不登校という長いトンネルの入り口での親子の関係性を決定づける、最も重要な鍵であると示します。
不登校は、親世代(40代)が10代だった頃の5倍以上にも増加しており、もはや特別な家庭が抱える特別な問題ではありません。この事実は、親の罪悪感や焦りを和らげ、冷静な対応を促すための最初の前提となります。
「NPOカタリバ」のこれまでの指導経験や知見に基づき、この書籍は「親が感情的にならず、子どもが最も必要としている「心理的な安全性」をどう提供していくか?」という具体的な対話と哲学を教示します。
私たちはこの支援の核心を、子どもが抱える「既存の学校システムや社会の規範に対する違和感」を否定せず、「子どもが自らの人生の主人公である」と信じ、伴走者となるという大事な考え方として、読み解いていきます。
ポイント:孤独を防ぐ「対話」と「安全の補給地」
パニックを止める「最初のひと言」の技術
不登校支援における最初のステップは、まず「親のパニックを止めること」です。親の不安や焦りは、そのまま子どもに伝わり、子どもをより孤立させます。
・ 判断を保留する: 「どうした?」「何かあった?」と問いかけ、子どもが「学校に行きたくない」と感じている現実をそのまま受け入れることから始めます。
・ 状況の分析: 親が冷静さを取り戻した後、初めて子どもが学校を休むことで「何を回避しているのか」「何を得ているのか」を客観的に分析するフェーズに移ります。これは、感情的な叱責を避けるための技術です。
独自の視点:違和感の肯定と「伴走者」の役割
この本で親が学ぶべきは、子どもの違和感を否定せず、自立を尊重する「伴走」の哲学です。
・ 自立の尊重: 親は子どもの人生という旅の目的地を指示する「司令塔」や「指導者」ではなく、子どもが選び取った道に対し、共に悩み、共に学ぶ「伴走者」となります。
・ エネルギーの供給: 家庭は、子どもが選んだ道のりが困難であった時に、いつでも立ち寄れる「安全な居場所」でなければなりません。この役割を果たすためにも、親自身の「安心」が不可欠です。
この「伴走」の哲学は、単に甘やかすのではなく、子どもが将来、自分の違和感を力に変えて自立した人生を歩むための、最も重要な土台作りとなります。
この本について
相対評価
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや具体寄り。親の「対話」や「声かけ」といった具体的な行動に焦点を当てています。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェット寄り。子どもの「気持ち」や親の「寄り添い」を重視しますが、NPOならではの社会的な視点も加味されます。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。親子関係の再構築と子どもの心の成長という長期的な視点を重視します。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。親がどう「関わるか」という支援者の役割に焦点が置かれています。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。不登校の現状を社会的な問題として客観的に捉え、親のパニックを冷静に鎮める役割を果たします。
・ 発達特性との関連度: ★★★☆☆ 3(個々の特性よりも、対話による心のサポートという普遍的なアプローチが主軸)。
独自の観点:支援アプローチの相対的な位置づけ
・ 問題の断ち切りと可能性の拡張: 心理療法の一部が「悪循環」を断ち切ることに集中するのに対し、カタリバの支援は、その後の対話と多様な選択肢の提示を通じて、子どもが学校以外の居場所や学びを見つける可能性を広げる点に独自性があります。
・ 行動の強化と関係性の維持: 一部の支援法が親の「言葉かけ」や「具体的な行動」によって子どもの自信を外側から「満たす」ことに集中するのに対し、カタリバの支援は、親の「姿勢」で子どもの孤立を防ぎ、対話の窓を開け続けることに焦点を当てます。
この本は、不登校を「親の失敗」ではなく「子どもが社会の規格に合わない時の必然的な反応」と捉え、親が冷静な伴走者として立ち直るための指針となります。
まとめ:孤独な親の心を支える「伴走」の哲学
「学校に行きたくない」という子どもの一言は、親の孤独な闘いの始まりとなりがちです。この本は、その孤独な親の心を「あなただけではない」と社会的な視点から支え、親子の対話を継続するための具体的な「最初のひと言」の技術を提供します。
子どもが立ち止まった時、親がすべきは「指示」ではなく「対話」です。親がこの本を通じて、自分自身の不安をコントロールし、子どもの人生を深く信頼する姿勢を身につけることが、子どもの自立への最も確かな一歩となります。
同意したならぜひ著書を手に取り、専門家に相談してみましょう。また当サイト主催の「読書会」では、この本が示す対話の方法をより具体的に議論するセッションを企画中です。たとえば冒頭の子どものつぶやきに、あなたならどのように回答しますか?ぜひ、当サイト主催の勉強会や読書会にご参加ください。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/dXRMzkX
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
NPOカタリバとは、以前某県の教育施設でご一緒しました。とにかく担当の「子ども最優先」の姿勢に心を打たれるとともに、若者たちを上手にエンパワメントしていく巧みさ(本著でも「ナナメの関係」として紹介されています)も非常に勉強になりました。
そんな個人的にも大変お世話になっているカタリバさんの書籍ですから、ボクとしてもぜひ一読したい。こと現場で見かけたエモい彼らとは打って変わって、書籍ではとにかく「まず落ち着いて」と呼びかけている印象です。
そんな冷静で教科書的な全体ですが、最初と最後は代表の今村氏が、真摯な思いをもって語っています。
不登校の問題をどうとらえるかは、日本の未来を決める分岐点だとすら思います。不登校の子どもたちは、「標準」とされるものに抵抗なく合わせられる人たちが、見落としてきた大切なことに気づかせてくれる存在ではないでしょうか。
多様な個性を持ち、認知の特性も様々に違う人達が、それぞれの在り方を認め合いながら、どうこの社会とともに行きていけば良いのか。学校が、そんなことを体感的に学び合える場所になったら、この社会から孤独な人がもっと減るのではないかと思います。(P.24「不登校の子は、大切なことに気づかせてくれる」)
改めて、不登校を選んだ子どもこそが知っている”大切なこと”とは何でしょうか?この機会にぜひ、子どもとゆっくり、語り合ってみてはいかがでしょうか?