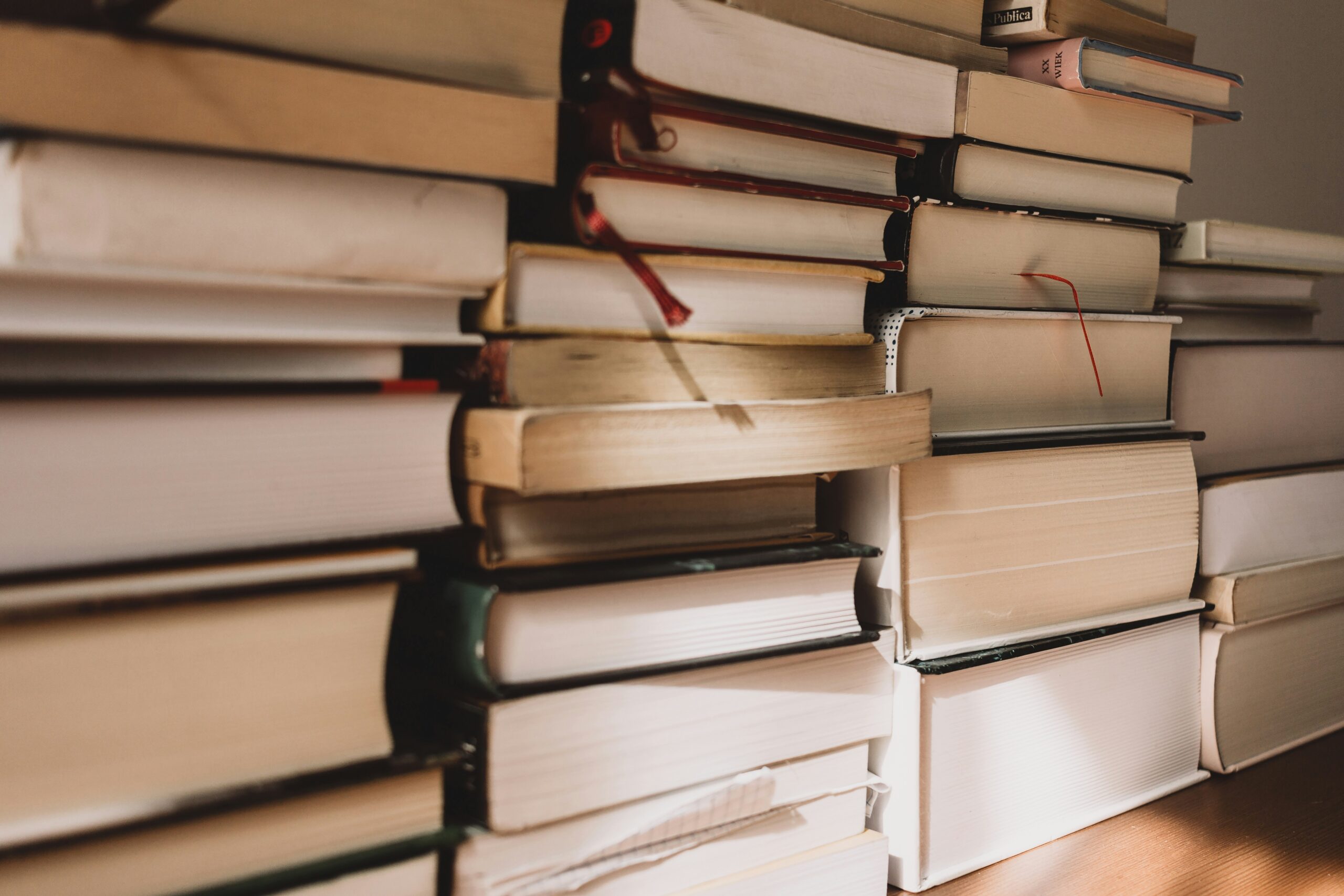https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB29482108
掲載情報
・書籍タイトル: 不登校に向き合うアドラー心理学:どうすれば子どもと親に勇気を与えられるのか
・著者: 深沢 孝之
・出版社:アルテ
・ご購入はこちらから:
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784434260261
劣等感は、人が成長するためのバネである
「劣等感は、悪」ですか?
「競争はいけないこと」と教える親の愛が、かえって子どもの成長機会を排除していませんか?
不登校の子どもの無気力や不安といった症状を前に、親は「自分の育て方が悪かった」「この子は劣っているのではないか」と悲観しがちです。
現代の子育ては「競争はいけない」という前提に立ち、子どもが劣等感を持とうものなら「ナンバーワンでなくオンリーワン」などの声かけで、その感情を打ち消そうとします。しかし人が成長するチャンスとは、他者との比較から生まれる「劣等感」を克服しようとするタイミングだったりします。この「劣等感をバネに頑張ろうとする姿勢」を止めてしまうのは、成長のチャンスをふいにするのではないでしょうか?
この本では「アドラー心理学」を応用し、不登校を劣等感の補償の失敗と捉え、「劣等感は成長のバネである」と肯定的に捉え直すことで親の罪悪感と悲観を解消します。アドラー心理学の核となる「課題の分離」と「勇気づけ」の技術は、不登校という状況下でこそ、親子が「ひとりの人」として向き合い、互いに成長するための道筋を示します。
ポイント:競争から共同体感覚へ 勇気づけの技術
劣等感の肯定と不登校の目的
アドラー心理学の「目的論」は、不登校の原因を過去のトラウマに求めるのではなく、「今、この行動によって子どもは何を達成しようとしているのか」という未来の目的に焦点を当てます。
・ 劣等性のバネ: 子どもが学校に行かないのは、決して「劣っている証拠」ではありません。それは、集団の中での競争や課題から逃れることで、「自分には価値がない」という劣等感をこれ以上強めないようにするための、無意識の防衛行動であると捉えます。この構造を理解することで、親は子どもを責めることなく、そのエネルギーの方向性を成長に向け直すことができます。
・ 競争から貢献へ: アドラーは、健全な劣等感は「もっと良くありたい」という努力と成長の源泉となると説きます。親や教師は、子どもを「他者との競争」から解放し、「共同体の中で自分は役に立っている」という共同体感覚(貢献感)を育むことで、劣等感を健全な成長のバネへと変える勇気づけを行うべきであると主張します。
課題の分離と「ひとりの人」としての対話
親が不登校という状況で陥りがちなのは、「学校に行かせること」を自分の課題(あるいは責任)と捉え、過剰な介入や管理を行うことです。アドラーの「課題の分離」は、この縦の関係を断ち切り、親子が”横”の関係で対話する土台を作ります。
・ 課題の明確化: 「学校に行く・行かない」は子どもの課題であり、「子どもの課題に過剰に介入することで生じる親自身の不安」は親の課題です。
・ 助けの明確化: 親は「放任」でも「過保護」でもなく、「ひとりの人」として向き合う態度を採ります。基本的に、子どもが「助けてほしい」という明確なヘルプ(”何を”、”どのように”助けてほしいか)を出すまで、過度な介入を控えます。この状況でこそ、助けを求めることと助けることの適切な境界線とスキルを親子で学び直す機会と捉えます。
この本について
相対評価
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや理論寄り。アドラー心理学の概念と、それを臨床・教育現場でどう応用するかという専門的な考察が中心。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ寄り。「目的論」「課題の分離」など論理的な分析枠組みを提示するが、「勇気づけ」という情緒的要素も核。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。「ライフスタイル」の理解や「共同体感覚」の育成という長期的な視点が中心。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。カウンセラー、教師、保護者といった援助職の「在り方」と「技法」が中心。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ポジティブに特化。劣等感を克服し、勇気づけを通じて健全な共同体感覚を育成するという、成長への肯定的視点。
・ 発達特性との関連度: ★★★★☆ 4。発達障害、不安、過剰適応など、不登校に複合的に関わる本人の「ライフスタイル」を深く分析。
独自の観点:自立と責任の哲学
・ 対話や行動療法との比較: 例えば「ブリーフセラピー」が悪循環の「解決」に焦点を当てるのに対し、アドラー心理学は不登校を「親子の関係性における縦の関係の失敗」と捉え、「横の関係(平等性)」の「再構築」に焦点を当てます。この再構築は、子どもの自立と自己責任の感覚を育む上で、他のどの支援法よりも哲学的基盤が強固であると言えます。
・ 倫理と平等: 親が子どもを一人の対等な人間として信頼し、勇気づけを行うことは、子どもの行動を操作するのではなく、生きる勇気そのものを与えるという点で、支援における倫理的な高さを保っています。
まとめ:勇気づけが、人生の主人公を呼び戻す
この本は不登校という困難な状況を、アドラー心理学という強力な理論的枠組みで分析し、親子それぞれの行動の「目的」を明確にします。
「劣等感は、成長のためのバネである」「課題の分離は、自立の第一歩である」。これらの概念を学ぶことは、親の不安と焦りを鎮め、子どもが自ら問題を解決する力を信頼するための勇気を与えます。
親子が縦の関係を解消し、横の関係で「勇気づけ」を実践するとき、子どもは他者からの承認ではなく、共同体への貢献の中に自分の価値を見出し、人生の主人公として立ち直る勇気を取り戻すでしょう。
本書は「不登校」と「アドラー心理学」を関連された珍しいものでしたが、こと「アドラー心理学」には他にも解説書が多数存在します。当サイト主催の「読書会」では、他書籍まで含めて「アドラー心理学」の具体(たとえば「課題の分離」と「勇気づけ」の技術)を詳しく解説しますので、ぜひ、当サイト主催の勉強会や読書会にご参加ください。
ご購入はこちらから
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784434260261