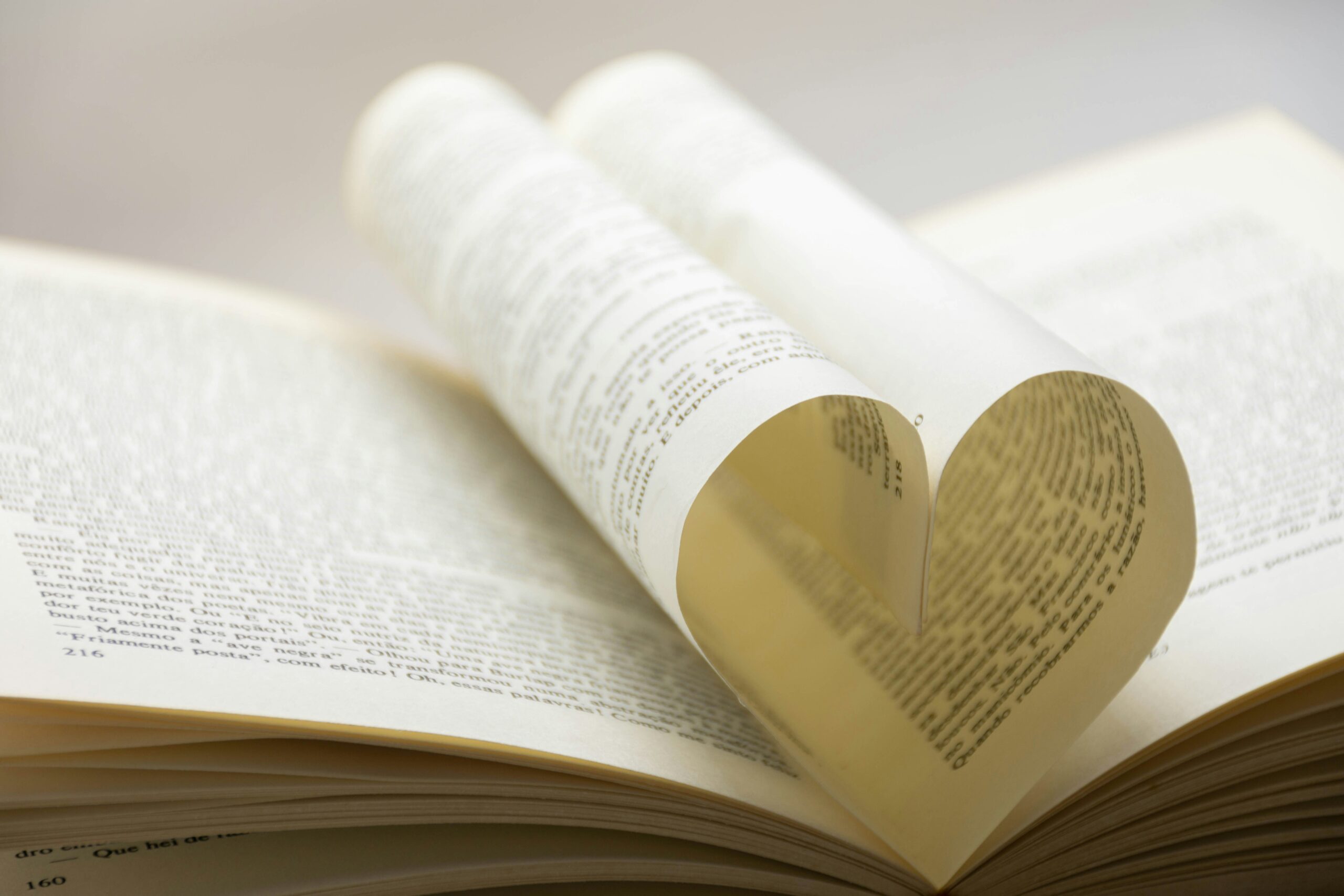https://www.toshobunka.co.jp/books/detail.php?isbn=ISBN978-4-8100-2767-9
掲載情報
・書籍タイトル: 不登校体験の本質と予防・対応 学校に行けない「からだ」
・著者: 諸富祥彦
・ご購入はこちらから:
https://www.toshobunka.co.jp/books/detail.php?isbn=ISBN978-4-8100-2767-9
「仮病」の真実
登校前の「腹痛や吐き気」を『仮病』だと疑ってしまったことはありませんか?
もしその症状が、『これ以上無理を続けたら壊れる』というからだの切実な警告信号だとしたら?
不登校に直面した親が抱える最大の苦しみの一つは、子どもの訴える身体症状に対する「疑念」と、それを信じられなかった「罪悪感」の板挟みです。しかし著者はハッキリと、子の訴えを「仮病ではない」と答えます。不登校とは子どもの「気持ち」の問題ではなく、本人もコントロールできない「からだ」(主観的な身体感覚)の変容によって引き起こされているという、新しい視点を提示します。
この本は、不登校の本質を”非意志的な現象”として捉え直します。子どもの「学校に行けないからだ」という不可抗力的な現実をありのままに受け止めることが、親の誤った介入を防ぎ、解決への第一歩となります。当サイトの哲学である「違和感を力に変える」という視点から見れば、この「学校に行けないからだ」は本人が否定できない「規格外の違和感」そのものなのです。
ポイント:「わけがわからない体験」への非介入的サポート
本書は、不登校の体験の多くが「からだ」の変容によって引き起こされ、本人はその変容に驚き、戸惑っている状態だと説明します。
「学校に行けないからだ」とは何か
・ 不登校の非意志性: 子どもは「行きたい」と思っているのに、朝になると腹痛や吐き気、体の重さなど、身体感覚が学校への道を遮断します。これは、本人の意志や心理的な問題を超えた、からだの防衛反応であると捉えます。
・ 自己の連続性の崩壊: 「これまでどおり学校に行ける自分」と「学校に行けないからだになってしまった自分」との間に生じる断絶こそが、不登校の本質的な苦しみであると解説します。
親と支援者がすべき「からだ」への尊重
不登校を「からだ」の変容として捉えることは、親や支援者に対し「気持ちを問い詰める」という無意味で有害な対応を止めるよう強く促します。
・ からだの安全性の確保: 親ができることは、子どもの「からだの変容」を責めずに受け入れ、家庭を身体的な安心感が得られる場所とすることです。本人の「からだ」が回復するための環境を整えることが、最も優先されるべき対応です。
・ 「なぜ?」を問わない: 「どうして行けないの?」という問いかけは、「からだの変容」という答えのない問いを子どもに突きつけることになり、さらなる自責と苦しみを増やします。この不可解な体験をありのまま受け止めることが、子どもの自立的な回復力を信じることに繋がります。
この本について
評価軸の傾向(ポイント形式)
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや理論寄り。不登校体験の本質を捉える現象学的考察が中心です。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ寄り。「からだ」という客観的な現象に焦点を当て、感情的な対処を排します。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 長期的な「体験の本質理解」と「予防法」に焦点を当てています。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。カウンセラー、教師、親への提言が中心です。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。不登校という現象を、倫理的な判断を加えず、ありのままの「体験」として捉えます。
・ 発達特性との関連度: ★★★☆☆ 3。感覚の過敏さや特性による「からだの変容」の理解に繋がる視点を含みます。
独自の観点:非意志的な「からだ」の尊重
・ 心理的なアプローチとの比較: 不登校を「心の傷」や「親子関係の悪循環」といった心理的・社会的な構造で捉えるアプローチに対し、本書は、それを可能にする根源的な身体の変容に焦点を当てる点で独自性があります。
・ 自立の哲学との共鳴: 「学校に行けないからだ」という不可抗力的な現実を認め、それを責めないことは、子どもの自己決定権(自立)を尊重する以前に、その存在そのもの(からだ)を無条件に肯定することに繋がります。これは、親が子どもの不可解な違和感を信じ、受け止めるための哲学的な基盤を提供します。
まとめ:親の「からだ」の理解が、子どもの「からだ」を解放する
不登校が長期化するにつれ、親は「なぜこの子は学校に行かないのだろう」という「気持ち」への問いに囚われがちです。この本は、その無間地獄のような問いから親を解放し、子どもの「からだが発するサイン」を読み解くよう促します。
子どもの「学校に行けないからだ」を、親が理性で理解し、無条件に受け止めたとき、子どもは初めて「わけのわからない体験」の孤独から解放され、自らの回復力と向き合う勇気を得るでしょう。
とはいえ、なかなか割り切れない感想も残るのではないでしょうか?当サイトの「読書会」では、本著で紹介された具体的なエピソードを紐解きながら、みなさんの体験談を基に対話していくセッションを企画中です。ぜひ、当サイト主催の勉強会や読書会にご参加ください。
ご購入はこちらから
https://www.toshobunka.co.jp/books/detail.php?isbn=ISBN978-4-8100-2767-9