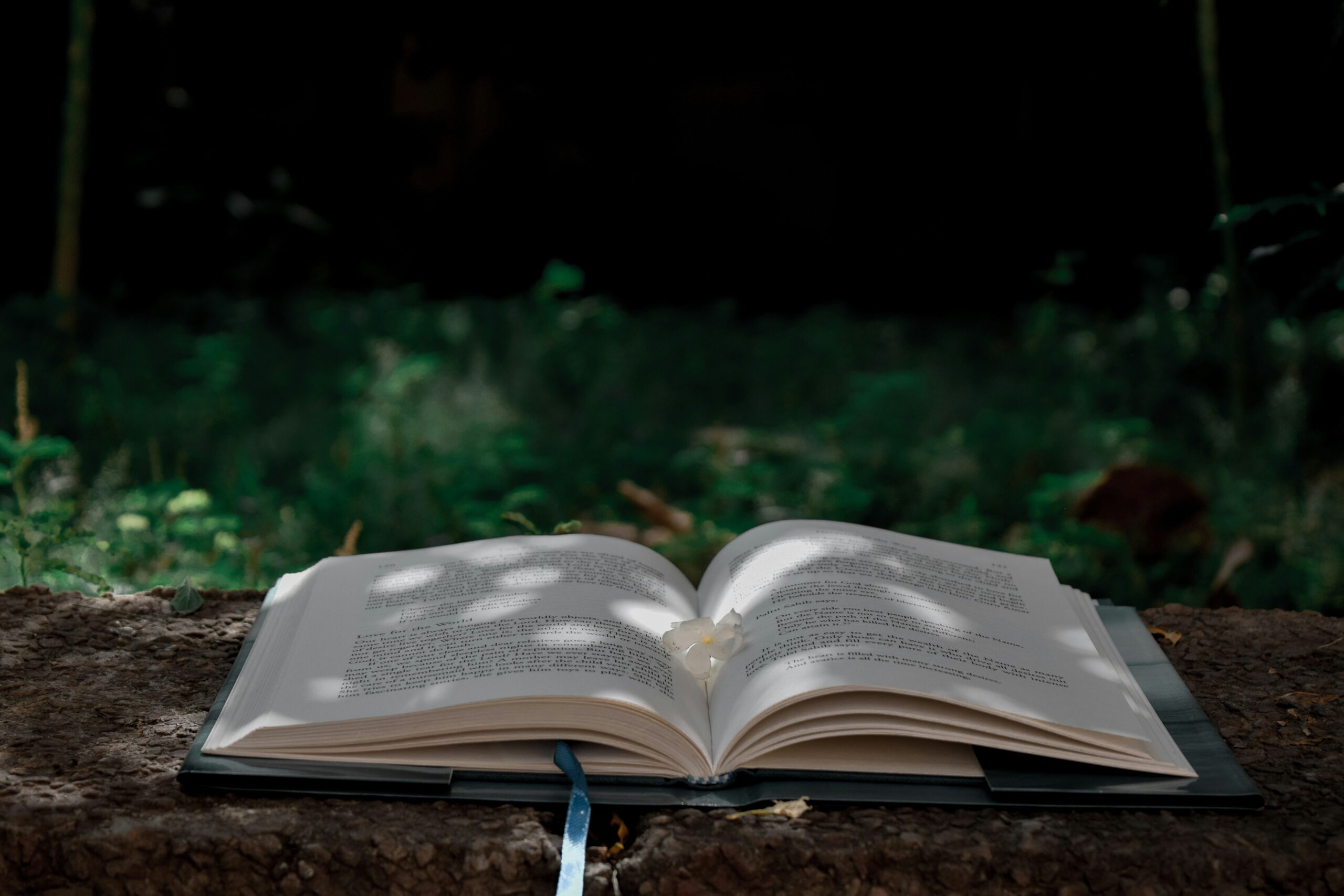概要
本書は日本の不登校研究史における最も深刻な問題、すなわち「本人・家庭原因説」の歴史と構造を徹底的に批判した専門書。著者は、この言説が不登校の当事者—子ども本人とその親—を深く傷つける性格のものであったにもかかわらず、専門家によって長期間にわたって主張され続けた事実を問題視し、論理的・方法論的欠陥と専門家の社会的責任を鋭く追及しています。
主要なテーマは、1960-90年頃までの約30年間にわたる不登校をめぐる言説について。この時期に日本の児童精神医学や臨床心理学の専門家たちが、不登校の原因を「本人の性格や親の養育態度に問題があるから起こる」と断定し、学校という「第三者」の責任を免除する役割を担ってきました。
本書の構成は批判の根拠を歴史的・学問的に確立するため、全9章からなる本論3部立てとなっています。
- 第1部では、不登校研究が始まる頃までの歴史研究が試みられ、不登校が「戦後の現象」であるという通説の誤謬を検証
- 第2部では、小泉英二や高木隆郎といった権威ある専門家による本人・家庭原因説の主張と、その論理的な破綻、そして最終的な放棄に至る経過が詳細に分析
- 第3部では、わが国の不登校研究全体が抱えていた方法論的な問題点(対照群比較の不在、国際的な自己訂正の遅れなど)を検討し、今後の生産的な研究のあり方へと提言
単なる学説の批判にとどまらず、専門職がクライアント擁護という基本理念から逸脱したときに、いかに当事者を傷つけ、社会に悪影響を与えるかを問いかける、専門家の倫理と社会的責任に関する問いを発しています。
不登校研究”前史”
不登校は”戦後”の現象か?
不登校に関する専門的な議論が始まった当初、不登校は「戦後の現象である」という通説が長期間にわたり、専門家たちの間では常識とされてきました。この通説は戦後の社会変動や核家族化、価値観の多様化といった社会状況を原因に結びつけ、不登校を現代社会特有の病理として位置づける論拠とされていました。
しかし本書では、この通説を歴史的な検証によって「誤謬(ごびゅう)である」と判断し、論理的な根拠を覆します。不登校が戦後に「発生」したという認識は、事実の混同から生じたものであると指摘されています。
著者自身、あるいはそのクラスメートの証言を通じて、戦前・戦中期にも、長期欠席を経験した、今日でいう不登校の様態を示す子どもが確実に存在していたという事実が示されます。また戦後まもない時期にも不登校を経験した人がいたという事実は、不登校が”特定の時代に突然出現した特異な現象ではない”ことを裏付けています。さらに戦前から、教職員の指導が原因で不登校が起こり得るという認識が存在していたことも明らかになります。
ではなぜ専門家たちは、「不登校は戦後の現象だ」と強く主張したのでしょうか。本書は、専門家たちが不登校の子どもと「出会い」を経験した時期(おおむね1954‐58年)を、不登校の「出現・発生」の時期と混同していた可能性が高いと分析します。すなわち専門家が不登校という現象を自らの研究対象として認識し始めた時期と、その現象が実際に社会で生じ始めた時期を専門家自身が誤って重ね合わせてしまったのです。この「出会い」と「出現」の混同は、専門家が自らの経験を出発点として理論を構築する際に、歴史的・社会的な検証を欠いたことの証左であり、その後の不登校言説に大きな歪みをもたらす端緒となりました。
浮き彫りにされた不登校と関連学会の発足
不登校研究の歴史は、臨床心理学の佐藤修策氏による論文(1959年)をもって学術的な対象として本格的に始まったとされています。この時期以前、戦時中や戦後まもない時期に学校を長期欠席していた子どもたちは多くの場合、「放縦児」や「不良児」といった問題行動のカテゴリーの一つとして扱われていました。彼らは当時の社会規範や学校の管理体制から外れた存在として周囲から干渉を受けない容認的な処遇を受けていたため、むしろ社会的な大きな問題とは捉えられていませんでした。
しかし1950年代後半から、日本社会には大きな変化が訪れます。高度経済成長に伴い、学校制度は国民全体に一律の知識と規範を注入する”絶対的、超越的な規範性”を帯びるようになります。学校に行くことが「普通」であり、「善」であるという社会的な心情が支配的になる中で、それまで長期欠席児童という枠の中に埋没していた「学校へ行けるはずなのに、行かない子どもたち」の存在が、社会規範からの逸脱として「不登校の子ども」問題として浮き彫りにされてきたのです。
この社会心情の変化は、学術界にも影響を与えました。1960年代前半に日本児童精神医学会や日本臨床心理学会といった関連学会が次々と発足します。これらの学会は、不登校の子どもを自分たちの研究・治療対象として積極的に取り込み、「治癒」「よくする」ことを通じて新興の学問としての有用性・効用を社会に示そうとした経緯があります。不登校という社会的問題を自らの専門的な領域に取り込むことで、学会や専門家自身が社会的な権威を獲得しようという、学問的なポリティクスが働いていたことが示唆されています。この「問題の発見」と「学問的権威の確立」が同期したことが、不登校の原因言説に偏りを生む大きな構造的背景となりました。
本人・家族原因説の主張と放棄
学会における本人・家族原因説の主張と放棄
不登校研究が学術的なテーマとして確立された後、その原因を「本人の性格や親の養育態度に問題がある(悪いところ)から起こる」とする本人・家庭原因説が、1960‐90年頃まで実に約30年間にわたって学界を支配しました。この言説は、不登校という問題の責任を学校教育から切り離し、すべてを当事者(子どもと親)に帰属させるものでした。
この原因説の論理的破綻を象徴するのが、「学校要因は誘因で、真因は親子関係ない本人のパーソナリティにある」と主張し、学校の責任を明確に否定した主張です(小泉、1978年)。論理の根幹にあったのは、「ごく少数の子どもしか不登校になっていないのだから、真の原因は本人・家庭にある」というもの。つまり学校に問題があるのなら、多くの子どもが不登校になるはずだ、という極めて単純な多数派の論理を根拠としていました。
しかし1980年代に入り、不登校の”増加”という現実がこの論理を根底から揺るがしました。不登校の子どもの数が「ごく少数」ではなくなり、「誰もがなりうる」という社会的な認識が広がるに及び根拠を失いました。小泉氏は1988年に至り、不登校の増加という現実に直面し、ついに本人・家庭原因説を放棄せざるを得なくなったのです。
本書は、小泉が用いた「ごく少数の子どもしか不登校になっていない」という論理が、厳密な根拠を伴わない表現上の言葉(レトリック)であり、非科学的であったことを鋭く批判します。このレトリックは、当事者を統計的な少数派として排除し、問題の責任を押し付けるための言葉の暴力に他ならなかったと総括しています。
なぜ本人・家庭原因説は主張され続けたか
この事例が示すように、論理的根拠が乏しかった本人・家庭原因説がなぜこれほどまでに専門家たちによって長期にわたり、しかも断固として主張され続けたのでしょうか。本書はその背景に、学問的な問題と同時に”専門家の内面的な倫理的葛藤”があったと分析します。
まず本人・家庭原因説の主張は、不登校の当事者クライアント、すなわち本来擁護すべき対象を「あなたの性格や育て方が悪い」という言葉で傷つける言動でした。これは「クライアントを第一義的に擁護する」という臨床心理学や医学の基本理念とは、全く逆の転倒した現象です。
この転倒が生じた原因として、専門家自身の社会的な立場が挙げられます。医学や臨床心理学の専門家たちの多くは、高学歴社会への恩恵を享受し、学校教育に対する強い親和性を内面化していました。彼らにとって学校というシステムは「良いもの」「正しいもの」であり、それを批判することは自らの社会的成功の基盤を否定することにつながりかねませんでした。この自己防衛的な心理が学校教育に対する批判的な視点を回避する動機となり、結果として原因を本人・家庭に求め続けることで「学校教育」という第三者の立場を”優遇”する、という深刻な倫理的問題を引き起こしたのです。
しかしこのような専門家の論理も、社会的な力には抗えませんでした。文部省による本人・家庭原因説の放棄は、不登校の増加という統計的な現実だけでなく、ポリティクス(社会史的背景)が大きく影響した結果です。具体的には法務省の調査結果が、不登校の原因が教師や学校にも十分に求められるという事実を公式に示したこと、戸塚ヨットスクール事件を契機とした体罰指導への社会的批判、さらには不登校経験者や親たちによる当事者運動の高まりが大きな社会的圧力となりました。これらの要因が文部省を動かし、本人・家庭原因説の放棄が決定づけられたのです。
本書は、文部省が本人・家庭原因説の放棄を決定した後も、専門家が不登校の原因を「本人の性格や親の育て方」に帰属させる言説を「もはや不可能になった」と考えたのではなく、「いまだに放棄することができない」という根深い問題が残ったことを示唆しています。これは専門家たちが、自らの内面化された価値観と、過去の言説への自己訂正の困難さという、二重の壁に直面していたことを意味しています。
不登校研究の問題点
「父性の不在/父親像の弱体化」原因説の盲点
本人・家庭原因説の代表的な論理の一つとして、「父性の不在/父親像の弱体化」原因説が挙げられます(精神医学者の高木隆郎氏による)。この説は1962‐85年までの約23年間という長期間にわたり、日本の学界でほとんど変化なく主張され続けました。この説は、不登校の子どもがいる家庭には母親の過保護や溺愛を抑制する「父性」が不在であるか、あるいは父親の権威や役割が弱体化しているという特徴がある、と指摘するものでした。
しかし本書はこの原因説の根本的な問題を、「対照群(control group)との比較検討の不在化」という方法論的欠陥にあったと断じます。不登校の子どもがいる家庭に固有の特徴として「父性の不在」を指摘しましたが、それが不登校”でない”子どもがいる「正常対照群」の家庭にも一般的に認められる社会現象であった可能性を検証しなかったのです。
1960‐80年代にかけての日本社会は、父親の長時間労働や家庭内での役割の低下といった「父性の不在」が社会全体で進行していた時期でした。したがって「父性の不在」は不登校群に固有の原因ではなく、当時の日本社会における普遍的な家族形態の特徴であった可能性が高いのです。
実際に「正常対照群」と比較検討を行った研究(1986年の三原論文など)では、不登校群と対照群の親の養育態度にほとんど差がないという結果が出ており、この原因説を支持しないことが明らかになりました。科学的な方法論を欠いた仮説に過ぎなかったにもかかわらず、専門家の権威を背景に長期間にわたって主張され続けたこと、その結果多くの不登校の父親たちを不当に責め立てたことは、専門家の社会的責任の重大な逸脱であったと本書は厳しく批判しています。
「肥大した自己像」原因説の行方
本人・家庭原因説のもう一つの論理的支柱として、「肥大した自己像」原因説があります(臨床心理学の鍵八郎氏による)。この説は不登校の原因を、子どもの持つ過大な自己像や強い自意識が、学校という現実社会からの批判や評価による「ずれ」を拒否するために、学校状況を拒否するというメカニズムに求めるものでした。すなわち「自分は完璧であるべきだ」という自己像と現実のギャップに耐えられないことが不登校の原因である、とするものです。
この同種の理論(レベンタールら)は、英語圏では1970年代にニコルズらによる批判的検証によって支持を得られず、事実上フェードアウトしました。なぜならこの説もまた、正常対照群との比較検証を行うと、説を支持するデータが得られなかったからです。
それに対し日本語圏ではこの「肥大した自己像」原因説が、1990年頃に至るまで権威ある専門家たちによって断続的に主張され続けました。この継続は単に対照群を用いた検証の不在化という方法論的欠陥の問題に留まらず、日本の不登校研究の学界が国際的な自己訂正の動きから約20年という大きな遅れを取ったことを示唆しています。これは日本の学界が外部の批判や科学的検証を積極的に受け入れる体質になく、国内の権威の論理が優先され続けた結果であると、本書は日本の学問の閉鎖性を批判しています。
1980年代の教育学による不登校理解
不登校研究の問題は、医学や臨床心理学の専門家だけに留まりませんでした。1980年代の教育学における不登校理解も、独自の盲点を抱えていたことが指摘されています。
1986年に教育科学研究会賞を受賞した横湯園子氏の中学教師時代の教育実践は、一見不登校の原因を「学校の問題」として捉える学校批判的な視点を含んでいるように見えます。しかしその実践の焦点は、体罰教師や差別的な教師の存在といった学校環境の病理性を温存したまま、問題解決を「子どもの内面の問題」、すなわち自己の再構成に帰結させるアプローチでした。
この指導は、子どもたちが自らの内面的な葛藤を乗り越えること、自分の生き方を見つめ直すことを促すものでしたが、これにより不登校の原因が学校の構造的な問題にあるという事実が、子どもの内面的な成長という教育的な価値によって置き換えられてしまいました。当時の教育科学研究会がこの実践を教育的な価値があるとして肯定的に評価してしまった点は、「学校教育」というシステムを擁護したいという教育学固有のバイアスが働いた結果であり、問題解決の責任を学校システムではなく子どもの内面に帰結させるという点で、本人・家庭原因説と本質的に同一の構造的欠陥を抱えていたと、本書は批判的に分析しています。
まとめ
本書の総括的判断は極めて厳しく明確で、不登校の専門家たち(児童精神医学、臨床心理学)が長期間にわたり主張した本人・家庭原因説は、方法論的、論理的な妥当性を著しく欠いていた仮説段階に留まるべき言説であったということです。この言説は科学的根拠よりも専門家の内面的な価値観や社会的な自己保身によって支えられてきた、非科学的言説であったと断じられます。
本来、教師との関係や学校環境が不登校の原因となり得る事実は戦前から存在していたにもかかわらず、専門家たちは「クライアント(当事者)を第一義的に擁護する」という臨床の規範に忠実ではなかったため、この事実に長く目を向けませんでした。専門家が自己批判を欠き、論理的妥当性を欠いた言説を振りかざした結果、当事者は不当な責任を負わされ、深く傷つけられるという、専門職の社会的責任の放棄という深刻な現象が引き起こされたのです。
本書は不登校問題を、特定の個人の病理としてではなく、1950年代の社会変化、すなわち学校制度の規範性の絶対化によって生じた社会現象として捉える相対化の視点の重要性を強調します。不登校は、学校という単一の価値観が絶対的になった時代に、その画一的なシステムに適応できなかった子どもたちが発した社会へのメッセージであったのです。
最終的に、不登校をめぐる言説が、専門家の論理的な自己訂正によってではなく、当事者運動や法務省の調査、マスメディアといった社会的なポリティクスによって動かされ、文部省による「本人・家庭原因説の放棄」が決定づけられた経緯を振り返ることは、極めて重要です。この歴史は、学問的な真実が、社会的な圧力と倫理的な要求によって初めて是正されるという、皮肉な現実を示しています。
本書は専門家の社会的責任を問い、過去の研究の誤りを明らかにし、生産的な研究が不登校に関して行われていくための契機を提供することを意図しています。この痛ましい歴史の検証を通じて、支援に関わる全ての専門職に対し、「クライアントの苦しみを第一に考えよ」という臨床の基本原則を改めて深く問いかけているのです。