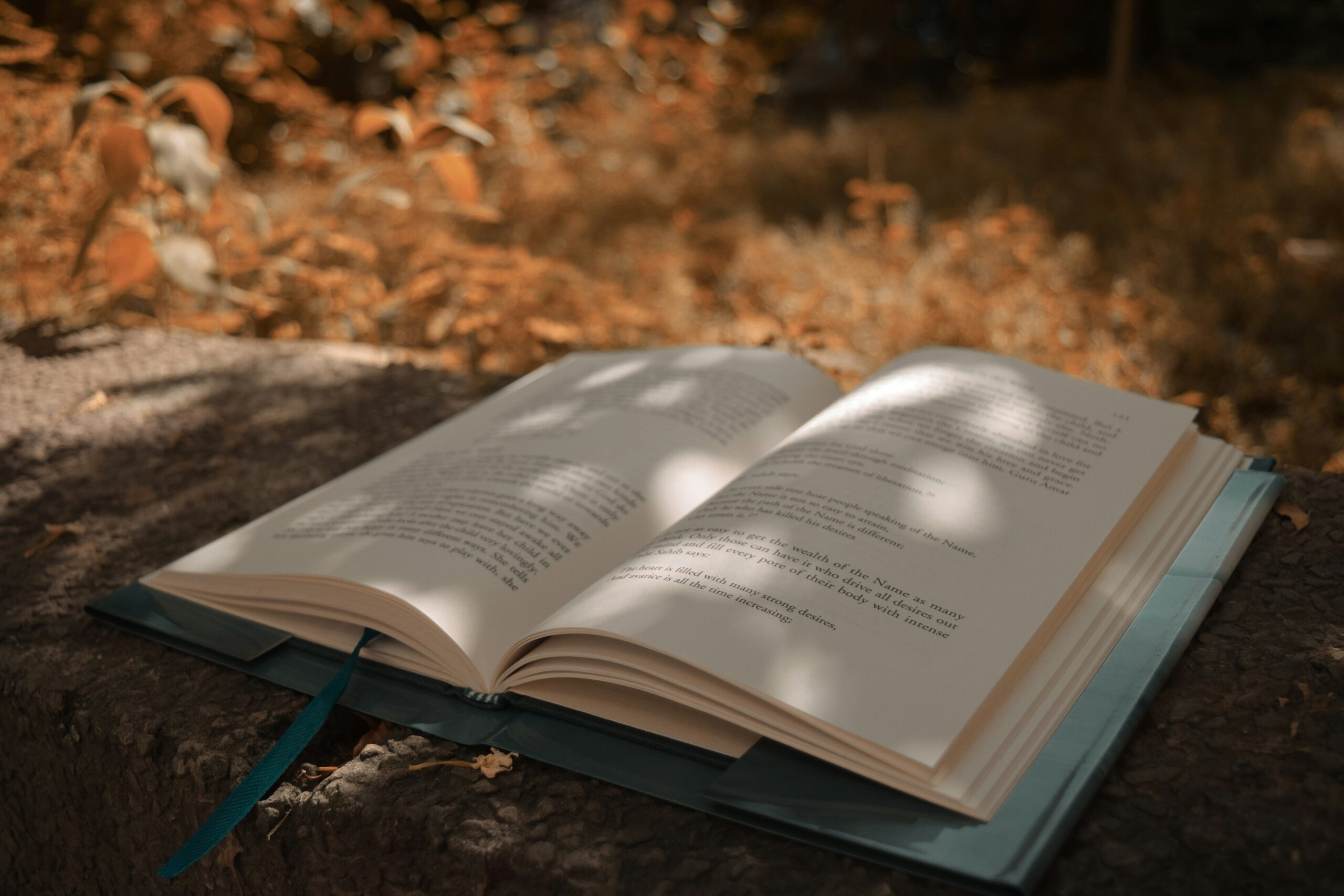https://www.kanekoshobo.co.jp/book/b184063.html
掲載情報
書籍タイトル: 不登校 その心もようと支援の実際
著者: 伊藤美奈子
出版社: 金子書房
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/eNtcz8z
統計という”大きな主語”からの解放
不登校のニュースで報じられる「過去最多」という数字は、親や支援者に焦りや不安を与えます。しかし、不登校の人数は数え方や定義で変わるため、数字の増減を眺めているだけでは、あなたの目の前にいる子どもの「心」は見えてきません。
本書は、不登校に関するさまざまな理論と調査データを示しつつも、それ以上に「実際にかかわりを続けてきた子どもたちであり、その保護者」の声と事例を重視します。
統計からみれば、「不登校」は「大きな主語」ということになりますが、現場の個別具体でみればそのひとつひとつが全然異なることがわかります。この本は、小さく小刻みに、微妙に変化し続ける子どもの「心もよう」を丹念に描き出し、「子ども一人ひとり」の「今」に向き合うことの大切さを教えてくれます。
親の心理的重荷からの解放:自罰の悪循環を断つ
不登校支援の難しさは、親(特に母親)が負う心理的な重荷に起因します。
母親の自罰と罪悪感の伝播
子どもが不登校になった際、最も大きな心理的負担を負う母親は、「学校や周囲の目に苦しみ、『子育てに失敗した』という自己否定感」を抱きやすいと本書は指摘しています。
- 自罰の悪循環: 母親がこの自責の念から自罰的になってしまうと、それは子どもの罪悪感まで強めかねません。「罪と罰」の構造は母子の共依存を生み、親の不安が子どもの心に伝播し、問題解決を阻害する「悪循環」を生み出します。
- 支援の第一歩: 母親の罪悪感や自罰を解消し、子どもの問題と切り離すこと(課題の分離)が、子どもの支援を始めるための必須条件です。本書が提示する「グループ・アプローチ」などは、親が孤立から脱却し、自己否定感を和らげるための具体的な手段となります。
支援の実際:長期的な「自立」への羅針盤
本書が不登校の「心もよう」の理解と「支援の実際」を結びつける試みは、過去の原因追及ではなく、「いま(心もよう)」を正確に把握することが、次にすべき行動(支援)を設計するための介入の設計図となるという点で、極めて実践的です。
克服の最終目標は「社会的自立」
この本は、克服の目標を単なる「学校復帰」ではなく、「子どもが自分らしい生き方を見つけること」を目標とした**「長期的な社会的自立」**に置いています。
- 違和感の肯定: 本書内には進路や「その後」まで射程広く語られています。目先の登校にこだわらず、学校外の多様な学び(フリースクール、通信制高校など)を許容し、子どもの「違和感」を大切に、自分らしく変わっていくきっかけにできると捉えるのが最善です。
- 選択肢の活用: 学校外の多様な学び方を許容し、子どもが自分にとって何が最善かを自己決定できるよう選択肢を示し、行動を支援することが長期的な自立を促します。
この本について
評価軸の傾向(ポイント形式)
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 理論に極めて特化。関係論、権利論、構造的な課題の分析が中心であり、具体的な対話テクニックや介入方法は薄い。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライに極めて特化。教育社会学的なデータ、論理、学説の分析が中心で、親の心情に寄り添う記述は少ない。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。不登校をめぐる社会構造、教育制度の歴史的な課題が主題であり、短期的な再登校を目指す人には不向き。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。学校、NPO、研究者といった支援システム全体への提言が中心。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。あくまで学校の”構造”的な課題を客観視し、居場所の必要性を論じる。
- 発達特性との関連度: 4(オルタナティブスクール利用者の背景として、発達障害や学習障害、社会的マイノリティとの複合的な関連をデータで提示)。
まとめ:不登校は統計ではなく、一人ひとつのゆらぐ「心もよう」への支援
本書は、不登校に関する「過去最多」という数字によるとらわれから見える「不登校だけでなく、個別具体の「心もよう」としての不登校を提示することで、画一的なイメージや価値観から親を解放し、目の前の子どもをただ丹念に理解することの重要性を説きます。また親の「自罰」を止め、「誰も悪くない」という安心感を取り戻すことも、支援の第一歩です。
また目先の登校にこだわらず、多様な学びの選択肢(フリースクールなど)を許容し、子どもの「違和感」を自分らしい生き方の土台へと変える、長期的な「社会的自立」こそを最終目標とします。この本は、臨床の最前線から、親子の消耗戦を終わらせ、子どもが自分自身の人生を紡ぎ始めるための、確かな羅針盤となるでしょう。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/1hZcVBX
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
- 「ロープを手放さない」
本書は、不登校の歴史的変遷と今後、また思春期特有の心理的課題「心もよう」(アンビバレントな感情、言語化されない苦悩)、さらに進路や学校側の対応など大規模データと臨床事例から多角的に分析した幅広な観点、いわば「不登校の教科書」的一冊でした。
著者伊藤氏は元教師でありさまざまな不登校と現場で向き合って来た方ながら、その語り口は実に冷静で客観的、また過去の成功事例に囚われずさまざまな可能性を提示されているところも、実に素晴らしいと思いました。
不登校についてさまざまな語り口から著者なりの考えを論じてきた。しかし著者が出会い見聞きしてきたのは、ますます多様化する不登校のごく一部に過ぎない。自分の経験を絶対視することはできないし、普遍化することもできないだろう。不登校の子ども一人ひとりが異なるように、不登校に対する見方・考え方に唯一絶対の「正解」はないと思う。そのばその場で迷い悩みながら、その子にあった「答え」を探すことが大切である (「さいごに」より)
また上記観点から「心もよう」とし、生徒に最大限リスペクトを払いつつしかし刻々と微妙に変化する「心もよう」を、とある中2女子とのやりとりから、このようにも表現されている。
「私は、学校という一本の長いロープの先を握っている。もう一方の先を握っているのは(顔は見えないけど)私の先生。もし先生が「あなたに会いたい」と言って、ロープの先をぐいぐいと引っ張ったら、私は怖くなってロープを放してしまうと思う。だからそれはやめてほしい。でも、私の「会いたくない」という言葉を鵜呑みにして、先生の方からロープを手放してしまったら、私の手にはロープの先しか残らない。だらんと垂れ下がったロープの先には、もう先生はいない。それも悲しい…」
彼女が望んだのは、先生にはいつもロープを握り続けてほしいということだった。自分の心のエネルギーが回復して先生に会える元気が出てきたときには、ロープを引っ張って合図をするから、そのときにはすかさず引き返してほしい。会いに来てほしい。でも、それまでは、私の顔が見えなくても、ロープの先に渡しの手があることを感じながら、ピンと張った状態でロープを握り続けてほしい、ということだった。…中略…「待つ」にせよ「働きかける」にせよ、大切なのは、この関係を切らない(ロープを持ち続ける)という姿勢であろう。(「さいごに」より)
「心理戦」などとは言いますが、もう少し解像度高く見るなら「心もよう」であり、ロープの張りや引き方、またタイミングなど本当に微妙で些細で大事な対象を扱っている。その感覚を忘れないことが、支援者としてなにより大切なことなのだと改めて深く首肯した次第でした。