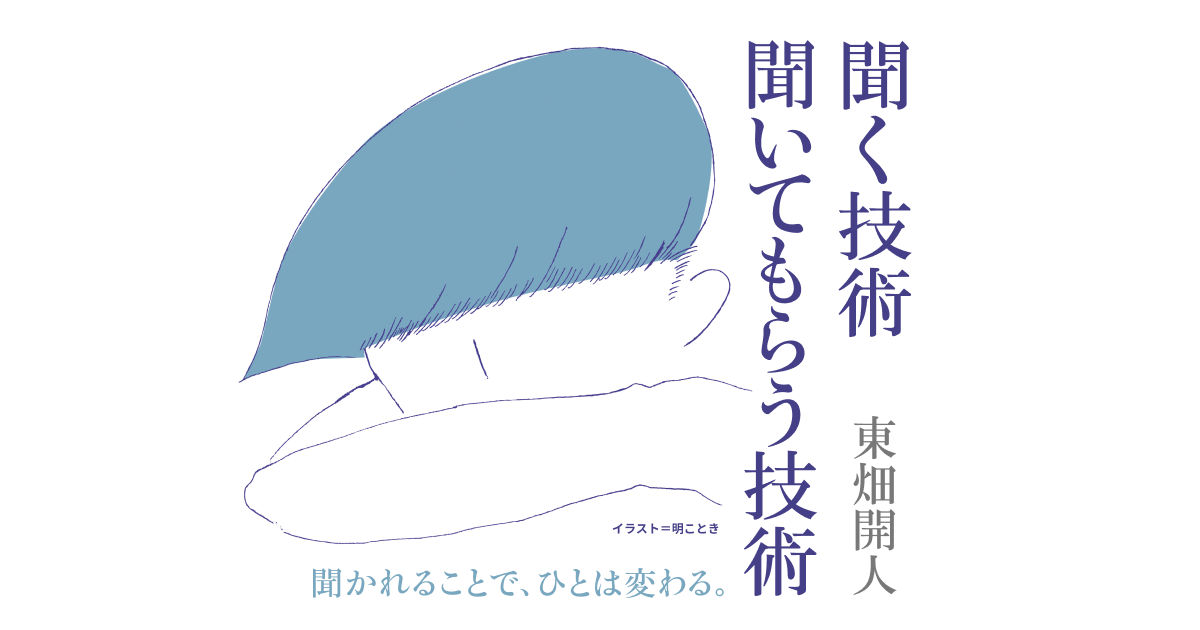
・書籍タイトル: プロカウンセラーの聞く技術 聞いてもらう技術
・著者: 東山 紘久
・出版社: 創元社
・ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/8BrqZxc
「聞く」ことは、「魔法」のような力を持っている
「子どもが何を考えているかわからない」「親の言うことを聞いてくれない」。不登校の家庭で頻発するコミュニケーションの悩みに対し、本書は「話し方」ではなく「聞き方」を変えることで解決の糸口を提示します。 著者は、長年臨床心理学の現場で活躍してきたプロカウンセラーの東山紘久氏。
本書は、カウンセリングの現場で培われた「聞く技術」を、家庭や職場などの日常会話に応用できる形で、具体的かつ平易に解説したロングセラーです。 「ただ聞く」ことが、どれほど相手の心を癒やし、信頼関係を築き、そして話し手自身(子ども)の問題解決能力を引き出すか。その「魔法のような力」を知ることは、焦る保護者の心を落ち着かせ、親子関係を劇的に変えるきっかけになります。
ポイント: プロが教える「聞き上手」の極意と「聞いてもらう」喜び
本書の核心は、「聞く」とは単に耳を傾ける受動的な行為ではなく、相手の心を開き、理解するための能動的な「技術」であるという点にあります。
・「聞く」技術の基本: 「相づち」や「繰り返し」といった基本的なテクニックから、相手の話を遮らずに最後まで聞く「沈黙の扱い方」まで、プロならではの具体的な技法が紹介されています。特に、相手の言葉を否定せず、評価もせず、ただそのまま受け止める(受容する)姿勢の重要性が説かれています。
・「聞いてもらう」ことの効用: 人は自分の話を十分に聞いてもらうことで、カタルシス(心の浄化)を得て、自らの力で問題の解決策を見つけ出すことができます。不登校の子どもにとって、親に「聞いてもらえた」という体験は、自己肯定感を回復させるための最も強力な栄養素となります。
・日常生活への応用: 専門的なカウンセリングルームだけでなく、家庭の食卓やリビングで、どのように「聞き上手」になるか。親子の会話、夫婦の会話を豊かにするための実践的なアドバイスが満載です。
この本について
・独自の視点
書籍の強みは、高度な臨床心理学の知見を、誰にでも実践できる「日常の技術」へと翻訳している点です。「話す」ことが重視されがちな現代において、「聞く」ことの価値を再定義し、人間関係の潤滑油としての機能を強調しています。
・相対評価
・評価軸の傾向(ポイント形式) 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 方法(具体)に特化。具体的な会話例や、やってはいけない「聞く態度」などが豊富に示されています。
・ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェット(感情)。人の心の機微や、温かい人間関係の構築に重きを置いています。
・今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 短期・長期の両立。今日から使える技術(短期)と、信頼関係の構築(長期)の両方を目指します。
・当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者(親・教師)目線。主に「聞く側」の技術を扱いますが、「聞いてもらう側」の心理も深く解説しています。
・ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ポジティブ。人間関係は「聞く」ことで必ず良くなるという、希望に満ちたメッセージです。
・発達特性との関連度: 2。特定の特性への対応というよりは、あらゆる人間関係に通じる普遍的なコミュニケーション技術を扱っています。
まとめ: 「聞く」技術で、家庭の空気を変える
本書は、つい「ああしなさい、こうしなさい」と口を出したくなる保護者に対し、「口を閉じて、耳を開く」ことの大切さと、その具体的な方法を教えてくれます。 親が「聞き上手」になることは、子どもにとって家庭が「安心できる場所」になることを意味します。親に話を聞いてもらうことで、子どもは自分の気持ちを整理し、混乱から抜け出し、自らの足で歩き出す準備を整えることができるのです。 この本は、会話のない食卓や、すれ違う親子関係に悩むすべての保護者に、「聞く」というシンプルで強力な処方箋を提供してくれます。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/8BrqZxc
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
「話し上手は聞き上手」とはよく言われますが、不登校の親御さんにとって「聞く」ことは、時として「待つ」こと以上に苦行かもしれません(普段、お忙しいですよね…)。しかし著者は、その苦労に見合うだけの価値が「聞く」ことにはあると断言します。 「聞き上手は、話し手に、自分のことをわかってもらえたという満足感を与え、信頼関係をつくり出す」 「話を聞いてもらうことによって、話し手は、自分の考えや感情を整理し、自分自身をより深く理解することができるようになる」。
つまり「(ただ)聞く」は、実はボクたちが考えている以上に”コスパ”がよいわけです。
また「聞く」ことは、相手をコントロールすることではなく、相手が自分自身で答えを見つけるのを手助けすること。不登校の子どもが必要としているのは、親の「アドバイス(正解)」ではなく、自分の混乱した気持ちをただ受け止めてくれる「器(うつわ)」としての親の存在です。 「聞く技術」を身につけることは、親自身の「忍耐力」を鍛える修行のようでもありますが、その先には、子どもとの新しい関係性が待っているはずです。
聞くことは、「魔法」であり「神秘」です。
苦境にあるとき、誰かが話を聞いてくれる。不安に飲み込まれ、絶望し、混乱しているときに、その苦悩を誰かが知ってくれて、心配してくれる。
ただそれだけのことが、心にちからを与えてくれる。現実は何も変わっていないのに、不安が和らぎ、考えるちからが戻ってくる。
これが神秘的だと思うのです。(「あとがき」より)
ボクたちが思った以上に「聞く」には魔力があり、一方「忙しさ」により失ってしまった、または「MP(マジックパワー)」を極端に損なってしまっているのかもしれません。
聞きにいきましょう!今すぐ大事な、目の前の人の話を




