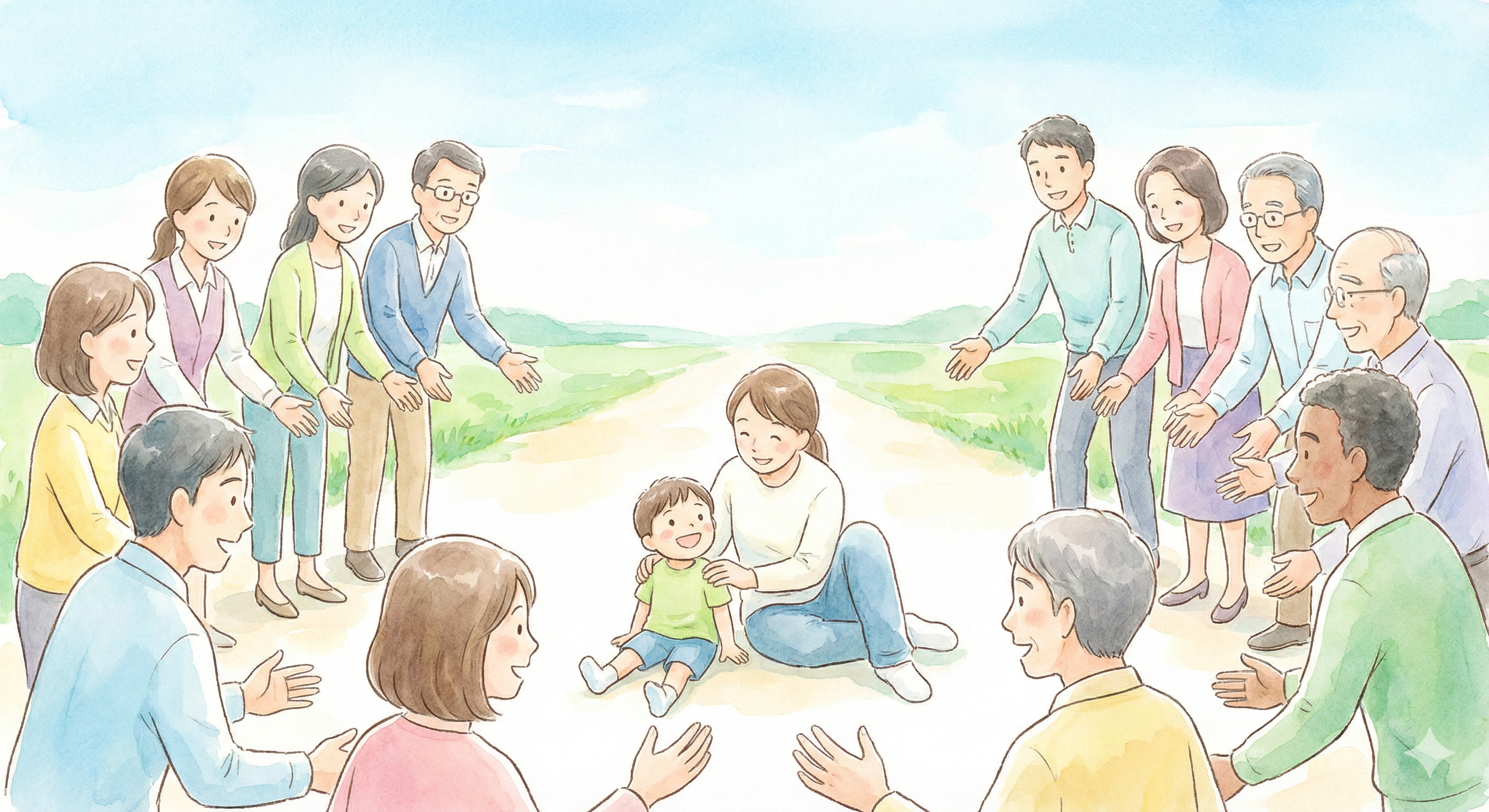- このページは、過去にご好評いただいた「学校や支援機関との連携方法」を、当サイト主催の勉強会参加者様の貴重な実体験コメントに基づき大幅に更新した【新版】となります。従来の学術的な知見に加え、当事者性の高い具体的なサインと初期対応の原則を凝縮しました。以前の記事をご覧になった方も、改めてこちら新版をご参照ください。
スミレ(※文責)、まる、いと、スガヤ
学校との連携は「言いなり」になることではありません。保護者が子どもの「代弁者」となり、外部機関を「利用する」ための賢いチーム戦略を、経験者の視点から伝授します。
前回までで私たちは、不登校の原因、回復への心の地図、そして具体的な居場所・学習・進路の確保の方法を学んできました。
しかしこれらの支援を成功させるため、最後にして”最大の難関”があります。
それが「保護者自身の心理的負担の解消」と、「学校や外部機関との連携」です。
保護者が一人で不登校の全てを抱え込むことは、長期的には親子双方の疲弊を招きます。「親(特に母親)の”笑顔”が子どもの回復を早める」という通説は実によく知られていて、筆者(スガヤ)自身もまずは保護者自身が心理的な安定を得ることがとても重要だと日頃から痛感しています。
この章では、保護者様の負担を軽減し、効果的に支援を進めるための具体的な戦略を解説します。
- 学校との連携: 支援を妨げる「3つの落とし穴」を避け、信頼関係を築くためのコミュニケーション術。
- 外部機関の活用: 臨床心理士、スクールカウンセラー、ペアレント・トレーニングなど、親の不安を解消するための専門的なリソース。
- 子どもの主体性を尊重する声かけ: 登校刺激にならない「共感と質問」の具体的なフレーズ。
この最終章を通じて、保護者が「孤独な闘い(あるいは長期の我慢)」から解放され、子どもの自立に向けた「チーム」として、周囲の社会と協力していく道筋を描きましょう。
1. 学校との連携:支援を妨げる「3つの落とし穴」を避ける
不登校支援において、「学校」は最も重要な連携先の一つです。しかし連携の仕方によってはかえって子どもの回復を妨げ、保護者の負担を増やすことがあります。以下の「3つの落とし穴」に注意しましょう。
落とし穴1: 過度な「再登校」への期待
保護者が学校側に対して「何とかして復帰させてほしい」という過度な期待を抱き、また伝えることで、学校は「登校刺激」を与えやすくなり、結果的に子どもはプレッシャーで心を閉ざします。保護者の体験談でも「先生の”熱心な”訪問のたび、子どもの元気が減り最終的には訪問を拒むようになった」との指摘がありました。
対応策: 連携の目標を「再登校」ではなく「子どもの心の安全と学習の継続」に設定し、学校と共有しましょう。学校がそれでも「再登校」を薦めてくる場合、意識的に一度、連絡を断つことも必要です(ある保護者は、わざわざ子どもに聞こえるように「行きたくなったらこちらから連絡します」と言い切り、電話を切ったそうです。個人的にもファインプレーだと思います。)
(元当事者スタッフ:スミレより)
不登校中、担任の先生が毎日のように家に来てくれるのが、結構プレッシャーでした。
先生がいい人だというのは分かっているんです。だからこそ、「期待に応えられない自分」が惨めで、チャイムが鳴るたびに布団を被って震えていました。
「そっとしておいてほしい」というのが、当時の切実な願いでした。
落とし穴2: 担任依存と情報不足
担任教師一人に全ての責任や情報共有を委ねることは、担任の負担を増やし、適切な支援を受けられなくなるリスクがあります。
対応策: 担任だけでなく、養護教諭、スクールカウンセラー(SC)、教頭など、複数の関係者と定期的に連携しましょう。子どもの変化(睡眠、食欲、機嫌など)を事実ベースで簡潔に伝える「交換日記」や「連絡メモ」の活用が有効です。
落とし穴3: 「なぜ行けないのか」という原因追及の対話
学校との面談では、どうしても「原因」についての話題が避けられず、受けてデリケートな責任を追及する議論に陥りがちです。こうなると学校はもちろん、保護者自身が余計に疲弊します。
対応策: 学校との対話は(過去は問わず)「現在から未来」に向け、「事実の確認」と「次の具体的なアクションの検討」に集中しましょう。「今日は何時に起きました」「宿題はどの程度進められそうですか」など、現在を踏まえて未来に向けた具体的な話に終始することで、面談の質が向上します。
2. 親の心理的負担軽減:外部機関の活用
「親の笑顔が子どもの回復を早める」と言われるのは、実は子どもは言語情報以外に”非言語情報(親の表情やしぐさ)”からより多くの情報を得るからです。なので親自身が”疲れ果てている”状況では、笑顔を見せることはできませんし子どもはより不安になり元気を失います。
(保護者:いと より)
子どものことばかり考えて自分のケアを後回しにしていた頃が、私のストレスのピークでした。あの頃が一番キツかったです。
その時、這うようにして診てもらったカウンセラーの先生に言われた「お母さんが倒れたら、誰がこの子を守るの?」という言葉で目が覚めました。
親が美味しいものを食べたり、愚痴をこぼしたりして「ガス抜き」をすることは、決して”ぜいたく”ではないです。長期戦を戦うため重要な「補給」なんです。
スクールカウンセラー(SC)とスクールソーシャルワーカー(SSW)
学校に配置されているSCは、子どもの心理的な相談だけでなく、保護者自身の心理的な負担やストレスケアについても専門的に相談に乗ってくれます。SSWは、経済的な問題や生活環境の調整など、社会資源の活用をサポートします。
臨床心理士とペアレント・トレーニング
家庭外の臨床心理士や専門機関を利用することで、学校や家庭の人間関係から切り離された中立的な立場からのアドバイスを得られます。
ペアレント・トレーニング: 子どもへの接し方や、課題行動への対応方法を具体的に学ぶプログラムです。親自身が行動を変えることで、子どもの行動が良い方向に変化する「支援の技術」を習得できます。
(編集長:スガヤより)
依存先が一つしかない状態を「孤立」とすれば、依存先がたくさんある状態を「自立」と言います(小児科医の熊谷先生に教えてもらいました)。
不登校支援も同じです。学校だけ、親だけで抱え込むと詰んでしまいます。
「勉強は塾」「心のケアはSC」「親の愚痴はママ友」というように、役割を分散させることが、家族全員の心を守る「最強のリスクヘッジ」になります。”ゆるい連携”を心がけましょう(お時間に余裕があればぜひ、ブックガイド|生きることは頼ることもご参照ください)
3. 子どもの主体性を尊重する声かけ:共感と質問
「見守る」ことが重要だと理解していても、つい「いつになったら学校に行くの?」と言いたくなり…実際に声に出してしまうのが保護者の常(もはや「業」)です。子どもの主体性を引き出し、登校刺激にならないための具体的な声かけの原則を学びましょう。
NGワード:「なぜ」と「いつ」
子どもが最もプレッシャーを感じるのは、「なぜ(原因)」と「いつ(期限)」を問われることです。これらは、子どもが自分を責めたり、親に対して嘘をついたりするきっかけになります。
魔法の質問術:「共感」と「提案」
大切なのは、子どもの感情を否定せず受け止める「共感」と、次の一歩を考える手助けをする「提案」です。
- 共感: 「しんどいんだね」「朝起きるの、すごく大変だよね」
- 事実の確認: 「昨日は夜中まで起きていたみたいだけど、何か面白いものを見ていたの?」
- 提案(選択肢の提示): 「今のしんどさを少しでも楽にするために、何か手伝えることはある?」「午前中に外の空気を吸いに行くのと、午後に少し本を読むの、どちらがいい?」
まとめ:不登校を「孤独な闘い」で終わらせない~緩やかな連携の必要性
この最終章を通じて、不登校からの回復には、子どもの主体的な回復と保護者の積極的な環境調整が必要であることをご理解いただけたかと思います。
そもそも不登校は、決して「家庭」内だけで解決できる問題ではありません(そもそも学校という「社会」との接点や関係での不適合なので)。保護者様が抱える「抑うつ」や「慢性的な高ストレス」といった心理的負担は、子どもに非常にネガティブな情報として伝わり、回復を妨げる要因となります。だからこそ、「親がまず元気になること、そして元気であり続けること」は、何よりも優先されるべき支援策なのです。
(元当事者スタッフ:まる より)
学校や親とうまくいかなくても、社会には「面白い大人」がたくさんいます。
私も地域の大人や、ボランティア先の大学生と出会って、「学校だけが全てじゃない」と気づけました。
保護者の方も、ぜひ外の世界とつながってください。親が楽しそうに社会と関わっている姿こそが、子どもにとって一番の「未来への希望」になるはずです。
不登校はたしかに大変な期間ではありますが、一方で「人生を生き抜く方法を”先取り”して親子で学んでいるのだ」と考えれば、きっと実りのある期間に変わります。
次回予告:専門家も活用する「質問術」
全章を通じて、私たちは「なぜ行かないの?」という問い詰める質問(空中戦)が、親子関係をこじらせる最大の原因であることを学んできました。しかし、では具体的に子どもに「どう声をかければいいのか?」という新たな疑問が生まれます。
次回の特別コラムでは、長年の対話のプロが編み出した「なぜ」と聞かない質問術に焦点を当てます。子どもの「言い訳」を引き出さず、本音と事実を淡々と引き出すための具体的な質問技法を学ぶことで、保護者のコミュニケーションの質を根本から変えるヒントをお届けします。
参考書籍
- 文部科学省「児童生徒の教育相談の充実について」/「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
- 日本小児精神神経学会「不登校の対応ガイドライン」
- 伊藤美奈子・阿部洋子『不登校児童生徒の母親の精神的健康と関連要因』
- ひきこもりUX会議「不登校・ひきこもりの当事者・経験者実態調査」