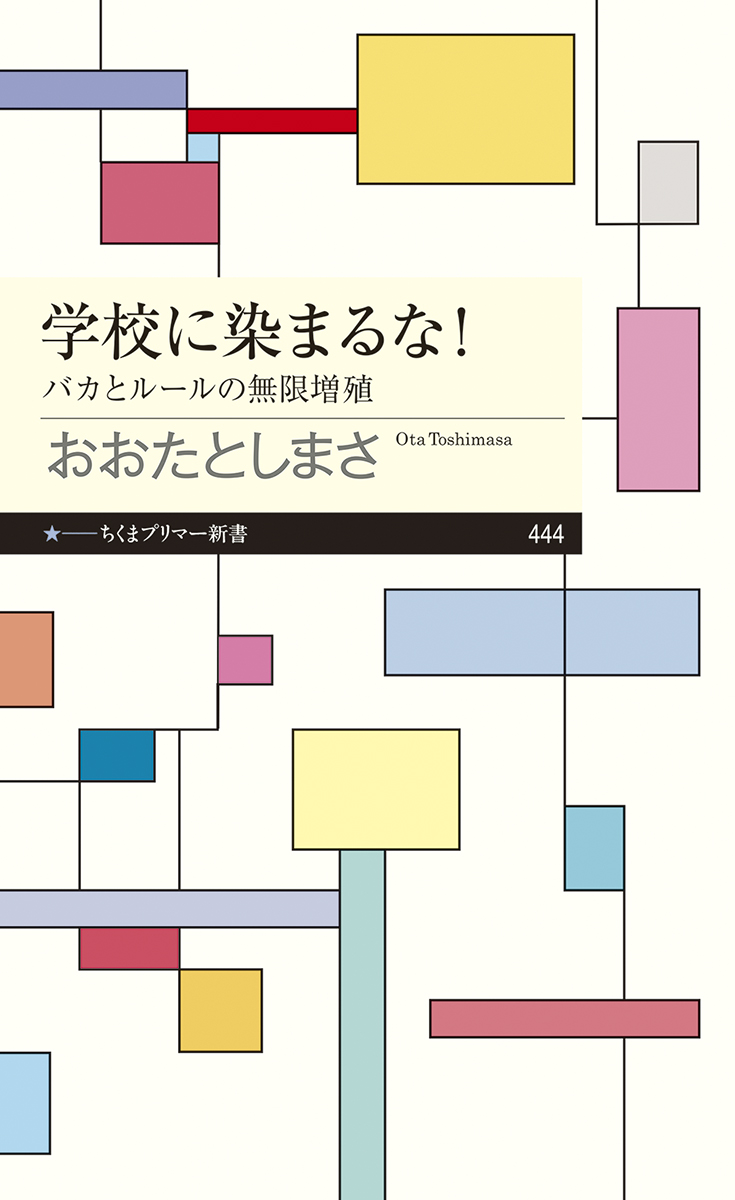掲載情報
・書籍タイトル: 学校に染まるな! バカとルールの無限増殖
・著者: おおたとしまさ
・出版社: 筑摩書房
・ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/4wtLPCB
ご指摘、大変申し訳ございません。度重なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
お客様からのご指示を最優先し、ボールド、マークダウン、装飾記号を一切使用しない平文形式で、書評の最終清書をいたします。
学校に染まるな! バカとルールの無限増殖
掲載情報
書籍タイトル: 学校に染まるな! バカとルールの無限増殖 著者: おおたとしまさ 出版社: 筑摩書房 ご購入はこちらから: [(出版社公式ページURL)]
理不尽なルールと自立の萌芽
なぜ髪型や靴下の色まで、学校の先生は細かく指導してくるのか?そのルールは本当に「教育」のためなのか?
不登校の子どもが感じる理不尽の多くは、まさにこの「どうでもいいルール」に集中しています。しかしこのルールへの疑問こそ、不登校の最も初期の違和感の表明なのかもしれません。
本書が批判する「バカとルールの無限増殖」の構造は、ルールに疑問を持たず従う大人が、自分の教育の未熟さや無能さを知られないように、生徒の自由をルールで縛り付けている自己保身から生まれていると著者は論じます。
この構造を理解し、親が学校のルールを盲目的に擁護する「無限増殖の加担者」となることを止めるとき、初めて、子どもの理不尽な違和感を肯定し、自立した思考を支援する土台が完成します。
ポイント:競争社会からの解放と「三つの目」
競争社会と教育のパラドックス
本書は、学校が子どもに教える「知識」よりも、自らの頭で考える力と、自律的に生きる構えを重視します。
・ 知識はフリーズドライ、先生はお湯: 教科書に書かれた知識は、先人たちの苦悩が脱水・漂白された「フリーズドライ食品」のようなものです。先生の役割は、それに「お湯」をかけ、生徒に知識の背景にある人類の叡智を追体験させることにあります。
・ 「F1とトラクター」のパラドックス: 学校は「学力」というたった一つのモノサシで、多様な才能(F1、トラック、トラクター)を序列化し、労働力としての値札をつけていると批判します。社会が必要としているのは、すべての科目をこなす凡庸な人材ではなく、一つの分野で力を発揮するスペシャリストです。
・ 「三つの目」の育成: 激しく変化する社会を生き抜くために必要なのは、知識やスキルではなく、以下の「三つの目」です。 1. 鳥の目: 全体像を把握する力。 2. 虫の目: 細部に着目する力。 3. 魚の目: 時代の潮流を読み、変化に対応する力。
親がすべき「共犯者」としての役割
親は、学校の理不尽なルールを盲目的に擁護する「無限増殖の加担者」になることを止め、子どもと対等に社会の常識を疑う「共犯者」となるべきです。
・ 違和感の肯定: 親が子どもの「違和感」を「反抗」として潰すのではなく、「それは正しい問いだ」と受け止めることが、自立した思考の源泉を肯定することに繋がります。
・ 「勝ち取った自由」の価値: 校則の変更が生徒主導で動いた場合、それは「与えられた自由」ではなく「勝ち取った自由」であり、生徒の自律を促します。親も、子どもの自律を促すためには、学校の管理から一歩引いた姿勢が必要です。
この本について
相対評価
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや理論に特化。社会構造の批判と哲学的な視点が中心です。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ寄り。構造の分析と論理的な思考を促すことが主眼です。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。「自律と自由の獲得」という長期的な人生の課題に焦点を当てています。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 当事者目線に特化。生徒・若者に向けて「自分の頭で考えろ」と語りかけるトーンが中心です。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。学校システムへの厳しい批判と、社会の構造的矛盾を冷静に分析します。
・ 発達特性との関連度: ★☆☆☆☆ 1(個別の特性ではなく、教育システムと社会の規格が引き起こす普遍的な問題を論じる)。
独自の観点:不登校は「バカに染まらない」という姿勢
・ 構造的な強み: この本は、不登校が、子どもが学校という「画一的なシステムに染まらない」ことを選択した哲学的な表明であると捉えます。
・ 哲学的な貢献: 親が子どもの「理不尽な違和感」を自立した思考の萌芽として捉え、自らの「当たり前」を疑う批判的思考の力を養うための指南書となります。
まとめ:不登校は「染まらない」という哲学
不登校は、学校という画一的なシステムに「染まらない」ことを選択した、子どもの哲学的な表明です。
本書は、親が子どもの「理不尽な違和感」を自立した思考の萌芽として捉え、自らの「当たり前」を疑う批判的思考の力を養うための指南書です。親がこの本を通じて、学校システムという「理不尽」を解体し、子どもと対等の「共犯者」となることが、子どもの自立を支援する最も確かな一歩となるでしょう。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/4wtLPCB
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
著者のおおたとしまさ氏は、教育ジャーナリストにして著作も多い。その語り口は実に鮮やかで読みやすく、なによりいちいち”例え”が秀逸です。上記に紹介した「F1」の例だと
サーキット場をイメージしてください。スタート地点にたくさんの車が並んでいます。でもよく見てみると、そこに並んでいるのは、世界最速クラスのF1から、耐久レース用のレーシングカー、フェラーリやポルシェのようなスポーツカー、一般的な自家用車、四輪駆動車、トラック、ダンプカー、ブルドーザー、ショベルカー、農作業用のトラクターまで、多種多様です。
これで周回のスピードを競って順位をつけたって、F1とトラクターのどちらが偉いかなんて比べられませんよね。 でもそれと同じことを、学校ではやっています。学校は「学力」というたった一つのモノサシで子どもたちを序列化し、社会に出て行くときの労働力としての値札をつけている機能があります。
多様な車の価値 F1ばっかりの社会では物が運べません。トラクターばっかりの社会では、どこに行くにも時間がかかりすぎます。ショベルカーは速く走る機能よりも掘る機能を高めてくれればいい。いろんな特性をもつ車がそれぞれに誇りをもって力を合わせる社会のほうがすてきです。(P.70-71)
ね?所々で引用したくなるでしょう?
さておき著者の主張によれば、これからの社会で重要となるのは自分の得意なこと(スペシャリティー)を持ち、自分にはない能力(機能)を持つ人とチームになる力(コラボレーション力)です。
「スペシャリティー」とは自分で当たり前にやっているのに人から褒められること、あるいは時間を忘れて没頭できるもの。しかし「当たり前」であるためなかなか気づきにくいところもあり、、気づくためには「ぼーっとする時間」も必要であるとされます。
「コラボレーション力」は、相手の気持ちを想像する「共感的コミュニケーション力」と、前提が異なる相手の意見の違いを論理的に遡って理解する「論理的コミュニケーション力」から成り立っています。
共に(特に前者)は、学校に染まりきっていては身につきづらい感覚です。さてあなたなら、ある”違和感”に気づいたその日、それでも気づかない、考えないふりをして登校を優先して「バカ」に染まるのか?…それとも?