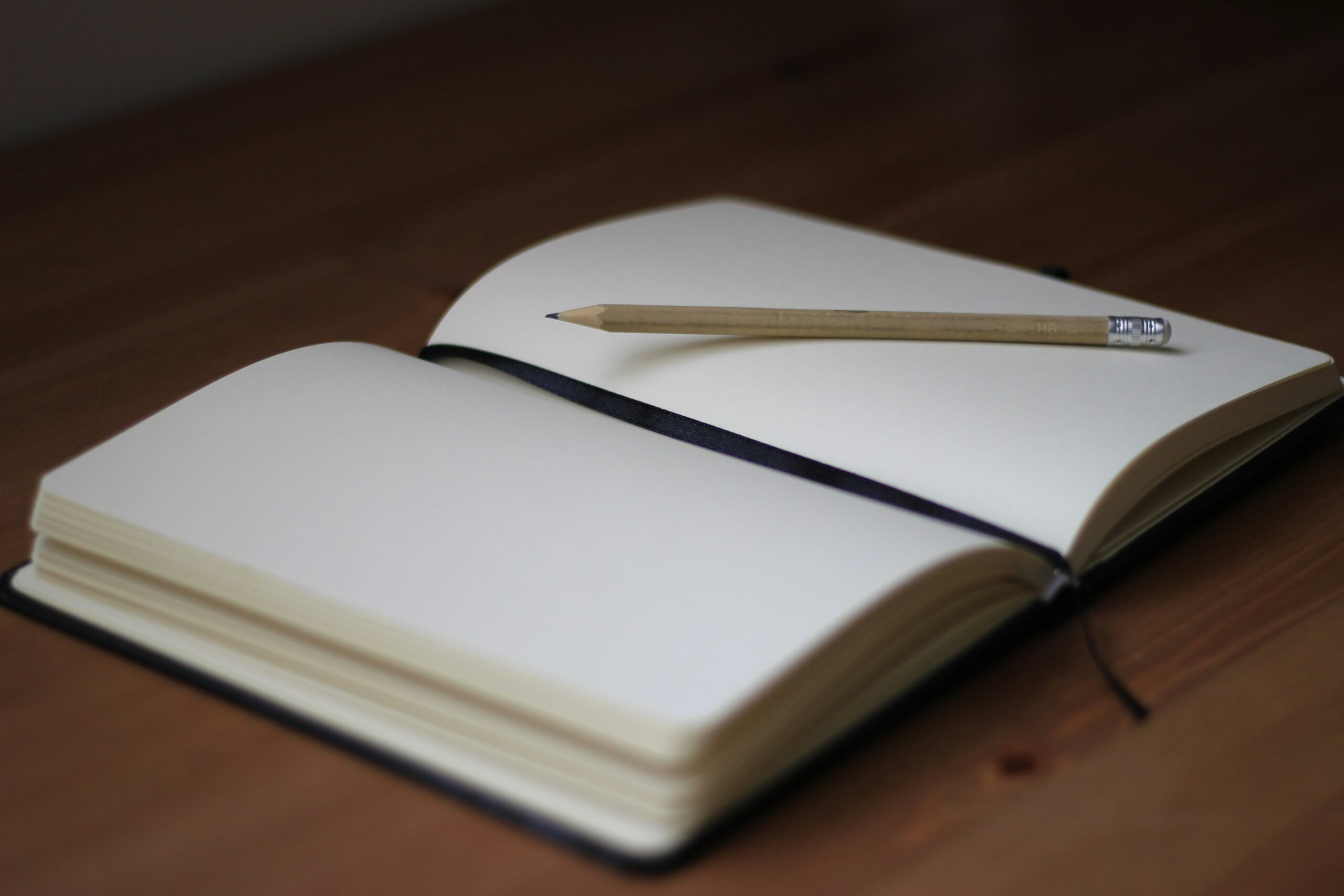掲載情報
・書籍タイトル: 登校しぶり・不登校の子に 親ができること
・監修: 下島かほる
・出版社: 講談社
・ご購入はこちらから:
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000324793
家庭は「絶対的な安心」の補給地
「学校を休ませることは甘やかしではないか?」 「現実社会はもっと厳しい、子育てもその厳しさを反映すべきだ」
不登校に悩み登校をすすめる親の根底には、このような価値観からくる罪悪感や焦りがあります。しかし本書では、これらの価値観こそが子どものエネルギーを奪いがちだと警鐘を鳴らします。家庭は、砂漠を行動するための「オアシス」でなければなりません。
この本が説く最もシンプルで重要な原則は、「家庭は絶対的に安心できるエネルギーの補給地でありたいもの」という考え方です。家庭の役割は、「甘やかし」ではなく、ただ「安心」できればよいのです。
著者は、不登校の子どもへの接し方のポイントを三つ示します。
・ 子どものエネルギーがたまるようにかかわること。
・ 子どもの選択や行動を尊重すること。
・ 子どもは本来、皆成長する力を備えていると信じること。
私たちはこの原則を、「自立した人生のドライバー」を育てるための戦略と解釈します。
独自の視点:助手席から始める「自立運転」の訓練
子どもの人生を長い車の旅にたとえるならば、「ドライバー」はいわんや”子ども自身”です。そのとき親は、助手席から「自立運転の技術」を教える役割を担います。さらに「車」のたとえで続けるなら
・仮免まで(運転技術の習得): まずは「ドライビングテクニック(ブレーキとアクセルの使い方)」を教えてあげましょう。この時、親がすべきは、「なんでできない」と叱責することではなく、「助言」や「フィードバック」を鉄則とする冷静な関わりです。
・ 路上への解放(信頼関係): ある程度、運転する力や知識が子どもの中についてきたと判断できたなら、あとは「路上」に放ってあげる勇気が必要です。ただしここでいう「放任」は「放置」でなく、「放って任せる」という”信頼”の姿勢です。ときどき様子を見てあげるのです。
・ 給油ポイント(家庭の継続): 親は、子どもがエネルギーを消耗し帰ってきたときに、いつでも燃料が補給できる「ガソリンスタンド」として笑顔で待ち構える役割まで。ときに「道に迷った」として立ち寄ることもありますから、そのときは一緒にルートを考えながらこれまでの道中を一緒に振り返るのもよいでしょう。
ポイント:不登校が表面化しやすい時期と潜んでいる根本原因
不登校はどの学年でも起こり得ますが、学校生活や環境が大きく変化する節目に問題が表面化しやすいという明確な傾向があります。特に以下の時期は、普段より多めに寄り添いたいところです。
・ 小1プロブレム: 小学校入学後に登校しぶりが生じる現象です。集団行動や規律が厳しく求められる生活へのギャップになじめず、ストレスを感じることが原因です。親はこの時期に完璧を求めず、小学校生活への緩やかな移行をサポートしましょう。
・ 中1ギャップ: 中学入学後に不登校数が増加する現象です。学習内容の難化や定期テストの導入による学業面での負担の急増、部活動や複雑な人間関係、思春期に伴う自意識の高まりがストレスとなります。親は特に丁寧な心のケアが求められます。
精神疾患・身体疾患のサインと専門家への相談
不登校が長期化したり、通常の心理的なアプローチが効果を発揮しない場合、根本に発達障害や心臓病、心身の病気、あるいはその他の身体的な疾患が潜んでいる可能性を検討する必要があります。
・ 起立性調節障害(OD): 朝起きられないという不登校のサインと類似するため、自律神経系の疾患である起立性調節障害(OD)の可能性を疑い、専門医による診断が不可欠です。
・ 精神疾患: 不登校が長期化し、強い抑うつ症状や幻覚・妄想などを伴う場合、うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患が隠れている可能性があります。
・ 医療機関での適切な治療: これらの病気の可能性を念頭に置き、親や学校のサポートだけでは対応が難しいため、医療機関での適切な治療と、専門医に相談する勇気を持つべきと筆者は強調しています。
この本について
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 方法に強く特化。親の具体的な対応と心構えが中心です。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェット寄り。家庭の安心感、子どもの気持ちの尊重を重視します。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。回復には時間がかかることを前提とし、長期的な成長を信じるスタンスです。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。親がどう行動し、どう支えるかに焦点が置かれています。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。現状を受け入れる冷静な視点と、多様な選択肢を提示する客観性を重視します。
・ 発達特性との関連度: ★★★★☆ 4(発達障害、分離不安、起立性調節障害といった医学的・特性的な問題を明確に区分して言及しています)。
独自の観点
構造的な強み: 小中学生の不登校という最も一般的な事例に焦点を絞り、親の冷静な対応と具体的な声かけ(対応と行動)に重点を置いた実践ガイドです。
方法論の応用: 感情論や精神論に陥らず、「家庭は補給地」という一貫した哲学のもと、医学的な疾患や発達特性の可能性も考慮に入れるという多角的かつ冷静な対応まで言及しています。
継続的な貢献: 子どもの人生の主導権(ドライバー)は子ども自身にあり、親は「助手席の助言者」として、自立を信じて見守る姿勢を徹底させます。これは親の過干渉や過保護を解消し、子どもの自立性を尊重するのに役立つでしょう。
まとめ:責任の放棄と自立への運転
この本は、親が抱える「甘やかしではないか」という罪悪感を取り払い、「家庭は補給地」という本来ありたい親の役割を明確にします。親が精神的に安定し、子どもの「自ら動く力」を信頼すること。これが、自立への運転を可能にする第一歩です。
これらによる支援とは、子どもが人生のドライバーとして「仮免」を経て「路上」へ出るまでを、親が助手席から冷静かつ愛情をもって見守る共同創造のプロセスです。親が「決めつけない柔軟な姿勢」と「相手のペースを尊重する心」を身につけることで、家庭内に新たなストーリーが紡がれ始めます。
この本が提示する具体的な対応方法は、親が自身の心労や焦りをコントロールし、家族システムの回復を導くためのものです。
ーーー
さてでは、親の「車検」はどのように行うとよいでしょうか?読後しばらくは「見守る」ことができたとして、気を許すとふと「過保護」「過干渉」になってしまいがち?ではないでしょうか。当サイト主催の勉強会では、定期的な親の「行動チェック」なども行っていますので、定期と言わずと気になった都度、ぜひお立ち寄りください。
ご購入はこちらから
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000324793