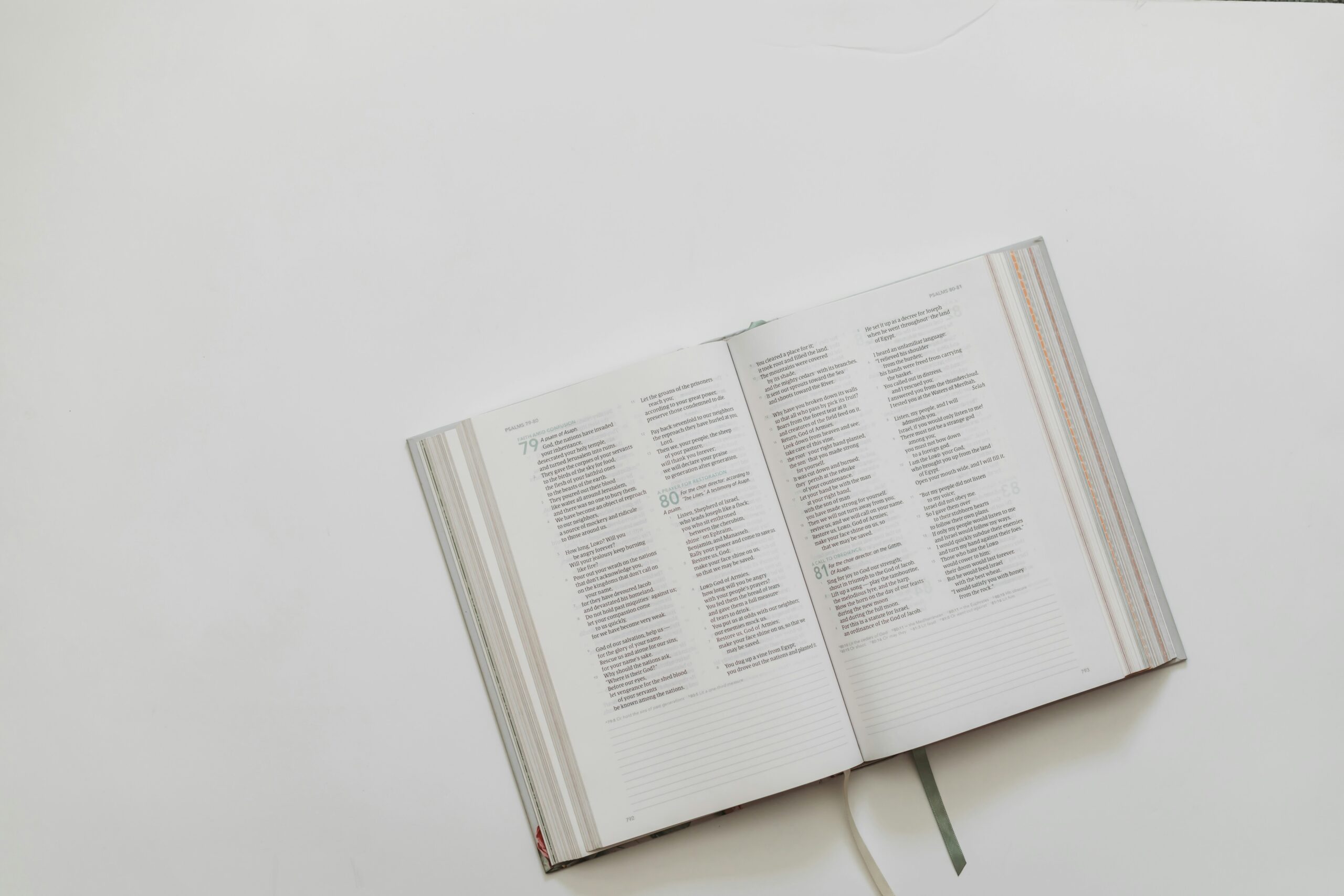掲載情報
・書籍タイトル: 不登校は1日3分の働きかけで99%解決する
・著者: 森田 直樹 ・出版社: リーブル出版
・ご購入はこちらから:
https://www.livre.jp/books/newbooks/sentence/1062
再登校を導く「99%解決」の約束
「不登校を99%解決」という驚異的な実績を提示するこの本を、あなたは信じますか?
解決策が見えない状況で、保護者はまず何を信じ、どう行動すればよいでしょうか?
「不登校」という”大きな主語”のもとで様々な焦りや不安を増幅させる言説が多いなか、本書は「保護者の協力が得られたケースでは、ほぼ百パーセント再登校している」という強い実績を提示します。
この「99%解決」という強い言葉の裏には、最も大切な「親の心身の中長期的安定」という不可欠な要素への貢献があると私は考えます。シンプルな「目の前の子どもを見る」、「ポジティブな側面に注目し強化する」という方法には悪いところが全くないからです。これまでの事例において、親の「不安」や「焦り」を解消し、冷静な行動を喚起する上で、この本の役割は極めて重要な行動指針となったのでしょう。
この「再登校」の保証は、親の自責の念や焦りを和らげ、「しょうがない」という冷静な受容へと導くのです。この安心感が、問題解決に向けた新たなストーリーを紡ぐための土台となります。
コンプリメントで大切な「3つのポイント」
著者は長年の教職経験と教育相談(カウンセリング)経験から、不登校の子どもを学校に戻すための効果のある「3つのポイント」にたどり着きました。
・ コンプリメント(心の水を満たす): 子どもの持つ良さや能力(リソース)を毎日3つ以上見つけ、その場で「〜の力があるね」といった言葉を添えて、親のうれしい気持ちを込めて伝える。これが子どもの心のコップに自信の水を入れ続け、自己肯定感を回復させます。
・ 愛情深く観察する(主人公を見つめる): 子どもを「主人公」として、愛情深く関心を持って観察します。問題行動ではなく、わずかな変化や努力に焦点を当てる。親の関心と愛情を子どもに伝えることで、愛情と承認欲求という心の栄養を一度に満たし、親子の信頼関係を深めます。
・ 原因探しを止める(未来志向の転換): 過去の不登校の原因(いじめ、親の育て方など)を追求するのを一切中断。問題の真因は”現在”、こと「心の栄養不足」にあると認識し、エネルギーを未来の行動(コンプリメントの継続)に集中させます。
このポイントは、子育ての根幹に関わる普遍的な原理に基づくとともに、やってしまいがちな「原因探し」を食い止めるため、将来(これから)へ向かう原動力と可能性を大きく育てることができます。
不登校のメカニズムと時間軸の認識
著者は不登校の真因を、”過去”かつ”特定”の出来事にあるのではなく、子どもの成長に必要な心の栄養(愛情と承認欲求)を満たせていないこと、つまり”現在”進行形の”心の欠乏”状態にあると断じています。
・ 再登校を導くため”原因探しを止める”: 多くの親や専門家は過去に遡って原因を特定しようとしますが、この行為は解決には繋がらず、むしろ親の罪悪感を強めたり、子どもを責めたりすることに繋がりかねません。支援の焦点は、過去の掘り起こしではなく、現在の心の栄養不足を補うという、未来志向の行動に注がれるべきなのです。
・ 「1年間」で解決の糸口を: 学校は一年間で体制や担当者が変わります。担任やクラス、学校の協力体制が変化する前に、一年間で解決の糸口を入れ、再登校に導くことが、問題の複雑化を防ぐ上で極めて重要です。短期集中型の解決を目指すべきです。
・ 待っていると、あっという間に時間は過ぎる: 親が「本人が動くまで待ちましょう」という体制でいることは、子どもの学業の遅れを招くだけでなく、留年やひきこもりになってしまう深刻な事態につながる危険性があります。親は、子どもの能力を信じ、その能力が発揮されるための環境と心のエネルギーを”提供”するという、”能動的な役割”を果たす必要があります。
この本について
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 方法(具体)に強く特化。コンプリメントという具体的な手法が中心です。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェット(感情)に強く傾倒しています。「愛情」「心のコップ」といった情緒的な概念が核です。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 今すぐ(短期)に特化しています。平均3ヶ月での解決実績や、1日3分の実践という速効性を強調します。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に強く特化しています。親の愛情と行動が、子どもの問題を解決するという、親の役割と行動変容を主題としています。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ポジティブ(肯定的)に強く特化しています。「不登校は治る」という強い希望的なメッセージを打ち出しています。
・ 発達特性との関連度: ★★☆☆☆ 2(発達特性への言及はありますが、「自信の水不足」による特性の顕在化と捉え、根本的な解決策は特性への個別対応ではなくコンプリメントによる心の栄養補給であるというスタンスです。)
独自の観点
構造的な強み: 「1日3分程度」という最小限の働きかけに方法論を単純化することで、親の心身の中長期的な安定という不可欠な要素に大きく貢献します。親の「不安」や「焦り」による過剰な干渉を止めさせる、実効的な方法です。
方法論の対極性: 単なる「待つ支援」を危険と見なし、「愛情と承認の言葉がけ」という能動的かつ短期間で可能な介入を通じて、子ども自身の自立を促すという第三の道を提示しています。
不変的な貢献: 再登校後も「再度の不登校になる子どもはいない」という実績は、「再登校」という単焦点(単なる登校刺激)ではなく、心のコップを大きく育てる「子育て」そのものに成功した証であり、子どもの自立と自己肯定感を育むという普遍的な原理に基づいています。
まとめ:心の重荷を降ろし、未来へストーリーを紡ぐ
・責任の放棄と自立への運転
この本は、親に「子育ては親の役目」と説きつつも、その方法を「一日たった三分間」という最小限の努力に単純化することで、親の心の重荷を降ろします。親が精神的に安定し、子どもの「自ら動く力」を信頼すること。これが、自立への運転を可能にする第一歩です。
「コンプリメント」による支援とは、子どもがもともともっている「資源」という燃料を信じ、親が冷静な会話を通じてその燃料を拾い上げる「共同創造」のプロセスです。親が「決めつけない柔軟な姿勢」と「相手のペースを尊重する心」を身につけることで、家庭内に新たなストーリーが紡がれ始めることでしょう。
・「上善如水」とコンプリメントの哲学
著書における「水」を、老子の説く「上善如水」(最高の善は水のような在り方である)の哲学と紐づけて考えてみます。
「コンプリメント」の考え方とは、親が子どもの心を育むための不変にして最高の在り方を示しているのではないでyそうか?
書籍が提唱するコンプリメント・トレーニングの根幹は、親が水を流す大河のように、執着や「べき論」を捨ておおらかであるよう示唆しているのではないでしょうか?なかで「不登校」とは、親の感情的な叱責や期待という「硬直した岩」によって子どもの心に愛情が流れ込まない「膠着状態」とも言えそうです。
コンプリメントが目指すのは、親が水のような柔軟な在り方になることです。
- 謙虚な姿勢(低きに流れる):親の弱さや不完全も認め、子どもの感情を受け入れ流すことから始めます。
- 柔軟性(器に応じる):子どもの「よさ」(リソース)を否定せず、「〜の力があるね」と、その子の形を承認することで、「自信の水」を満たします。
- 利他の精神(万物に恵み):親が「1日3分」という最小限の介入で純粋な愛情を注ぎ、子どもの自立という成長に奉仕する姿勢を身につけます。
親が水のように執着を捨て、ときにより臨機応変に形を変えながら愛情を注ぎ続けることで、その水で子どもの心のコップは満たされ、自ら動き出す力が育まれるのです。これが、コンプリメントによる「愛と承認」の哲学です。
著作では、これらコンプリメント継続のためサポートプランも紹介されています。気になったらぜひ、本著を手にとって早速実践してみませんか?