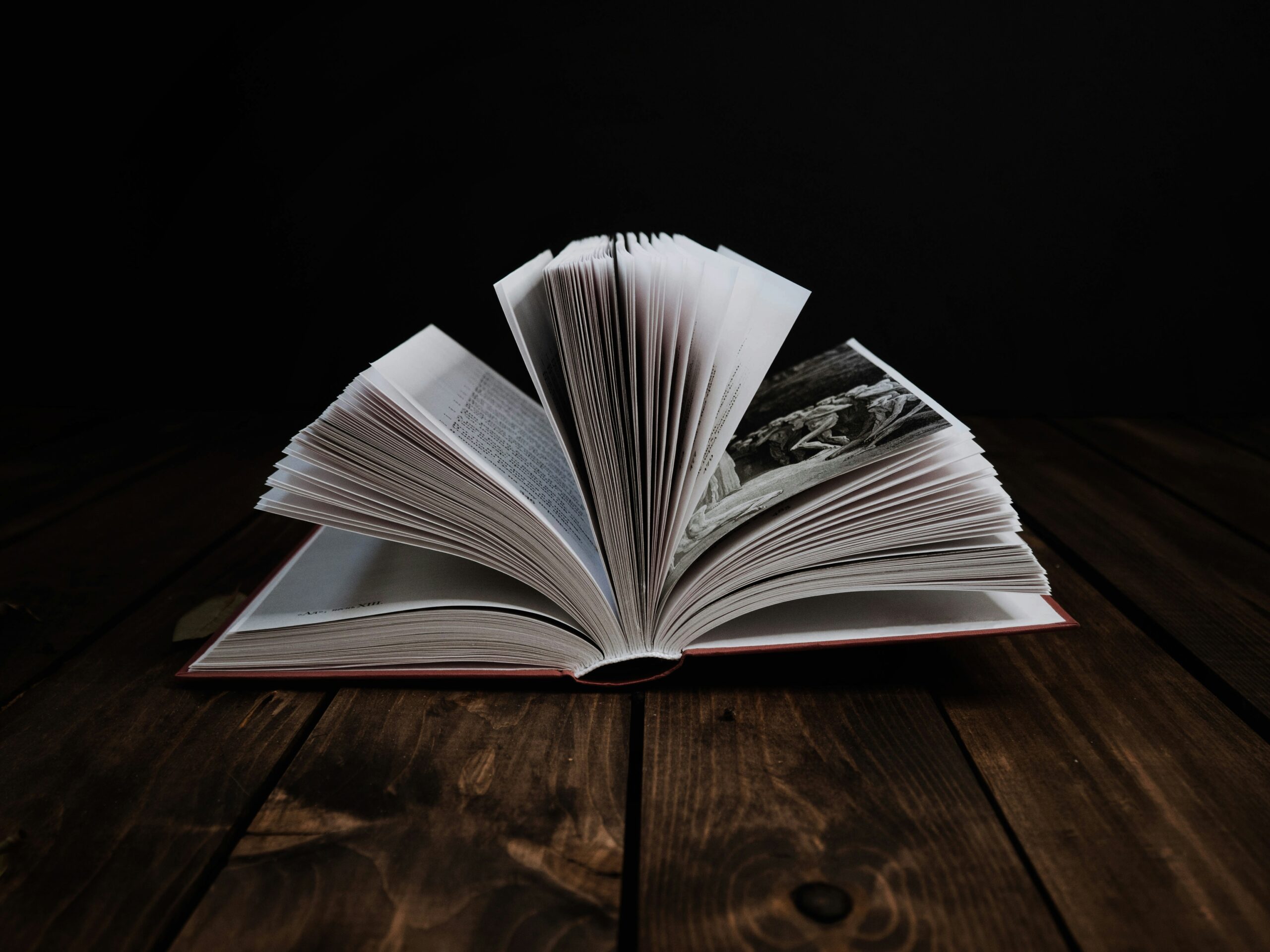https://www.shogakukan.co.jp/digital/098401750000d0000000
掲載情報
- 書籍タイトル: コンプリメントで不登校は治り、子育ての悩みは解決する ~子どもの心を育て自信の水で満たす、愛情と承認の言葉がけ~
- 著者: 森田 直樹
- 出版社: 小学館
この書籍は、森田直樹氏の提唱するコンプリメント・トレーニングという具体的な手法に特化し、親の感情的な関わり方を変えることに焦点を当てた一冊です。
他書籍との比較
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 「方法(具体)」に強く特化。コンプリメントという、親が日々行うべき言葉がけや行動変容の具体的な手法が中心です。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): 「ウェット(感情)」強め。「愛情」「心のコップ」「親の懺悔」など、情緒的な概念と親の体験談が核です。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 「今すぐ(短期)」に特化。平均3ヶ月での解決実績や、1日3分の実践という速効性を強調し、初期対応と行動開始を促します。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 「支援者目線」。親の愛情と行動(コンプリメント)が、子どもの問題を解決するという、親の役割と行動変容を主題としています。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的):「ポジティブ(肯定的)」に強く特化。「不登校は治る」という強い希望を提示し、「自信の水」を満たすことで問題を克服できるというメッセージを打ち出しています。
発達特性との関連度
- 発達特性との関連度: ★★☆☆☆ 2
- 補足: 発達特性(ADHDなど)への言及はありますが、それを問題の主因とするのではなく、「自信の水不足」によって特性が顕著に現れていると捉えます。根本的な解決策は特性への個別対応ではなく、コンプリメントによる心の栄養補給であるというスタンスです。
努力が裏目に出る親の「愛し方の間違い」
なぜ”褒めて育てて”いるつもりなのに、子どもはどんどん自信を失っていくのか?」
親が良かれと思って注ぐ「子どものための愛」が、実は子どもの心のコップを空にし、不登校を引き起こす「最大の原因」になっていたとしたら?
著者の森田直樹氏は、不登校の真因を子どもの心にある「自信の水不足」と分析し、その解決策は親が毎日行う「コンプリメント(愛情と承認の言葉がけ)」にあると説きます。著者はこの「自信の水」こそが、子どもが活動し、順当な成長を遂げるための「心の燃料」であると定義しています。
プロローグでは「お母さんうれしい」の一言が口から出ないという、親の懺悔にが紹介されます。愛し方を教わらず知らない親の「コントロール欲求」が、子どもにとっては「過干渉」や「支配」となり、結果的に子どもを救うべき親自身が愛情という名の”毒”を与えていたという衝撃的な事例でした。
コンプリメント・トレーニングは、親自身が持つ「愛し方を知らない(教わっていない)」という内面的な課題に光を当て、親子の信頼関係を根底から再構築します。このトレーニングの目的は、親が愛情を”表現”する力を取り戻し、子どもの自立に必要な「心の燃料」を満たすことです。したがって、「学校に行かない」という子どもの違和感を力に変えていくためにも、まず親が冷静にこの「今すぐ」できる具体的な手順と心構えを習得することが具体的な第一歩となります。
本書の核心:愛情と承認の言葉がけ「コンプリメント」の技術
本書が提唱する「コンプリメント」は、単なる「褒め言葉」とは一線を画します。子どもの存在(良さ)を親が心底から認め、愛情として伝える「愛情と承認の言葉がけ」の技術です。
コンプリメントの基本原理
- 目標は「心のコップを満たす」こと: 親がコンプリメントを継続的に注ぐことで、子どもの心のコップに自信の水を満たします。水が満たされると、様々な身体症状が軽減・消失し、自律的なな成長を始めていきます。
- 方法: 承認(「〇〇の力があるね」)と愛情(「お母さんうれしい」)という二つの言葉を使い、子どもの「したこと・できたこと」という事実に具体的に焦点を当てます。
コントロールと自立の「育て直し」
この方法論が真に価値を発揮するのは、親が自身の「コントロールの欲求」を反転させ、「自立への信頼」へと育て直す点です。
この方法論が真に価値を発揮するのは、親が自身の「コントロールの欲求」を「自立への信頼」へと育て直すプロセスにおいてです。
著者は「コンプリメントで親の思うように子どもを動かすことはできない」と明確に述べています。これは、親がコンプリメントを「操作の道具」としてではなく、子どもの主体的な「自己決定」を育むための「燃料」として用いるべきことを意味します。親が「学校に行ってほしい」という期待や、子どもを支配したいという意図を完全に手放し、純粋な愛情に切り替えるプロセスこそが、このトレーニングの最大の成果です。
この親の姿勢を試すように、コンプリメントが効き出す過程で子どもは「試し行為」を行います。例えば、幼児のような振る舞いをしたり、わがままを言ったりして、親の愛情を試してくるのです。親がこの「試し行為」にひるむことなく、純粋な愛情を注ぎ続けることで、崩壊した親子の信頼関係を根底から「再構築」していくことができます。
親が心得る鉄則:「安全」の優先と「孤立の排除」
当サイトがポリシーとする不登校支援において、親が心得るべき鉄則は「安全と健康の維持こそが家庭の最も基本的な機能であり、その優先順位は学業よりも上である」そして「親が孤立しない」という原則でした。
改めて本著に照らすならば…
身体症状の隠れた真実
- 子どもが訴える胃痛、頭痛、腹痛などの身体症状は、決して「仮病」や「甘え」と決めつけない。症状が登校回避と連動している場合でも、それは身体が発する切実なSOSです。
- 著者も、「病気のふりをしている、と決めつけないことが大切です。私は以前、登校する時に胃が痛むという九歳の女の子の治療をしたことがあります。みんな、この女の子が仮病を使っていると思っていましたが、実際には胃潰瘍だったのです。」と、具体的な事例を挙げて強く警鐘を鳴らしています。
医療の鑑別とセカンドオピニオン戦略
- 診断の優先: 登校しない理由が体の症状の場合は、まず医学的な診察と治療を受けましょう。特に、注意欠如・多動症(ADHD)やうつ病のような深刻な問題が疑われる場合は、精神科や心理の専門家の受診を検討してください。
- セカンドオピニオン戦略: 専門家からの助言を「セカンドオピニオン」として捉え、できるだけ多くの視点(教師、カウンセラー、医師など)を集めようとする姿勢が、親の判断の「主体的・自立的な」土台を築いていきます。「孤立」は不登校における最大の危険で、次に危険なのは一つの意見(専門家)に「依存」してしまうことです。
まとめ:心のコップが満たされた後の「自立」という名の運転
スタートライン:親の愛を”燃料”に変える
この本で短期的な”消耗戦(言葉のやりとり)”を乗り越えた読者ならば、次に不登校という機会を「自立」につなげていくという、より長期的にして本質的なテーマに向き合っていくでしょう。
コンプリメントを継続することで、親は「お母さんうれしい」という純粋な愛情を表現する力を取り戻し、子どもの心のコップは満たされます。この水が満たされた状態こそ、身体的な不調が軽減され、子どもが順当な成長を再開するための”スタートライン”となります。
だからといって以降、コンプリメントは”用無し”か?と言われれば…当然そんなことはなく、今度は子どもの人生の「燃料補給係」として並走していきます。
自動運転:「違和感」を力に変える運転への切り替え
心のコップが自信の水で満たされた後の課題は、「コントロールの終結(自動運転への切り替え)」です。
子どもは満たされた自信という”燃料”を使って、「なぜ自分は学校に行くのか?(踏まえて学校に行く/行かない)」「何を、何のため学ぶか(学びのデザイン)」といった自立的な選択(人生の運転)を、徐々に自らの意志で行っていくでしょう。このとき親は、もはや「どこへ行け」や行き方の注意と指示する必要はありません。親の愛情と承認が、子どもが自己決定するプロセスを温かく見守るための”土台”となるのです。
ゴール:そして「目的」をひらく
コンプリメントという愛と承認の方法を実践し走り出した先には、きっと「不登校を経て真の”自立”へ」という、長期的にして本質的なテーマに立ち向かっていきます。その際、コンプリメントで満たされた自信という”土台”をたまに叩いて確認しながら、あとは応援席から見守ってあげましょう。
コンプリメントで満たされた自信という土台の上に、「違和感を力に変える姿勢」「生きる目的の探索」といった、より本質的な支援を積み重ねていきます。
***
当サイト主催の読書会にて、さらに詳しく本著を読み広げながら”具体的にどうするか?(どう変わるか?)”を参加者と一緒に考えていきます。開催日は随時ご案内しますので、よろしければフォームに登録して機会をお待ち下さい。
本著の購入はこちら
https://www.shogakukan.co.jp/digital/098401750000d0000000