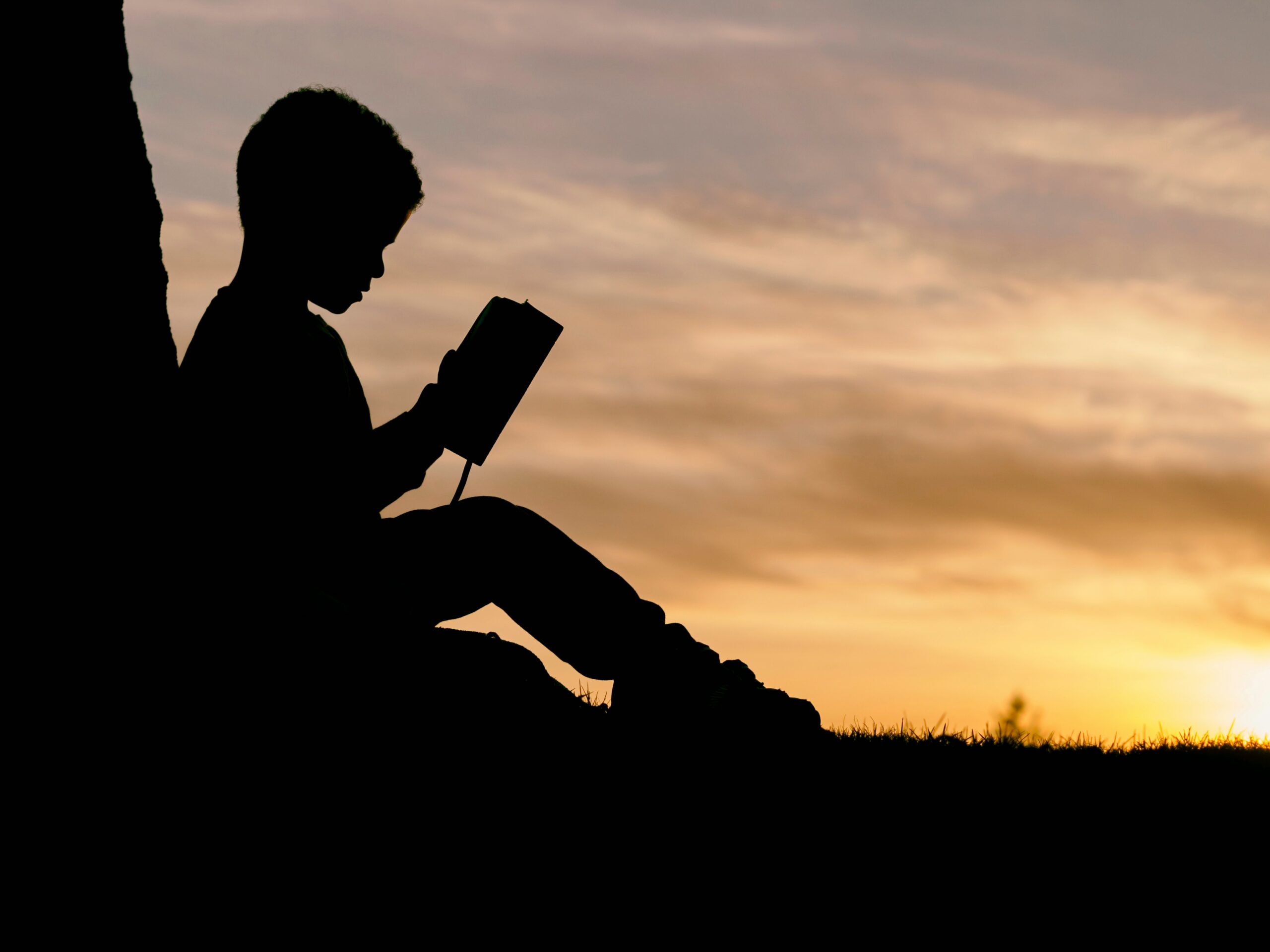https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784422120669
掲載情報
- 書籍タイトル: 不登校の子どもに親ができること 4つのタイプ別対処法
- 著者: C・A・カーニー 著 / 今井必生 訳
- 出版社: 創元社
ー相対評価
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 「方法(具体)」に強く特化。登校にまつわる行動変容という具体的な手法が中心です。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): 「ドライ(客観)」。心理学的な行動分析と冷静な介入を推奨します。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 「今すぐ(短期)」に特化。不登校が長期化するリスクを避け、初期の迅速な行動開始を促します。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 「支援者目線」に特化。親や教師といった周囲の人間が、子どもの行動を客観的に分析し、適切に介入する役割を担うことを主題としています。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): 「ニュートラル(客観的)」寄り。問題の機能分析と冷静な解決を目指し、感情的な希望論は控えています。
- 発達特性との関連度: ★★★★☆ 4
本書は心理学者であるC・A・カーニー氏の長年の臨床研究に基づいた、不登校の子どもを持つ親向けの「ガイドブック」です。原題は「Getting Your Child to Say “Yes” to School」であり、タイトルが示す通り本書の目的は、子どもが学校に対して「イエス」と言えるようになるための具体的な方法を提供することにあります。
「毎朝の”登校バトル”に、もう心が折れそう。感情的にならず、子どもと向き合う方法はないでしょうか?」
不登校の親が最も疲弊するのは、朝のバタバタの中で起こる「登校バトル」です。親としては子どもに苦しんでほしくない一方で、つい「学校に行きなさい」とプレッシャーをかけてしまうのは当然の心理です。しかしこの本では、その感情的な叱責やプレッシャーこそが、子どもが”学校を避ける行動”を強化し、問題を長引かせているかもしれないという”問い”を投げかけます。
著者のC・A・カーニーが提示する行動科学的な「方法」は、この消耗戦から親が脱却し、冷静な『時間と心の余裕』を勝ち取るための今すぐ使える「速攻剤」です(「朝バトル」は、一日でも早く終戦しましょう!)
この本は「親が冷静さを取り戻し、自立への橋渡しを行うためのツール」として非常に実用的です。感情論を排し、子どもの行動を客観的な「タイプ」として分析し、短期的に行動変容を促すこと。それが、子どもの「学校に行かない」という違和感を自立への力に変えるための、最初の不可欠な一歩となります。
不登校を紐解く「4つのタイプ」と冷静な介入
この本の核心とは、不登校が子どもが登校を回避することで得られる「4つの利得(機能)」で分類されるという、ドライな分析です。この分類は、親が感情的な非難を避け、冷静な「仮説」を持って対処するための強力なツールです。
- タイプ分類の有効性: この分類は、ある子に有効な対処法が、別の子にも有効ではない、という前提です(たとえば「母親にしがみついて泣いている六歳の子への対処法」は、「昼に教室を抜け出して居場所を親に知られたくない一五歳への対処法」とは違う)。親はまず「うちの子はどのタイプか」と冷静に原因を見極めることで、感情的な叱責を避け、対原因的にアプローチできます。
- 方法論の特化: 本書の目的は、「子どもが朝に登校して、日中に学校にとどまるために何をすればよいかアドバイスし、もう少し楽に登校できる方法」を紹介することに集中しています。
コントロールの罠と自立への橋渡し
この本が教える行動変容の技術は、親が「朝のバトル」という消耗戦から解放されるための手段です。しかし親がこの「ごほうび」や「ペナルティ」を、子どもの人生を「親の思う通りに動かす道具」だと誤解した途端、「コントロールの罠」に陥ります。
親が心に留めるべきは、”賞罰”の適用範囲を明確に限定することです。賞罰を用いるのは、あくまで「朝の準備」「時間通りに家を出る」といった目に見える表層的な「行動」の変容に関わるところまでで。
また仮にこの方法が成功しても、「わかったつもり」を避けることも大切な姿勢です。仮に親がこの方法で子どもの行動を変えられても、「なぜ行きたくないのか」という子どもの本質的な「違和感」や「感情」に、そのまま親の価値観を上書きしてはいけません。親が冷静さと時間を取り戻したその瞬間こそ、「学校に行かないという選択をした子どもの違和感を力に変える」という、自立を尊重する支援が始まるのです。
鉄則:「安全」の優先と「孤立」の排除
不登校支援において親が心得るべき鉄則とは、「安全と健康の維持こそが、家庭の最も基本的な機能であり、その優先順位は学業よりも上である」そして「親が孤立しない」という原則です。
- 身体症状の優先
- 子どもが訴える胃痛、頭痛、腹痛などの身体症状は、決して「仮病」や「甘え」と決めつけないように。著者は、「病気のふりをしている、と決めつけないことが大切です。私は以前、登校する時に胃が痛むという九歳の女の子の治療をしたことがあります。みんな、この女の子が仮病を使っていると思っていましたが、実際には胃潰瘍だったのです。」と、具体的な事例を挙げて強く警鐘を鳴らしています。
- 登校より「診断」の優先:
- 登校しない理由が体の症状の場合は、まず医学的な診察と治療を受けましょう。特に注意欠如・多動症(ADHD)やうつ病のような「もっと深刻な問題」がある場合は、精神科や心理の専門家の受診を検討してください。
- セカンドオピニオン戦略
- 専門家からの助言を「セカンドオピニオン」として捉え、できるだけ多くの視点(教師、カウンセラー、医師など)を集めようとする姿勢が、親の判断の「主体的・自立的な」土台を築きます。「孤立」は不登校における最大の危険です。
消耗戦からの脱却と人生の運転
この本は、親が「朝のバトル」という消耗戦から脱却し、冷静な『時間と心の余裕』を勝ち取るためのツールです。
親が冷静さと時間を取り戻したその瞬間こそ、子どもの違和感を力に変える支援のフェーズが始まります。
- 朝の時間の再定義: これまでバトルに使っていた朝の時間は、子どもの人生において優先順位の高いことに時間を割り振る(例えば、心身を回復させるための「ゆっくり眠る」という仕事)ことに使ってください。
- 違和感を力に変える: 子どもは、満たされた自信という燃料を使って、「学校に行く・行かない」「何を学ぶか」といった自立的な選択(人生の運転)を、徐々に自らの意志で行っていきます。親はもはや「どこへ行け」と指示する必要はありません。
あなたの孤独な挑戦を「孤立」させてはいけません。当サイトは、あなたがこの本で得た具体的な方法論の土台の上に、「自己否定感からの脱却」「違和感を力に変える哲学」「生きる目的の探索」といった、より本質的な支援を積み重ねていきます。
以上までが当サイトによる本の紹介でしたが、さらに「勉強会」「読書会」では”実践編”として「具体的にどうするか?」を他のメンバーといっしょに考えていきます。開催日時は随時お知らせしますので、ぜひご参加ください
書籍の購入はこちら
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784422120669