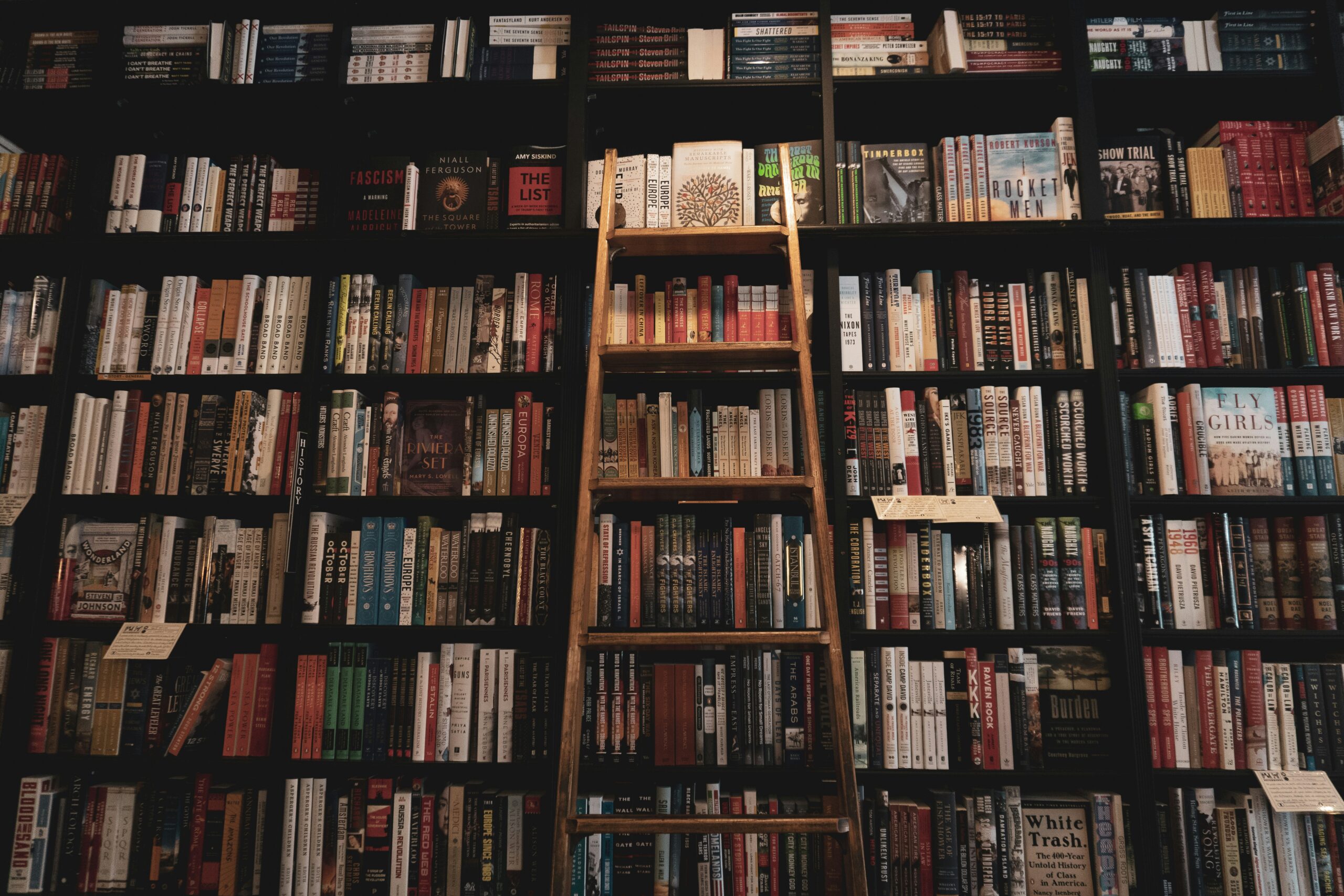概要
書籍タイトル: 不登校の はじまりからおわりまで
監修: 児童精神科医 齊藤万比古
出版社:辰巳出版
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/dvqBYp3
時間軸の現実と親子の関係再構築
「不登校を克服するまでに数年間」と言われたら…あなたは受け入れられますか?
親が焦り、過剰な介入をするほど悪化しやすいというこの問題の核心に、本書は正面から向き合います。
不登校は、子どもの内的な成長プロセスが従来の学校の時間軸から逸脱している状態です。親がこの時間軸の現実を知らずに「早く解決しなければ」と焦るほど、子どもは過剰なプレッシャーを感じ、問題は悪化しやすいのです。
この本が説く「数年間」という時間は、親が焦り、過剰な介入をするのを止めるための「待つための羅針盤」となるでしょう。「不登校」は子どもが独立するため、親子関係の”再構築”を迫られている期間なのだと考える方が筋が良い。親が焦りを手放し、子どもが自力で次の段階に進むのを「待つ」という心構えに転じることが、最も重要です。
ポイント:子の葛藤の肯定と身体的サインの尊重
子どもの心理的葛藤と自由の肯定
本書が指摘する、子どもが抱える「学校に行きたい(接近願望)」と「学校に行きたくない(回避願望)」という二つの相反するエネルギー。この「自分の中に二人いる」感覚は、大人だってわからないものではありません。
- 葛藤は成長の証: 親が理解すべきは、子どもが激しく苦しんでいるのは、単に「つらい」からだけでなく、その奥で「がんばろう」としている強いエネルギーが動いているからです。親の役割は、この苦しみを否定せず、子どもに「悩む権利(自由)」を、誰に遠慮することなく、家の中で与えてあげる大切さに気づくことです。
- 過剰介入の弊害: 親が「頑張れ」「行くべきだ」と過剰に介入することは、子どもの自己内対話を妨げ、親の望む行動(接近)を取らせることで、かえって自分自身の葛藤から目を逸らさせることになりかねません。
身体的要因と親の「後援」
不登校には単なる心理的な問題だけでなく、起立性調節障害(OD)に代表される「身体的な不調」が深く関わっていると本書は指摘します。
- 調整障害の理解: 「病気か?さぼりか?」という二極論の間に、「調整障害」というフェーズがあることをまずは知っておきましょう。この”現在調整中”フェーズこそ、子どもが激しい葛藤を抱えている時期であり、親はとにかく自己判断せず、できるだけ早期に専門家(医師など)に相談するなどのが最善です。
- 親の「後援」に転じる: 親が子どもの身体的苦痛を”客観的に(これは、結構難しいことですが)”理解し「怠けではない」と確信できた場合、次にすべきは回復に向けた「後援」です。子どもの「学校に行けない」状態を責めるのではなく、「怠けではない」ということを非言語的(表情やしぐさなど)な態度も含めて受け容れ、回復のための環境(規則正しい生活リズム、医療的な指導への協力など)を提供する後援者としての役割を果たすとよいでしょう。
本の特徴
相対評価
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや方法寄り。4つの段階ごとの具体的な対応を重視します。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ寄り。児童精神科医による冷静な分析と体系的な解説が中心です。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。克服には数年かかることを前提とし、長期的な視点が中心です。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。家族や周囲の適切な「関わり方」が主題です。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。問題の現状と克服の道のりを冷静に解説します。
- 発達特性との関連度: ★★★★☆ 4(身体症状、特に起立性調節障害(OD)や発達障害との関連、そして5つの行動タイプに明確に言及)。
独自の観点:ネガティブ・ケイパビリティの肯定
- 長期化の要因: 中高生以降の長期化の最大の要因は、将来に対する「不安」です。キャリア学習などが注力される社会では、子どもが「適当に、なるようになる」という態度で臨むのは許容すらされず、二重の重圧に苦しみます。
- 克服の目標: 親は強いて「自己決定」を促すのではなく、むしろ「不安のままあり続ける(ネガティブ・ケイパビリティ)」を支えるのが大事です。この受容の姿勢を保つために、保護者は「あなたには理解者がいる/学校や教室以外にも複数の居場所がある」などを時や場所を変え刷り込むように伝えていくことが重要です。
まとめ:親の「動じない心」が自立を導く
不登校の克服の最終的なゴールは、「子どもが自分らしい生き方を見つけること」です。親が「数年間」かけてもいいという余裕を持ち、この本で説かれる原理原則を愚直に実行すること。これが、子どもの「自ら立ち直る力」を信じ、自立を導くための鍵となります。
「学校復帰」以外の「多様な選択肢」を提示し、子どもの不可解な違和感を力に変えるには、親の冷静な「動じない心」と、子どもが自力で次の段階に進むのを「待つ」ための哲学が必要です。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/bO2D14b
スガヤの付箋~個人的ブックマーク
・言ってはいけない~親の何気ない言葉が心の傷に
不登校の子どもに対して、親がつい発してしまう「怠けているのではないか」「甘えているからだ」といった何気ない言葉が、子どもには深い傷になることがあります 。
これは…数多くの親がど真ん中ストレートすぎて「うっ」となってしまうではないでしょうか?(うっ…)
親の焦りからくるこれらの言葉は、子どもに不信感や深い傷につながる危険性があります 。
- 親の焦り:不登校を「怠け」や「甘え」だとするのは親の焦りであり 、子どもにそのままいうのは百害あって一利なし
- 問い詰めや叱咤激励:「どうして学校に行かないの?」「あんたは頑張っていない」といった言葉は子どもを追いつめ、自己否定感を強める
なかで親がすべきことといえば、とにかく「信じて待つ」。あとは家庭を子どもにとって「安心できる環境に保つ」こと。ホントこれだけ、数千回心に唱えて刷り込みましょう。
子どもに伝えたいこと
ただでさえ最近は「キャリア教育」など、子どもの「夢」ですら「良い大学」や「良い会社」といった固定観念にとらわれがちです。もうガチガチなんです、彼らは
なかで「柔軟で適当でも生きていけるよ」こそ、親側から伝えてあげたほうがよい(もはや、親でないと言えないのでは?)
本著(P.178)でも以下のようにありました。
子どもが、葛藤やストレスに対応できるようになるために、次のようなことを伝えてあげてください。
・あなたには理解者がいる
・あなたには学校や教室以外にも複数の居場所がある
・失敗やつまずきは誰にでもある
・人それぞれにいろいろな考えがある
・人と話すことで見えてくるものがある
いわゆる「不登校対策」という話でないので読み飛ばされがち?のように思いますが、すごく大事なこと。なかで「学校にいく”べき”」という一方的な主張は、上記全てに逆行する考え方ですからくれぐれも言わないよう心がけたいところです。