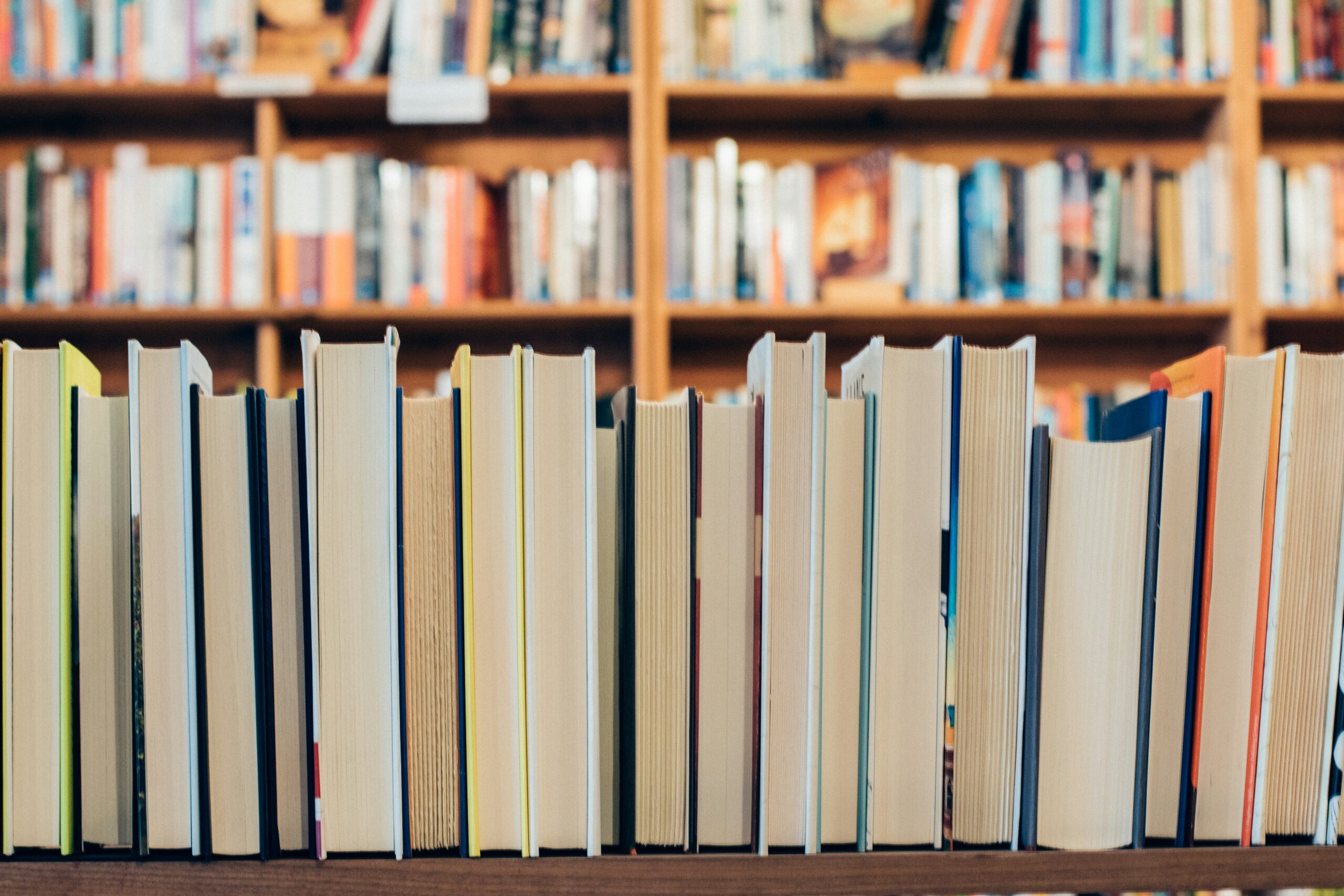掲載情報
書籍タイトル: 元・しくじりママが教える 不登校の子どもが本当にほしがっていること
著者: 鈴木理子
出版社: すばる舎
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/5kErEPD
「学校的呪い」からの解放
あなたが「子どものため」と思って行っている、最も愛情深い行動(世話、心配、声かけ)が、実は子どもを苦しめ、自立を妨げる『呪い』になっているとしたら?
「呪い」の正体は、あなたの心の中にある「〜すべき」「〜せねば」という思考のクセ、すなわち学校的・集団優先的な価値観に深く根ざしています。
この書籍は、親の「私の育て方が悪かったのではないか」という自責の念から親を解放します。著者は、親の育て方そのものが不登校の原因ではないと断言し、問題の焦点を「親がこの呪いをどう解体するか」という自己変革に置きます。親が自己の「呪い」を解き、自分の人生を充実させることが、子どもの自立への最良のサポートであるという哲学が核となっています。
ポイント:呪いの解呪と承認シャワーの技術
呪いの正体と自立の妨げ
この本が提唱する「呪い」の正体は、「頑張らないと価値がない」「人に迷惑をかけてはいけない」といった、親が内面化した非合理的な信念です。不登校を決めた子どもにとって、この価値観を内面化した「学校的母親(※これは当サイト独自の言い回しです)」は、子どもの行動の自由を阻む”敵対側”になってしまいます。
不登校の真の理由:は、子どもが「自分はダメだ」「期待に応えられない」といった強い自己否定感に直面し、これ以上心身を悪化させないために体が発動した「フリーズ」状態です。またその過程での潜在意識への「学校=イヤなところ」という刷り込み(条件反射)も、原因の一つです。
この条件反射は、親の日頃の言動(「敵か味方か?」という二極論と、「役立つか否か?」という反射的で短期的な価値判断)によって生じ、また強化されます。そして不登校に際しても、親が短期的な結果を求めるほど子どもはかえって動けなくなります。
呪いを解くための「承認シャワー」
子どもが本当にほしがっているのは、親の「自責の念」や「心配」ではなく、「無条件の承認」です。子どもを救うために親がすべきは、「学校的だった自分」を批判的に見つめ、その呪いを解くことです。
・承認シャワーの技術: 子どもの承認欲求を満たすため、結果ではなく存在を承認する言葉がけ(承認シャワー)を実践します。特に大切なのは、「そのままのあなたでいい」と、存在そのものを認める「存在の承認」です。
・「NG行動」の回避: 「説得する」「怒る」「脅す」といった、子どもの自己否定感を強める3つのNG行動を絶対に避けます。親の心配は、子どもには「脅されている」と感じさせてしまいます。
・「課題の分離」の徹底: 親子の課題を明確に分け、親子の境界線を引くことを学びます。「仲間を置き去りにしない」という集団の規範(これは学校的でもありますね)から脱却し、この機会に返って「親自身が自分の人生を充実させる」という、いわば逆張りの行動をとります。親が自分の人生を楽しむことで、子どもは「自分も人生を楽しんでいいんだ」というメッセージを受け取り、自立へのエネルギーを得られるのです。
この本について
相対評価
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 方法に特化。NG行動の回避や承認シャワーなど、具体的な実践が中心です。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェットに極めて特化。「しくじりママ」の体験と「親の呪い」という感情的な課題が核です。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。親子の信頼関係の修復、親の自己肯定感の回復という長期的な課題が中心です。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。親の心の在り方と行動の変容が主題です。 ・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ポジティブに極めて特化。親子の問題が親自身の成長のチャンスであるという希望を強調します。
・ 発達特性との関連度: 3(過度な診断に警鐘を鳴らし、親の自己変革に集中します)。
独自の観点:”深い共感”の方法
普段の親子対話の「質」について、どれくらいこだわってますか?たとえば子どもの話を最後まで遮らずに聞き切る「傾聴」や、負の感情に「そうか、つらいんだね」と寄り添う「真の共感」の技術は、親子の信頼関係を根底から変革します。一方で親が忙しいほど、蔑ろにされがちでもあります。不登校のゴールは単なる復学ではなく、親子の関係が心地良いものとなり、親も子もそれぞれが自分らしい人生を大切に歩むこと(親は子どもの「生涯サポーター」となること)です。一方子どもは自分になくして今の状況にあるわけですから、これを期に「ありのまま承認している」ことを表すため、もう一度「共感の方法」を見直してみるのもよいかもしれません
まとめ:親の「人生の充実」が子どもの扉を開く
この本は、不登校という困難を、親自身が「呪い」から解放され、自己肯定感を回復させる最大のチャンスと捉え直します。親がまず自分の心の平穏を取り戻し、自分の人生を謳歌している姿を子どもに見せること。
それが、子どもにとっての揺るぎない「セキュアベース(安全基地)」となり、子ども自身が「自分も人生を楽しんでいいんだ」というメッセージを受け取り、自立の扉を開くための最も確かなエネルギーとなるのです。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/5kErEPD
スガヤのふせん~個人的ブックマーク
本著では、赤裸々に「しくじり」体験談が語られています。しかしホントにこれ、「他人事」と読み流せる親がどれくらいいるでしょうか?ボクはところどころで「うっ」となりましたが
「良い親」だからこそ、不登校という事態に直面したときに「なんとか子どもを学校に行かせよう」と焦り、「しくじり」に繋がる行動を取ってしまいがちなのでしょう。
本著で語られる「3つのNG行動(やってはいけない声かけ)」は以下
- 説得する:まずは「みんな頑張っているから頑張ろう」「とりあえず行ってみよう」などと説得を試みます。
- 説得が受け容れられなかったことに怒る:説得が通じないと、「誰が学費を払っていると思うの?」「子どもの仕事は学校へ行って勉強することでしょ!」と怒ります。
- 脅す(叱る):怒っても効果がないと、「将来、まともな仕事に就けなくなるよ」「一生、家にいるつもり?」と脅すような言葉で迫ってしまいます。このとき親には脅している自覚がなく「取り返しのつかないことになる」と伝えたいだけなのですが、子どもは「心配してくれている」とは受け取らず、脅されていると感じてしまいます。
特に、親が日課のように問いかける「明日は学校に行くの?」という質問は、子どもにとって「行かない」という選択肢がないため苦痛であり、たとえ「行く」と答えても、翌朝起きられなければ親は「ウソをついた!」「行く行く詐欺だ!」と憤り、母娘関係は悪化の一途をたどります。
これらがなぜNG行動なのか?は、客観的にみれば言うまでもないでしょうが…自分が当事者だったならば、やらない自信はありません(うっ…)
結論!とにかく理由を聞かず、ただ休ませる
子どもが不登校になったときの最も効果的な対処法は、シンプルに「理由を聞かずに休ませる」こと。親が「サボりではないか?」という疑念に駆られたとしても、それは一旦脇に置いて、とにかく休んでもらいましょう!
学校に行きたがらない子どもにとって、まず何よりも必要なのは安心安全な場所、つまり「セキュアベース(安全基地)」です。セキュアベースとは、自分が自分らしくいられる場所であり、不登校の子どもにとっては、自分が否定されない家庭こそが唯一、セキュアベースになりうるのです。
家庭をセキュアベースにするためには、親がゆったりと構え、子どもを否定せずに無条件で受け容れて、安心安全を体感させることが大切です。これにより子どもは「私はこのままでいいんだ」と思えるようになり、フリーズ状態が解かれて徐々に動けるようになっていきます。
実は「子どもよりママ」!あなたの心は平穏か?
さてそのとき、「親もゆったり」する準備はありますか?子どもだけの問題ではなく、「家族全体の問題」と捉えてみましょう。家族が健全に機能するには、特に「ママ」の元気が最重要とも言われます。
そもそも多くの親は、子どもを「導くべき」存在だと思いがちです。が、それは違います。親は子どもを教え導くのではなく「手出し・口出しをせずにただ見守る(それこそ「木の上に立って見る」のが「親」です!)」関わり方が正しいのです。子どもには、自分で人生を切り拓く力があります。親が自分の人生を充実させることは、「子どもを放置」することではありません。むしろ、親が自分の人生を大切にし、楽しんでいる姿を子どもに見せることで、子どもは「自分も人生を楽しんでいいんだ」と感じ、「自分らしい選択」をして自分の人生を切り拓くエネルギーを得るのです。
不登校は、親が変わる最大のチャンスでもあります。親が人生を謳歌している姿を見て、「あんな人間になりたい」と子どもが心底思えたとき、親子関係はゆっくりと、しかし劇的に改善していくのでしょう(そういえばなんと、娘さん「共著」という珍しいスタイルで、かつて「死ねマン(※原文ママ)」だった母親との関係回復のきっかけは「母の雰囲気が変わってきた」ことだったそうです)