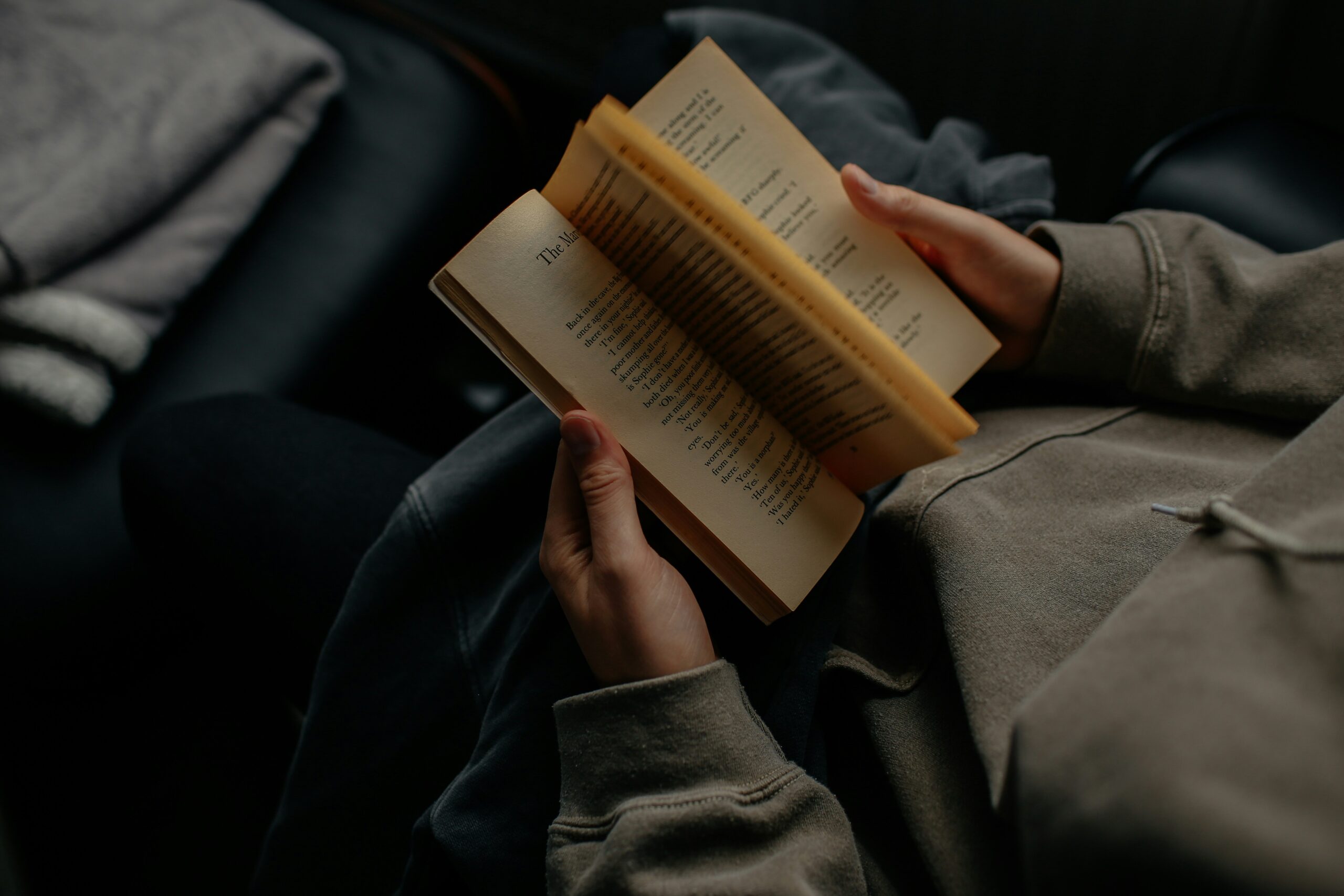書籍タイトル: 不登校・ひきこもり急増:コロナショックの支援の現場から
著者: 杉浦孝宣+NPO法人高卒支援会
出版社: 光文社新書
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/8js6Dcc
「待つ支援」の限界と「迎えに行く支援」への転換
「このままではいけない」と焦りながらも、子どもが動き出すのを「じっと待つ」ことに限界を感じていませんか?
この書籍は、コロナ禍で不登校・ひきこもりの児童生徒が急増し、学校や行政の主流である「待つ支援」モデルが、現在の危機の深刻さに対して構造的限界を迎えていると強く批判します。家庭や学校といった公的支援が届きにくい領域に問題が拡大した結果、対話やコミュニケーションから完全に分断された「放置」状態が常態化し、親も子も孤立を深めています。
この非常時を踏まえて、本書が提唱する「迎えに行く支援」(アウトリーチ)は、従来の支援システムに対し、支援の「場」を施設や学校から家庭という「当事者の領域」に移すという、根本的な哲学的転換を突きつけています。これは単なる訪問ではなく、子どもをリスペクトした上で孤立状態から「誘う」ための戦略なのです。
ポイント:メンタルフレンドと「粘り強さ」の哲学
アウトリーチ成功の鍵:本質の探索
支援者が家庭に踏み込む目的は、子どもを一人の人間(主体)として尊重し、孤立を解くことにあります。成功の鍵は、アウトリーチの最初のステップである「本質の探索」にあります。
この段階では、腰を据えた「傾聴」および「対話」が最重要です。親や教師のような「上下関係や評価」のプレッシャーがない、対等な関係性を構築する「メンタルフレンド」(不登校経験を持つ学生サポーター)が、子どもが最も安心できる「相手の懐」に入り込み、自発的な行動を促します。彼らは「つかず離れず」の絶妙な距離感を保ち、子どもの関心事から入ることで、主体性を踏まえて「誘う」ことを実践するのです。
「粘り強さ」の根拠:同じ傷を持つ者同士の共感
本書は「支援期間を定めない」ことの重要性を説き、「ひきこもっていた期間と同じくらいの時間がかかる」と現実を突きつけます。この「粘り強さ」は、単なる根性論ではなく、支援対象者の「気持ち(傷)がわかる」という深い共感に裏打ちされています。
支援者の力は、「専門性」というより「同じ傷を持つ」メンタルフレンドの戦略的価値にあります。親は「急いで結果を出す必要はない」という安心感を得て焦りから解放され、子どもは回復を信じられているという安心感のもと、自らのペースで次の行動へと動く勇気を得るのです。
最終目標:「自律とは依存先を増やすこと」
アウトリーチ支援の最終的な目標は、子どもと家族を孤立から脱却させ、精神科、福祉機関、学習塾といった他機関へ移行させる「つなぎ役」を果たすことです。
このとき支援者の代弁(対話の継続)の役割とは、支援者が子どもや保護者のニーズを学校や移行先の他機関に「正確に伝え、代弁・仲介役割」を担うことは、当事者が自らの苦しさを言語化する力が不足している場合に不可欠です。この「代弁」は、不完全で未熟であっても「本人性」をもって他者とつなげる「対話の継続」そのものです。生きるのはあくまで本人であり、支援者は、本人の主体性が他者にリスペクトをもって受け入れられるための最小限かつ最大限の擁護者となるのです。
この本について
相対評価
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 方法に極めて特化。アウトリーチの具体的な手順、3ステップの支援プロセスが中心です。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ウェット寄り。支援現場の熱意、当事者の生々しい体験談が豊富です。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。アウトリーチは訪問期間を定めず、ひきこもり期間と同程度の時間をかけて回復を目指します。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。支援者側の「粘り強い姿勢」と「介入技術」が主題です。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。現状の深刻さを警鐘しつつ、支援の効果を冷静に報告します。
- 発達特性との関連度: ★★★☆☆ 3(複雑な困難を抱えるケースや、発達特性を持つ子どもへの「メンタルフレンド」の導入に言及)。
独自の観点:支援アプローチの相対的な位置づけ
- 構造的な課題への対応: 従来の「来訪型支援」の構造的限界を指摘し、ひきこもりという孤立状態に対して、支援者が家庭へ「迎えに行く」という、支援の「場」の転換を促します。これは「行動」しなければ何も始まらないという場合の特別な支援のケースです。
- 対等な関係性による回復: 支援者の力は、「専門性」ではなく「同じ傷を持つ共感」にあります。親や教師の評価や指導から解放された対等な関係性こそが、子どもが主体的に行動を始め、自立という最終目標に向かうための鍵となります。
- 自律と依存先の増加: 支援の最終目標である「他機関への移行」は、「自律とは依存先を増やすこと」という哲学に基づいています。単なる家庭訪問では得られない社会的・構造的な解決を、福祉、医療、学習という多職種連携への移行によって実現します。
まとめ:行動しなければ何も始まらない
本書は、コロナショックにより不登校・ひきこもりが激増した危機的状況に対し、行動しなければ何も始まらないという明確なメッセージを投げかけます。親の不安や焦りを理解しつつも、「待つ」という名の放置が子どもをさらに孤立させる現実を突きつけ、支援者自身が家庭に踏み込み、対等な関係性で主体的な行動を促すアウトリーチの具体的な道筋を示した一冊です。
この本は、支援に関わるすべての関係者、そして「このままではいけない」と悩むすべての保護者にとって、現状を突破するための具体的な知恵と、長期的な覚悟を与えてくれるでしょう。
ご購入はこちら
https://amzn.asia/d/e21AoLA
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
読後改めて、団体への活動に深いリスペクトを禁じえません。一方でこれはある種の「使命」をもって活動する方々の「プロフェッショナル」なストーリーなのだと思い、こと「不登校」とは違ったフェーズの、違った支援の事例として深く勉強になりました。
改めて確認をするならば、
メンタルフレンド(Mental Friend)
”不登校・ひきこもり経験のある”学生サポーター(フレンドサポーター)で、親の言うことを聞かない子どもでも彼らの言葉には耳を傾ける可能性があるとされている。
具体的な活動内容といえば、訪問先で子どもと話し相手になったり、ゲーム、将棋、小物作り、キャッチボール、映画、買い物、パソコンなど、子どもが関心を持っているところから入っていき、時間をかけて信頼関係を築いていく。また訪問時には子どもたちの状態をよく観察したうえ、「つかず離れず」の絶妙な距離感を保ちながら心地の良い関係を築いていく。親のような過干渉や感情の甘え合いを避け、かつ教師のような上下関係や学校制度による緊張やストレスを与えにくいとされるそうだ。
こちらは東京都も募集していますね。もっと認知が広がると良いと思いました。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jicen/ji_annai/m_friend/gaiyou
さて団体の懐の深さというか専門性を特に感じたのは以下の部分で
慣れてきても、この(訪問時間は「1時間」という)時間は必ず守ってもらいます。 ここで深追いしてはいけません。もう少し話すとし外へ出せるんじゃないか、などと期待し て長引かせると、子どもも話がつき、お腹いっぱい、という感じになってしまいます。子 どもに、もう少し話したい、と思わせるのが重要です。 もちろん、初回訪問で拒否反応があることもあります。トイレに閉じこもる、布団をかぶって出てこない、すきを見て窓から脱走、などは、初回ではよくあることです。 拒否反応があった場合、がっかりされるご家庭もありますが、最初からうまくいくわけがありません。初回訪問すると、その反動でスタッフが帰った後に家庭で暴れることもあります。それも織り込み済みで、徐々に良い方向に向かっていくように作戦を練っていきます。 もう一つ重要なのが、ひきこもりから立ち直るまでの期間を定めないことです。 世間では、半年で必ず外に出すから、そのかわり数百万円という報酬を求める、いわゆる引き出し屋と呼ばれる団体もあります。しかし、子どもが自発的に出て来てなくては、意味がありません。また、スタッフにとっても、必ず期間満了までに結果を出さなくてはならないと思うと、精神的に負荷がかかり、焦って強引な手段を使ってしまう原因になります。場合によっては事件にまで及んでしまうこともあるでしょう。それを防ぐために、期間を定めな いことが重要です。 これまでの経験からいうと、アウトリーチ支援でひきこもりから脱するには、ひきこもっていた期間と同じくらいの時間がかかるのです。 よく保護者から「どのくらいで直りますか」と聞かれるのですが、「そんなにかかるんですか」と言われることが多いです。 しかし、急ぎすぎてはいけません。本人が納得して自発的に外に出られるようになるため には、少しずつ、一歩ずつ、スタッフとの信頼関係を構築し、外に出られるようにしてい く必要があります。そして、一気に順調に良くなることはありません。良くなったかと思 うと、その反動でまた悪くなったり、という波を繰り返しながら、徐々に良い状態になって いきます。決して焦らず、その子のペースを尊重することが大事です。
(P.106-107より)
ことひきこもり期間が長くなり、「もう当事者(家族)だけでは話にならない」という緊急事態に、大変頼りになる団体なのだと思いました。非常事態に備えて、ぜひ知っておきたい支援の一つです。