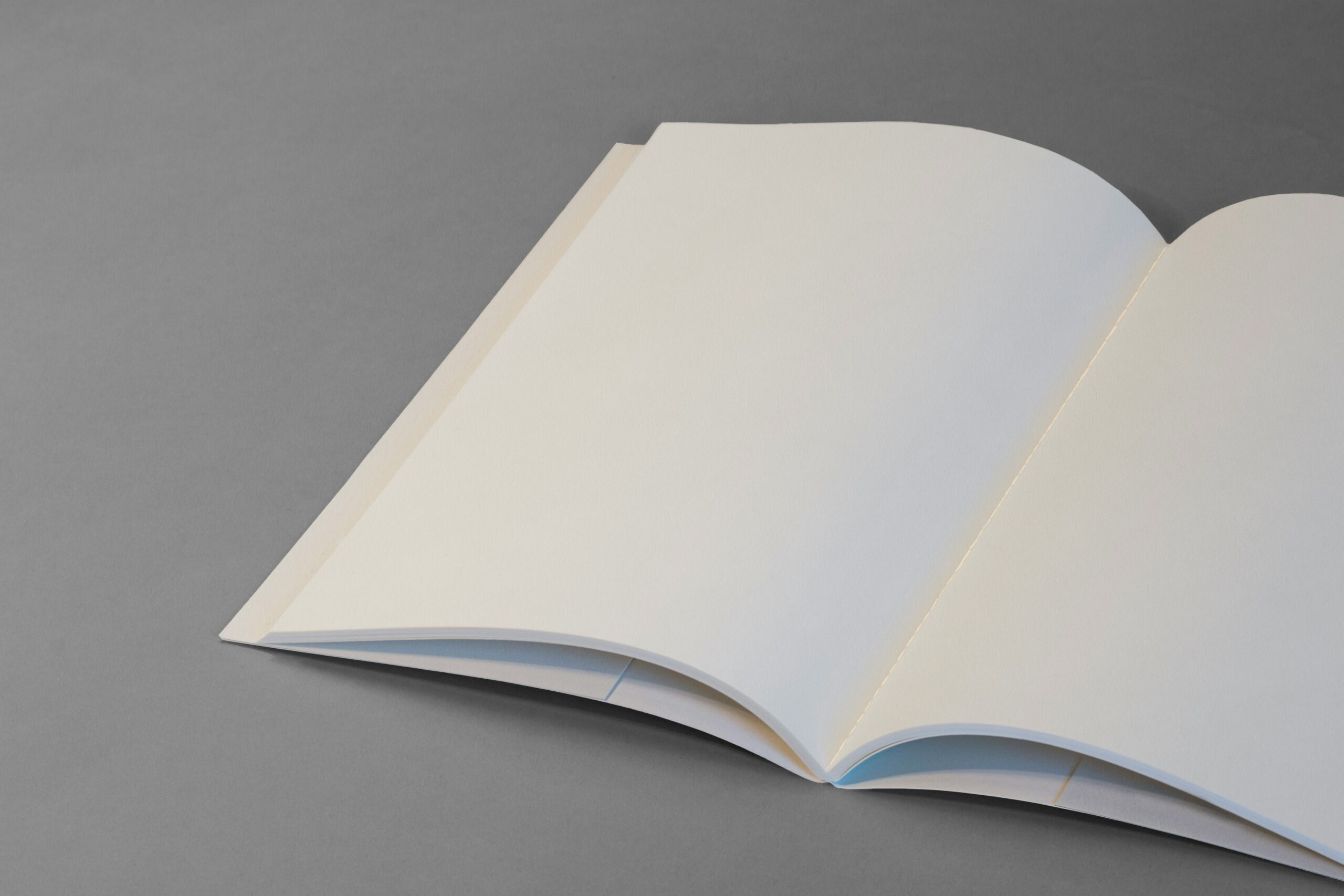掲載情報
・書籍タイトル: 不登校の理解と支援ハンドブック:多様な学びの場を保障するために
・監修: 伊藤美奈子(いとう みなこ)
・出版社: ミネルヴァ書房
・ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/5P7xyEZ
「親の責任」からの解放…のため知識の必要性
「不登校の問題は、家庭や親の責任。だから自分でなんとかしないと」という孤独な重圧に耐えていませんか?
不登校に悩む親の最も大きな課題は、問題を家庭内だけで抱え込み、「私の育て方が悪かったのではないか」という自責の念に囚われてしまうことです。この書籍は、まず「不登校について正しく知る」ことが、その自責の念から解放される第一歩であると説きます。
本書が提示する、学校、カウンセラー、医療、福祉が連携する「チーム支援」の視点は、親の孤独な闘いを終わらせ、「安心」に変えるための構造的な解決策の提案です。社会には様々な支援者がいて、不登校を”是”と解釈できる人たちもいるという事実をまず知り、孤立しないため早期に外部とつながり「チーム」を形成していくことが、不登校解決における必須アクションとなります。
ポイント:発達段階ごとの課題と多職種連携
身体的・心理的要因の客観視
不登校は単なる心理的な問題ではなく、身体的要因が深く関わっていると本書は指摘します。
- 調整障害の理解: 不登校の背景には、発達障害(ADHD、ASDなど)や心身症(起立性調節障害など)が隠れているケースが多く、この本はその鑑別診断の重要性を強調しています。親は自己判断せず、専門家(医師など)に相談するのが最善です。
- 親の「後援」: 親は、子どもの「怠けではない」という非言語的な態度をもって受け容れ、回復のための環境を提供する後援者としての役割を果たすべきです。
克服の最終目標:長期的な自立の運転
本書は、克服の目標を単なる「学校復帰」ではなく、「子どもが自分らしい生き方を見つけること」を目標とした「長期的な社会的自立」に置いています。
- 成長のステップ: 克服には数年かかることを前提とし、「兆候段階」から「社会との再会段階」までの4つの段階を知ることは、親が焦りを解消し、子どもの行動を「成長のステップ」として冷静に捉えるための羅針盤となります。
- 多様な選択肢: SC、SSW、医療機関、フリースクールといった専門家とよく相談し、この本を手に様々な選択肢に当たることが大切です。ハンディが重いとしても、これが早期に判明したのを「機会」と捉え、自分の生きる道(場所)をさぐるため、多様な選択肢に当たることが重要です。
この本について
相対評価
- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや理論寄り。発達段階ごとの特徴、多職種連携の構造といった理論的理解を重視します。
- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライに極めて特化。統計、発達論、支援機関の機能といった客観的な情報が中心です。
- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): じっくりに特化。多職種連携の構築、長期的な社会的自立を目指す視点が中心です。
- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に極めて特化。学校、SC、SSW、医療といった専門職の役割と連携が主題です。
- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラルに特化。問題を体系的に整理し、多様な選択肢の保障を客観的に説きます。
- 発達特性との関連度: ★★★★★ 5(発達障害、ODなどの身体的要因を不登校の背景として明確に位置づけ、鑑別診断の重要性を体系的に解説)。
独自の観点:ネガティブ・ケイパビリティの肯定
- 違和感の外部化: 本書が重視する発達特性や心身の疾患の鑑別診断は、不登校の原因を「怠け」や「親の責任」といった精神論から解放し、構造、かつ複層的な外部機関へとつながるきっかけ(観点)を与える鍵となるでしょう。
- 機会としての不登校: 特性や疾患は学校期間が終われば解消されるものではありません。これが早期に判明したことを「機会」と捉え、この本に紹介される様々な専門家(およびその考え方や方針)とよく相談し、できるだけ”自分のまま(自分らしく)”の「生き方(社会的自立)」ができる方法を探ってみましょう。
まとめ:不登校は「チーム」で考えていく
不登校の克服の最終的なゴールは、「子どもが自分らしい生き方を見つけること」です。なかで親が”孤独な闘い”を続けようとするでなく、早期に学校、カウンセラー、医療、福祉といった「チーム」を形成すること。それが、子どもに「多様な選択肢」を提示し、不可解な違和感を力に変えるための確かな土台となるでしょう。
同意したならぜひ著書を手に取り、様々な専門家に相談してみましょう。本書では
・スクールカウンセラー(SC)
・スクールソーシャルワーカー(SSW)
・医療、教育支援センター
・フリースクール
といった多岐にわたる支援の専門職・機関からの視点を統合していて、大変読み応えがあります。この多角的なアプローチは、複雑化・多様化する不登校の背景を理解し、「チーム学校」として機能するための確かな羅針盤となるでしょう。
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
支援における視点と具体的な取り組みを知る
不登校の要因が複雑化・多様化してきている、と言われます。なかでその支援者も、学校内の教員だけではなく、スクールカウンセラー(SC)やソーシャルソーシャルワーカー(SSW)といった様々な専門家が参画する多機関連携の必要性が高まっています。支援においては、家庭の問題(虐待、ネグレクト、ヤングケアラー)や医療的ケアが必要なケースの増加に伴い、医療機関との連携を含む多機関連携(拡大ケース会議)の重要性が高まっています。学校の枠を超えて、生活、心理、医療、福祉の専門家が連携することで、生徒が抱える複雑な問題への包括的なアプローチが可能になります。
また、学校外の「居場所」として、教育支援センターやフリースクールを「学習指導の場」としてだけでなく、「安心していられる場所」として積極的に活用する支援もあります。また教育方針の根本を異にするオルタナティブスクールも様々あります。
さてでは、これら多様化する支援情報を処理し紐解き俯瞰的に現状を踏まえ「こんなときは」「こんなタイプには」と選びきれる人?と言われると…皆さんの周りにはいますか?(別の観点で、行動経済学では「選択肢が多すぎるほど選べない」という問題も指摘されます)
本著はそんな「適切な道案内」のため、孤立化しがちな保護者のため「地図」となる、必携の一冊といえるでしょう。
不登校政策が大きく転換期を迎えた今、改めて不登校を見直す必要があると考えました。それが、この1冊を企画した大きなきっかけです。本著は、発達段階による不登校の特徴を概観したうえ、多職種連携の立場から、教育機関以外にも医療や福祉、さらには新しい特例校まで、様々な支援の現場ごとに、不登校の特徴が描かれる構成にしています。さらに、保護者支援と不登校支援のこれからについても章立てして、各先生方にご執筆いただくことができました。(「はじめに」より)
不登校は、子どもから発せられる社会へのメッセージです。一方でそのメッセージと応答も、「教育機会確保法」をきっかけに、大きな変換のパラダイムを迎えています。このハンドブックは、それらメッセージを正しく読み解き、学校、家庭、福祉、医療、地域社会が連携して、子どもたちが安心して自己肯定感を育み、未来に向けて自立できる環境を整備するための、実践的で必携のガイドブックだと感じました。
困ったとき、迷ったときに正しい連携先に素早く!つながれるよう、手元に用意しておきましょう。