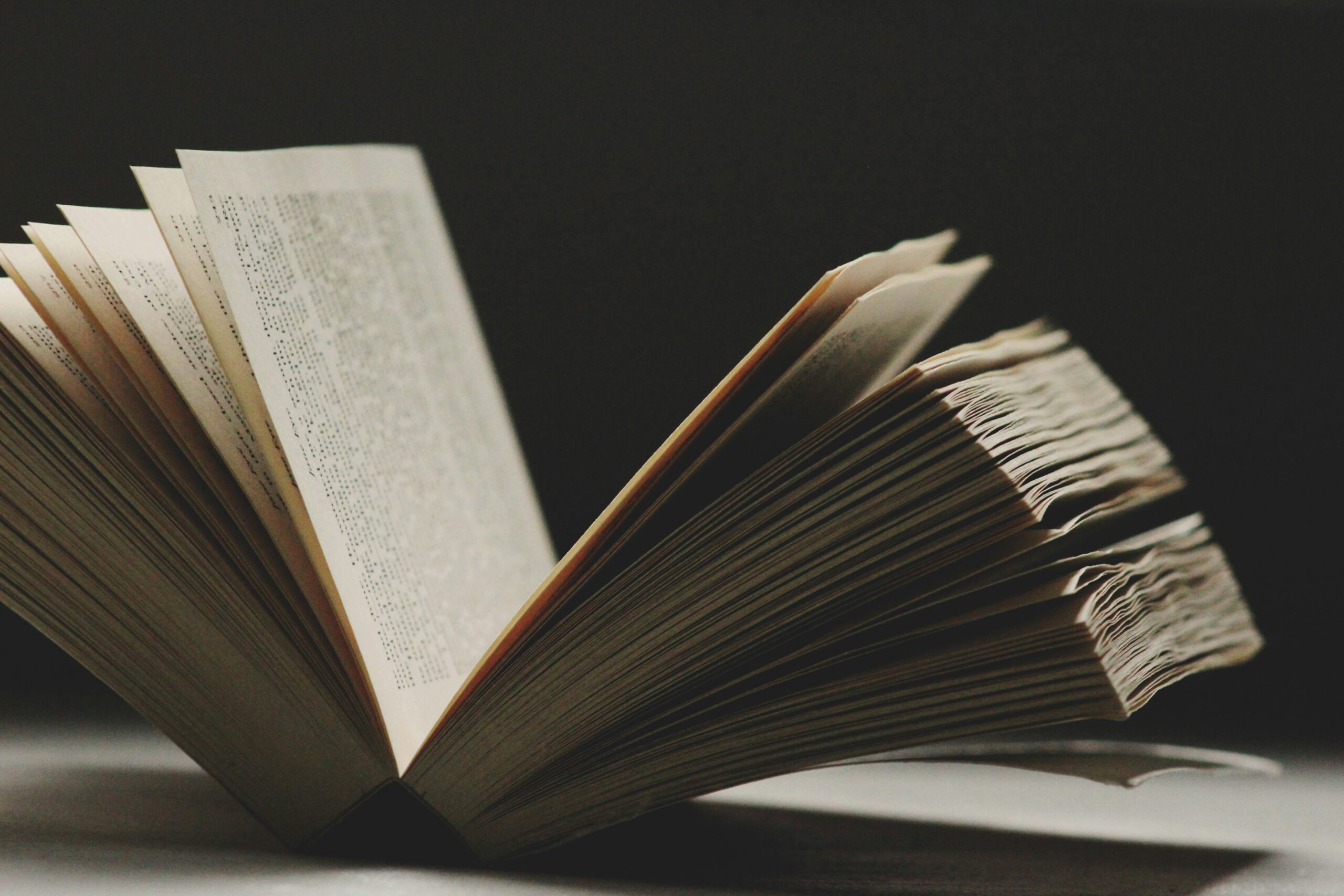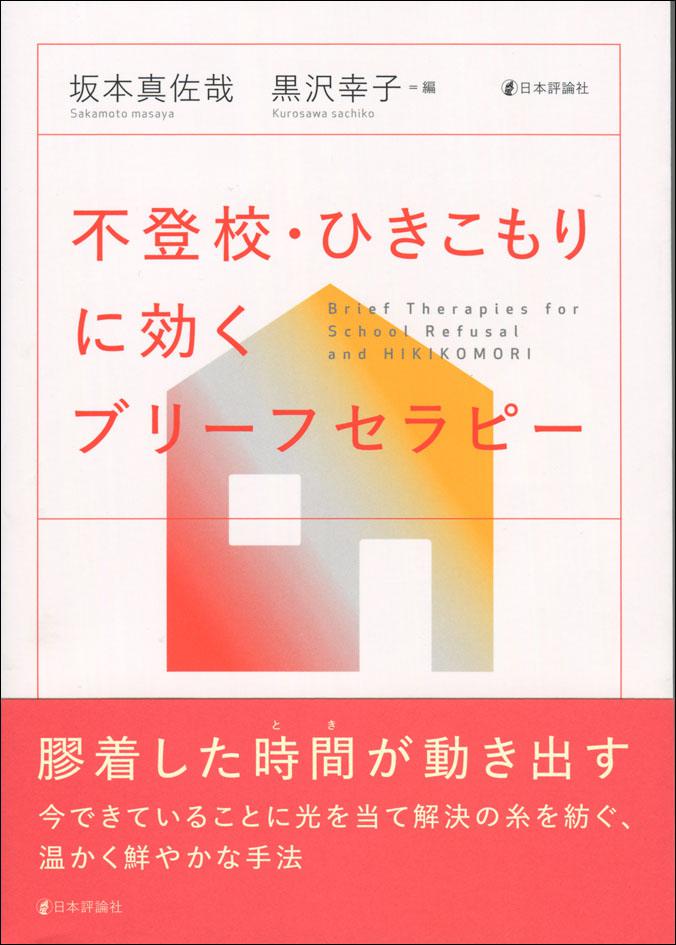
掲載情報
書籍タイトル: 不登校・ひきこもりに効くブリーフセラピー
編者: 坂本 真佐哉、黒沢 幸子
出版社: 日本評論社
ご購入はこちらから:
https://amzn.asia/d/jbCNMnJ
原因探しの放棄と「対話」可能性の戦略
不登校の支援においては、本人、家族、関係者の「想いや努力」が、しばしば原因探しや悪者探しを生み、「膠着した時間」を流すことになります。
本書が共通のスタンスとする「ブリーフセラピー(短期集中療法)」は、この消耗戦を終わらせるための哲学的転換点を提供します。問題の原因を追求するのではなく、「誰も悪くない」という安心感のもと、解決の会話を構築することです。
・ブリーフセラピーの焦点は、「何がうまくいっていないか」ではなく、逆に「うまくいっていることを見つける」ことにあります。
・最も重要な原則は、「誰も悪くないと捉える」ことです。
親や教師が「〇〇してはいけない」「✕✕すべき」という禁止や価値観の押し付けを行うことは、思考実験における「シロクマのことを考えるな」のように、かえってその対象行為を強調し、問題行動を強化(維持)してしまいます。なかで問題の解決とは、このうまくいっていない解決行動=「偽解決」をやめることから始まります。
ポイント:会話の技術と資源(リソース)の発見
技法1:思考のズラしと未来の解像度向上
ブリーフセラピーは、「木でなく森で見る」ように、広く遠望に見渡すことが「意外な解決」を及ぼすことがあると捉えます。考えすぎることで問題が解決した試しはほとんどないのです。
・ ミラクル・クエスチョン: 絶望的な「過去の原因」から、希望的な「未来の行動」へ焦点を強制的に移すことで、クライエントの「欲望(望む状態)」の解像度を一気に引き上げます。親は、子どもが「何をしたら変わるか」を具体的に描き、解決の糸口を見つけられます。
・ ユニークな介入: 本書に登場する「庭で朝ごはんを食べる」といった「ズラす」「うまくボケる」ようなユニークなアプローチは、クライエントの思考を「過去の失敗」から「未来の可能性」へと強制的に転換させる戦略として機能します。
技法2:行動への勇気づけと自主性の回復
・ 例外探し: 「うまくいっていたとき/こと」に注目することは、子どもが本人性を強調するなかでの自主性の回復を促すことが多く、掘り下げれば解決の糸口につながりやすいのです。
・ ウェルフォームド・ゴール(WFG): 「小さく、具体的で、肯定形で表現される目標」を設定することで、結果的に「過程(的な目標)に注目する」ことにつながります。この小さな目標は、失敗しても「すぐ別の方法でやり直す」という勇気を育みます。
・ コンプリメント(承認/労い): 問題は考えるより「行動」でしか解決しないとして、その勇気を高めるため、「コンプリメント」は役立ちます。対象者(子ども)の持つ資源、努力、できている点に対し、労い、認め、賞賛する行為は、自己効力感を高める肯定的なフィードバックです。
独自考察:親の「責任の放棄」と対話の技術
この本の核心は、親の自責の念に対する「責任の放棄」という安心感の約束です。
・ 親の免責: 援助者はひきこもりの「原因」について家族から尋ねられた時、迷わず「家族のせいではない」と伝えます。この「責任を問わない」という姿勢こそが、親の自責の念を和らげ、「しょうがない」という冷静な受容へと導き、家族の消耗戦を終わらせます。
・ 会話のコツ(フレームの尊重): 援助者は、来談者の発話が「何を意味しているのか」(フレーム)を常に考えながら会話します。来談者が抱える「揺れ動いている」フレームを尊重し、「理解してもらえている」という安心感と「自分で選択できる自由」を与えることが重要です。
この本について
相対評価
・ 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): やや方法寄り。具体的な技法や質問例が豊富です。
・ ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ寄り。現在と未来に視点を置く、論理的・効率的な手法です。
・ 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 今すぐ(短期)に特化。「短期集中療法」であり、短期間での問題解決を目指します。
・ 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。セラピスト、教員といった専門家が「何をすべきか」が主題です。
・ ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ポジティブに特化。問題ではなく「解決像」に焦点を当てる、未来志向の姿勢です。
・ 発達特性との関連度: 3(事例の一部として言及はあるが、手法の普遍性が核)。
独自の観点:行動と自立への勇気づけ
- 構造的な強み: 親の「頑張りすぎる努力」や「禁止の言葉」が問題を強化するという構造を明確に否定します。そうでなく「思考の転換」を促すことで、親の消耗を最小限に抑えます。
- 自立へのアプローチ: 問題は考えるより「行動」でしか解決しないという前提のもと、WFGやコンプリメントを通じて、子どもに「行動する勇気」と「失敗からの回復力」を与えます。これは、自立に必要な試行錯誤を促すための戦略的なツールです。
まとめ:細部現状に囚われず、新しく魅力的なストーリーを語り直す
この本は、不登校支援における最も困難な「原因探し」という消耗戦から親を解放します。ブリーフセラピーの哲学は、その効率性(Efficiency)と効果性(Effective)だけでなく、「クライエントの資源を尊重する倫理的(Ethical)な姿勢」を重視します。
親がすべきは、自責の念という「心の重荷」を降ろし、「誰も悪くない」という安心感を得ることです。そして、ユニークな質問や「例外探し」を通じて、子どもが持つ「自主性」と「強み」という資源に光を当てます。
問題は考えるより「行動」でしか解決しない。この本は、親子のコミュニケーションという普遍的な領域に、論理的かつ創造的な「心の技術」を持ち込み、子どもが自ら立ち直るための「過程」を再設計する力を与えてくれるのです。
ご購入はこちらから
https://amzn.asia/d/5Y1SR1Y
スガヤのふせん ~個人的ブックマーク
- 「原因」や「正解」を探すでなく、対話可能性を開き、つないでいく
さまざまな対話方法が、実際に用いられる現場での再現事例を通して学べます。なかには「漫才(ボケとツッコミ)」みたいなケースもありましたが、当事者としては至って”真面目”なのでしょうし、逆に”真面目”に「正解」を探そうとするほど、短期単眼的、また「べき・ねば」にとらわれてしまい、「解決」が遠のくのでしょう。
この本は、不登校支援における最も困難な「原因探し」という消耗戦から親を解放します。ブリーフセラピーの哲学は
不登校やひきこもりの問題は、決して新しい問題ではありません。心理援助に携わる者にとってはむしろよく出会う問題とも言えるでしょう。しかし、そこには実にさまざまなディスコース(言説)が存在しています。ディスコースの宝庫と言っても過言ではありません。おそらく携わる専門家の数だけ、あるいは経験した当事者や関係者の数だけ、解決へのアイデアや、場合によっては「ねばならない」があるかもしれません。ということは、当事者や関係者の方たちもそれだけさまざまな情報に影響を受け、時には振り回されたりプレッシャーを感じたりするはずです。問題に直面している時間が長いうえ、さまざまなぷれっしゃーにさらされるのは本当に大変なことだと思います。
ブリーフセラピーは決して「正解」を提案するものではありません。当事者や関係者の困りごとやニーズを丁寧に汲み取りながら、柔軟に使えるリソースを探索していくところにその特徴があります。(「おわりに」から)
逆説的ですが、あえて「正解」を探さず「解決しない」姿勢を保つ。いまできていること(リソース)を大事に、何かにとりあえずつなげて”行動”してみる。その結果…また振り返って考えてみる。
こと「考えすぎ」に、あまり良いことはありません。これはいわゆる「デキるサラリーマン」ほどよく知っていて、実践していることだったりします。ひとつ・ひとところにこだわらず、自由で創造的に物語を書き換えてみる勇気…そんなものに出会うのがこの「ブリーフセラピー」の良さなのかもしれません。