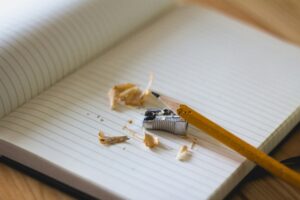この記事では、不登校が単なる個人的な問題ではなく、時代の社会・文化的な状況を反映する現象として、その捉え方がいかに変容してきたかを詳細に論じていきます。
不登校の定義と変遷
歴史的経緯
学校教育が始まって以来、病気などの正当な理由なく学校を長期にわたって欠席する行為は、学校側から「問題行動」として捉えられてきました。当初は、その行為は「怠学」というレッテルを貼られ、研究の対象となっていたのです。しかし、やがて従来の怠学とは異なる神経症的症状を持つ子どもたちがいることが指摘され、彼らの状態は「学校ぎらい」として、長期欠席の一類型として登場しました。
この「学校ぎらい」の数が文部省の調査で増加し始めた1970年代後半から1980年代にかけて、不登校は教育関係者の注目を集めるようになりました。この1984年以前の時代は「登校拒否」と呼ばれており、子ども本人や親の「わがまま」「病気」「精神的な問題」と見なされることが多く、社会的な偏見が強く、十分な理解や支援体制は整っていませんでした。
しかし、この時代に転機が訪れます。東京シューレの設立者である奥地圭子は、自身の我が子の不登校経験をきっかけに、1984年に「登校拒否を考える会」を設立しました。この動きが、不登校問題を個人の病理から社会全体の問題へと捉え直すきっかけ、すなわち不登校問題の「社会化」の端緒となったのです。
1985年から1999年の時代には、不登校が社会問題として広く認識され始めました。不登校の子どもを単なる「問題児」として扱うのではなく、その個別の背景を理解しようとする動きが広がりました。2000年から2013年の時代に入ると、不登校への公的な支援が制度化され、不登校児童生徒数が一時的に横ばい、あるいは減少傾向を示しました。この時期には、「いじめ」や「友人関係」といった明確な理由よりも、「無気力・不安」といった内面的な要因が増加したことが特徴です。
そして2014年以降の現代では、不登校児童生徒数は急増し、過去最多を更新し続けています。不登校は、もはや「問題」として排除すべきものではなく、多様な学びの選択肢の一つとして認識されつつあります。この時期の不登校の要因は、従来の「無気力・不安」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による生活リズムの乱れやオンライン学習の普及など、新たな要素が複雑に絡み合っているのです。
文部科学省による定義(整理)
不登校の捉え方は、行政の定義からもその変遷を読み取ることができます。文部科学省は、不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」と定義しています。ただし、この定義には「病気や経済的な理由による者を除く」という重要なただし書きが付記されています。この点は、不登校が心や感情の問題を背景に持つ場合に用いられる言葉であることを示唆しています。
また、「多様な要因・背景」という言葉が示すように、不登校の理由は個人の心身の状態だけでなく、家庭や学校、社会といった環境的影響も複雑に絡み合っている場合が多く、単純な単一原因では説明できません。さらに「したくともできない状況」とは、子ども自身が「学校に行きたい」と望んでいても、心や体の状態がそれを許さない状態を指し、これは決して「サボり」や「わがまま」ではなく、子ども自身もその状況で苦しんでいるという視点が大切です。
文部省が1992年に「登校拒否(不登校)はどの子どもにもおこりうる」という見解を出して以降、不登校を捉える認識自体が「明確な逸脱」から「子どもの多様なあり方の一つ」へと転換したことは、非常に大きな変化でした。
しかし、文部科学省の統計データ自体も一定ではありませんでした。1990年代には不登校の定義が修正され、学校基本調査の統計基準も1991年以降、年間50日以上の欠席から30日以上の欠席へと変更されています。「学校ぎらい」という項目が『学校基本調査報告書』に加わったのは1966年調査からで、当初は年間50日以上の欠席者が該当していました。1991年度データからは30日以上の欠席が基準となり、1998年度のデータからは「学校ぎらい」に代わって「不登校」という用語が使用されるようになりました。
文部省自身も、不登校の実態は公式統計の「学校ぎらい=登校拒否」の数字を上回っていることを再三認めています。特に1998年度に「不登校」の増加数が過去最高となったのは、「学校ぎらい」から「不登校」への名称変更に伴い、現場が抵抗なくカウントできるようになった要素も影響していると文部省も認識していたようです。
不登校公式統計の信憑性については、多くの研究者が疑問を呈しています。統計データには定義の一元性に関する不備が存在し、都道府県間で分類基準が著しく異なっている可能性が指摘されています。
呼称変更の背景(COCOLOプランに至るまでまとめ)
子どもの長期欠席を示す呼び名が「学校恐怖症」から「登校拒否」、そして「不登校」へと変化してきた背景には、不登校に対する社会的な認識の変遷と、それに伴う政治的な力学が深く関わっています。
1970年以降に「登校拒否」という用語が一般化したのは、「恐怖症」という精神病理学的なイメージを避け、より一般的な不適応行動として捉え、関わっていこうという意図があったためとされています。
呼称変更の根拠は、1989年の法務省人権擁護局『不登校児の実態について』において示されています。「学校に行くことを『拒否』しているわけではなく、『行きたいのに行けない』あるいは『行かなければならないと思っているのにいけない』児童生徒もいることから、『不登校児』と呼ぶことにした」と明記され、子どもの内面的な苦悩に配慮した表現が採用されました。
新聞記事全体における呼称の移行は、意味上の使い分けというよりも、文部省が1992年に出した『学校不適応対策調査研究協力者会議最終報告書』が直接的な要因となり、ごく短期間に入れ替わったと見るのが妥当です。この呼び名の転換は、長期欠席に対する社会的意味づけの転換の指標と見なすべきでしょう。
この転換の背景には、「登校拒否は病気ではない」と訴える母親たちからの異議申し立てが、社会問題としての不登校問題の構築過程を明確にしていったという歴史があります。文部科学省による統計の枠組みや分類の変更は、不登校問題に対する行政側の対応の混乱や戸惑い、そして不登校に対する視点の変化を反映しているものと見なせます。
1990年代以降、不登校はもはや「治療」の対象ではなく、「癒し」の対象として語られるようになり、「理解」「ケア」「心」といった言葉がキーワードとなりました。この言説の転換が、呼称変更の背景にあると考えられます。不登校の公式統計が近年、社会的まなざしや政治的作為を敏感に反映する指標と化しており、そのことが呼称変更の背景にも影響していると指摘されています。
不登校の原因と背景
言説の変化
不登校の捉え方は、時代とともに大きく変化してきました。初期には「怠け」や「病気」として捉えられ、「医療化」という支配的な言説と、それに対抗する非「医療化」の対抗言説が登場し、社会問題としての不登校の社会的構築の過程が明確にされていきました。
1970年代半ばから1980年代前半にかけては、登校拒否が「家族関係、とりわけ母子関係の病理」として問題化され、新聞記事などでは母親が「犯人化」される傾向が見られました。また、1982年頃には登校拒否が母子心中や親殺し、子殺しと結びついて「悲劇」として社会面で報じられました。
しかし、こうした言説に対し、母親たちは結束して対抗言説を生み出します。1983年の新聞投書には、「一人で苦しみ悩んでいるお母さん方、電話ででも悩みをわかちあい、励ましあって、明るく生きていこうではありませんか」と母親同士の結束を呼びかける記事が現われ、「登校拒否は病気ではない」と異議申し立てを行う「新しい社会運動」が生まれました。
文部省が1992年に「登校拒否(不登校)はどの子どもにもおこりうる」という見解を出して以降、不登校は「明確な逸脱」から「子どもの多様なあり方の一つ」へと認識が転換しました。この動きを先駆け、1987年以降の新聞家庭面では「『拒否』は病気じゃない 個性抑える学校に原因」といった学校批判の記事が増加し、当事者の声を反映する形で「病理」ではない不登校の姿が伝えられ始めました。
不登校研究も、不登校という「実態」を前提とするのではなく、不登校に対する私たちの「認識方法そのもの」を問題とする立場へと変化していきました。
現代の支配的な不登校言説としては、森田洋司が提唱した「私事化」社会における「登校回避感情」の行動化としての不登校言説と、スクールカウンセラー制度導入・拡充による改善策言説があります。特に後者の言説では、医療の専門家が「語り手」の立場を占有し、不登校児を自身の言説における「登場人物」として客体化する実践が指摘されています。
これに対し、不登校を「もう一つの生」の可能性や「状況突破の一様式」と捉える試み、また「移動」「変身」「旅」といった例えで捉えることで、自己の新しい物語を生きる主体としての不登校児の可能性を提示する「オルタナティブ・ストーリー」が登場しました。
1990年代以降、不登校はもはや「治療」の対象ではなく「癒し」の対象として語られるようになり、個人の心性に焦点が当てられ、「理解」「ケア」「心」といった言葉がキーワードとなりました。しかし、この「癒し」の言説は、不登校を個人的なものとし、その結果として不登校を規制する社会構造上の諸矛盾も受け容れるという逆説的な状況を提示しているという指摘もあります。不登校がかつての「病理」としてではなく、「多様な適応の形の一つ」として見なされるようになったのです。
不登校に関する研究の主題の動向を分析した研究によれば、2000年以前は「相談」「予防」「療法」といった予防・治療の視点が中心でした。しかし、2001年から2010年には「適応指導教室」「中学生」「事例」「調査」といった学校外機関での実践や実態調査へとシフトしました。さらに2011年から2015年には「母親」「発達障害」「経験」といった親への支援や発達障害との関連、経験の意味付けが特徴的なテーマとなり、2016年から2021年には「フリースクール」「大学生」「居場所」「行動」「分析」といった多様な学びの場や対象の拡大へと変遷しています。
「学校」の変化(聖性の衰退、社会化空間としての機能低下)
不登校増加の背景として、学校そのものの変化も重要な要因です。1970年代半ば以降の不登校増加の背景には、学校がかつて持っていた「聖性や絶対性」の文化が衰退し、「理屈抜きに学校は大事なところで、休むなんてとんでもない」という意識が社会全体に薄れたことがあります。学校が、かつての「聖なる場」という役割やイメージを失ったのです。
教育の近代化(合理化)が儀礼的空間を失わせ、合理的な思考が「何のために我慢して学校へ行かなければならないのか」という問いを人々に駆り立てるようになり、これが不登校増加の一因となっています。「登校の自明性の低下」という概念に基づき、かつては当然とされていた登校行動の正当性や妥当性が、社会化機能や進路形成機能の限界、逸脱統制機能の限界といった社会の変化とともに揺らいでいるのです。
学校の「社会化機能」や「進路形成機能」が変容・衰弱し、児童・生徒の社会化の場や余暇の場が多様化した結果、学習面や交友面、遊びの面で学校が占める比重は低下しています。特に高校教育においては、もはやかつてほど進路形成機能が十分に機能しなくなり、学校が「社会化空間」として機能しなくなりました。
学校が「自分探し」の場として機能しなくなったため、フリースクールやサポート校などが、既存の高校ではできない「自分探し」の場、あるいは進学・就職先への「社会化空間」として機能している現状があります。
学校の機能不全、あるいは子どもや社会のニーズへの不適応も問題化しています。学習内容の硬直化により、学校よりも柔軟な進学塾や予備校が子どもの学習ニーズに応えるようになった現状もあります。
学校の教育指導は「一斉的・画一的指導」から「多様で個別的で内面にまで踏み込んだ指導」へと変化が進んでいるものの、子どもたちの学力や学習態度、学習習慣の多様化、私化(プライバタイゼーション)の進行により、学校の対応が困難になっているのです。不登校の背景には「心の安全」が脅かされている状態があるという考え方が広まり、無理に学校へ戻すよりも、子どもが「安心できる場所」で心のエネルギーを回復させることが大切だとされています。学校現場でも「心理的安全性」や「ウェルビーイング(心身の満たされ感)」が重視されるようになりました。
家庭・個人の変化
不登校は、個人の内面や家庭環境の変化とも密接に関わっています。かつては、登校拒否が「家族関係、とりわけ母子関係の病理」として問題化され、母親が「犯人化」される言説が存在しました。これは、近代家族の持つ諸前提(家庭における父・母役割の強調や性別役割分業など)にもとづいて登校拒否が問題化されていった結果です。しかし、母親たちが「犯人化」されつつも、互いに結束し、自らの子どもを擁護する対抗言説を生み出していったことは、その後の支援のあり方に大きな影響を与えました。
1990年代以降、父親のあり方への問いかけも変化しました。近代家族の枠内での「父親の担うべき役割」という観点から、「心開いた」関係を求める方向へと変化し、個人の心性に焦点が当てられるようになりました。
森田洋司の「私秘化(プライバタイゼーション)」理論に基づけば、現代社会では人々の私的世界への関心が高まり、学校社会のプライベート・スペースの縮小が、子どもと学校との「つながりの糸」を弱め、不登校行動の誘発要因になっていると説明されます。また、不登校には「家庭の居心地が良くなったために、子どもにとって学校が相対的に居心地が悪くなった」という側面もあります。
不登校の子ども自身も、学校に行けないことによる重圧と苦しみを抱えています。学校に行けなくなったことによる漠然とした不安や心理的な苦しさが隠れているため、保護者や支援者はその心の声を受け止めることが重要です。
近年の不登校が増加する背景として、小学校低学年からの不登校、人一倍敏感な気質(HSC)、ADHDやASDといった発達特性が挙げられます。また、「なんとなくしんどい」「漠然と不安がある」といった原因がはっきりしないケースが増えていることも特徴です。
その他(多様な複合原因論)
不登校は、一つのことでは説明しきれない多様な理由で構成されているという共通認識があります。不登校は、個人病理や家族病理、学校病理に還元し尽くせる現象ではなく、その背後を貫く本質は社会・文化的な現象として把握する視点が欠かせません。
いじめや校内暴力の深刻化も不登校増加の一因です。特に1980年代半ばからいじめが変質し深刻化し、いじめによる悲劇的な事件が社会の注目を集め、学校教育の限界を衆目に晒すことになりました。
地域要因として、村山・内山(1972)以来の研究で、都市化が進んだ地域で不登校(学校ぎらい)の出現率が高く、人口の増加・流動の少ない地域や過疎地では低い傾向があることが報告されています。
学校間でも不登校の出現率に差があることが指摘されており、授業における教師の行動、教師の相談しやすさ、生徒の主体的参加度、教職員の士気の高さなどが、出席率と有意な関係があることが報告されています。また、学校規模が小さいほど、規則が守られるほど、生徒自治が行われているほど、そして学校と保護者の緊密度が高いほど出席率が高いという結果も出ています。教員異動率が高い学校ほど怠学傾向が高いこと、アメリカの高校における研究では、校内の競争が激しく、教師が支配的で生徒への援助が少ない学校で欠席率が高いことも明らかにされています。
不登校の背景には、個人・家庭・学校・社会の要因がすべて密接に絡み合った「複合原因」があると一般的にとられています。
不登校支援の変化
教育行政の対応
不登校の増加を受け、教育行政の対応も変化しています。文部科学省は、不登校児童生徒への支援推進に向け、①個々の状況に応じた支援の推進、②多様で適切な教育機会の確保、③不登校等に関する教育相談体制の充実の3点を整理し、対応を進めています。
1992年に文部省が「登校拒否(不登校)はどの子どもにもおこりうる」という見解を発表し、不登校を捉える認識が「逸脱」から「子どもの多様なあり方の一つ」へと転換したことが、その対応変化の基盤となっています。不登校特例校・適応指導教室(平成15年には「教育支援センター」と改称)の設置促進、教育委員会・学校とフリースクール等の民間団体の連携による支援推進が具体的な施策として挙げられます。
不登校の減少を数値目標化した政策が導入されたり、都道府県別に「1,000人当たりの不登校児童生徒数」が記載されるなど、「不登校」出現率が90年代後半以降、地方教育行政に対する評価基準としての意味合いを強めています。このため、「不登校」統計は不登校現象の「実態」を表す指標としてではなく、地域社会の「まなざし」や「政治的作為」を反映した「社会的まなざしの関数」として機能している側面も指摘されています。
多様な学びの場
不登校の増加を受け、「学びの空間や生活の空間をどのように確保していくか」が実践的な課題となり、学校に代わるさまざまな居場所が登場しました。
- フリースクールと通信制高校: 従来の「学校に戻ること」だけがゴールという考え方から、フリースクールや通信制高校は「子どもの個性に合った学び」の場として前向きに評価されるようになりました。文部科学省も「誰一人取り残されない学びの保障」を掲げ、こうした選択肢を支援しているため、保護者も「学校に戻ること」だけにとらわれずに子どもに合った学びを選びやすくなっています。
- 適応指導教室(教育支援センター): 学校の空き教室などを利用して行われる公的な支援施設で、不登校児童生徒の居場所として機能しています。その役割は拡大し、心理的な支援、学習サポート、集団活動など多面的な援助活動を行うようになりました。
- オンライン学習とICT教育: ICT教育の普及により、不登校支援でもオンライン学習やカウンセリングが一般的になっています。学校が授業を配信したり個別指導を行ったりするケースも増え、自宅にいながら学びを続けられる環境が整いつつあります。外出が難しい子や集団が苦手な子にとって、新しい学習の選択肢となり、孤立感を減らす効果も期待できます。
- 保健室登校: 学校内で唯一安心できる場所として保健室を利用し、少しずつ学校生活に慣れていく方法です。
- 通信制サポート校: 不登校経験のある生徒が高校に進学した後の学習面や生活面を支援するための施設です。
これらの多様な学びの場は、文部科学省が2016年に成立させた「教育機会確保法」によって、不登校児童生徒の多様な学びの場を保障する方向性が明確に示されました。
支援者の役割
不登校支援においては、子どもだけでなく保護者、そして多様な支援者の役割が重要になっています。不登校からの回復には、子どもだけでなく保護者自身の心の安定も大切だと考えられるようになり、カウンセリングやペアレントトレーニング、心理教育の場が増えています。SNSやオンラインコミュニティで保護者同士が悩みを共有したり、経験者からアドバイスを得たりする場が広がっており、親が一人で抱え込まず多様な情報や視点を得ながら子どもを支えやすくなっています。
スクールカウンセラー(臨床心理士など)は、不登校の増大と相まって導入された制度であり、カウンセリングや教員・保護者への助言を行う専門家として位置づけられています。しかし、臨床心理学的知見の拡大が、不登校問題を「心の問題」へと過度に還元し、そこに発生している社会的な側面が忘れ去られてしまう危険性も指摘されています。
スクールカウンセラーが配置されても不登校が減少する気配がないことについて、ある養護教諭は、「スクールカウンセラーが来て、肌で感じる学校の雰囲気が違ってきた時に、はじめて子どもたちは休みたい、今行きたくないんだというのを、本当に素直に出せてるのではないか」と述べており、心理学的なものの見方が不登校に対する認識そのものを変えている可能性を示唆しています。
不登校に関する研究の主題の動向として、2016年から2021年には「フリースクール」「居場所」「大学生」「行動」「分析」といった語が特徴的に見られ、不登校問題の範囲が通常学級の小中学生に限られず、大学生や発達障害のある不登校生、特別支援学校の児童生徒といった多様な対象にまで拡大している現状があります。
不登校は、子どもからのサインを見逃さず、社会の変化や新しい支援の形を理解しながら、焦らず着実に寄り添い続けることで、きっと乗り越えていける課題です。
参考文献
- 『不登校現象の社会学』(森田洋司 著)
- 『不登校問題の社会学 に向けて』(加野芳正 著)
- 『不登校の基礎知識』(奥地圭子 著)
- 『「不登校」ナラティヴのゆくえ』(瀬戸知也 著)
- 『不登校公式統計をめぐる問題』(山本宏樹 著)
- 『「不登校」 をめぐる政治』(加藤美帆 著)
- 『不登校をめぐる歴史・現状・課題』(保坂亨 著)
- 『不登校に関する研究の主題とその動向-過去30年間の文献に対するテキストマイニング』(佐藤主馬、宮川拓人、末吉彩香、柘植雅義 著)