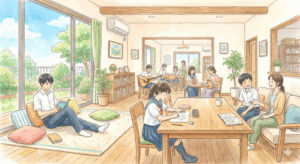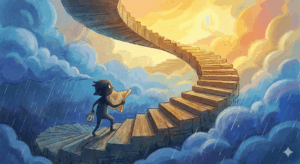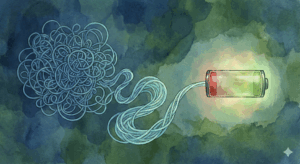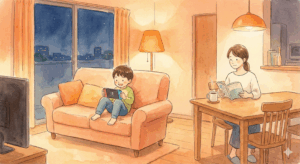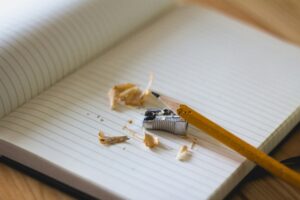前回の『不登校の予兆』編では、不登校の小さなサインを、
- 身体のサイン
- 行動のサイン
- 精神・感情のサイン
- 対人関係・環境のサイン
の4つのカテゴリーに分けてご紹介しました。
今回は、それらのサインが
①どのような背景であらわれるのか
②保護者さまはどのように対応すればよいのか
についてわかりやすくお伝えしていきます。
[筆者プロフィール]
中学生娘の不登校を経験した母親。自身の経験を活かしつつ教育カウンセラーを目指し、現在は不登校支援団体でのボランティア活動にも参加。「同じ悩みを持つ保護者の方に寄り添いたい」という思いから、実体験に基づいた記事の執筆を行っている。
はじめに
不登校はいまや珍しいことではありません。私自身も不登校の子どもをもつ保護者として、不安や焦りを身をもって感じてきました。朝、お子さまが「学校に行きたくない」と口にしたとき、保護者さまがどのように対応すればいいのか迷ってしまうことも、ごく自然なことです。
特に中学生は思春期の真っただ中。心身ともに大きな変化を迎える時期であり、友人関係や学業のプレッシャー、将来への不安などさまざまな要因が複雑に絡み合います。その結果として、学校に行くことがつらくなってしまうことも少なくありません。
この記事では、最新の研究成果と実際の体験をもとに、不登校の予兆として現れる”心理的背景”をひもときながら、お子さまをサポートするための具体的なヒントをお伝えしていきます。
コロナ禍が子どもの心に与えた影響
急速に変わりゆく社会と子どもの心
コロナ禍は子どもたちの日常を大きく変えてしまいました。
長期間の臨時休校、慣れないオンライン授業、友達と会いにくい生活・・・
こうした変化は、特に思春期真っただ中の中学生に大きな混乱をもたらしました。“自分らしさを見つけるための大切な時期”に、コロナ禍での社会的制約や孤立感による“心の負担”が重なってしまったのです。
そして、その影響は現在も色濃く残り、不登校の子どもは増加傾向にあるといわれています。
会えない日々が生む孤立感
中学生にとって、友人関係は”自分”という存在を確かめるうえで欠かせないものです。
しかし、コロナ禍によってマスクをつける生活や距離をとったコミュニケーションが求められ、相手の表情や感情を読みとることが難しくなりました。
(例)
- 相手が何を考えているのかわからない
- 自分の気持ちが伝わらない
こうした不安から、多くの子どもたちが深い孤立感を抱えるようになったのです。
実際に、わたしがお話を伺った保護者さまからは、
- 急に内向的になった
- 友達と遊ぶことを避けるようになった
という声が寄せられています。「本当の自分をわかってもらえるだろうか」という思いが、子どもたちの心に重くのしかかっているのです。
デジタル依存で乱れる生活リズム
「不要不急の外出は控えてください」
この言葉は、コロナ禍で毎日のように耳にしたフレーズです。
友達とも遊べない、習い事にも行けない・・・
そんな日々が続き、気付くと家で過ごす時間が増え、多くの子どもたちがスマートフォンやゲームにのめりこむようになりました。この習慣は、コロナが落ち着いた現在も続いています。
そして、気付けば夜遅くまでスマホやゲームを楽しむのが当たり前になり、
「朝なかなか起きられなくなった」
「日中の集中力が続かない」
といった悩みも珍しくありません。
こうした変化の積み重ねで、”学校に行くこと”自体が負担になってしまった子供も少なくありません。
アフターコロナの不登校を考える
不登校の背景には、
- 学習面
- 心理・社会面
- 健康面
の3つの要因が複雑に絡み合って影響しています。
特にコロナ禍を経て、これらの要因がより深刻になっているといわれています。
「わからない」から「行きたくない」へ
学習面の要因で最も多いのが、「授業についていけない」という不安です。
(例)
- 難しくなった学習内容
- 「自分だけがわからない」という劣等感
- テストの点数が下がることへの罪悪感
これらの悩みによって、学校が“失敗を突き付けられる場所”に感じてしまうことがあります。
コロナ禍の臨時休校やリモート授業は、これらの状況をさらに悪化させました。
外出や息抜きを制限されることによって、子どもの勉強への意欲は落ち、学習の遅れを広げてしまったといわれています。
“孤立感”が不登校につながるきっかけ
思春期の子どもにとって、友達グループでの“立ち位置”はアイデンティティそのものです。
そのような大切な時期に、コロナ禍の外出制限や臨時休校は”孤立感”をさらに強めました。
実際に文部科学省の調査では、コロナ禍の10代の約6割が「孤独感を感じた」と答えています。
- 「仲間外れにされるかも」
- 「本当の友達っているのかな」
- 「みんなに合わせるのにつかれた」
子どものこうした悩みは、大人が考えている以上に重大なものです。対面でのコミュニケーションが減ったことで、友人関係を築くことが難しくなり、不登校につながるケースも見られます。
さらに、家にいる時間が増えたことで、家庭での虐待や暴力が増えたと報告されており、こうした環境が若者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼしているのです。
「朝起きられない」が心のSOSになる
健康面の要因で深刻なのは、”睡眠不足”です。
多くの小中学生が「朝起きられない」「夜眠れない」といった悩みを抱えています。これは単なる「怠け」ではなく、生活リズムの乱れによって心身ともに深刻な影響を受けているのです。
睡眠不足、不規則な食生活、運動不足、慢性的な体調不良・・・
これらの状態が続くと、集中力や記憶力が低下し、感情のコントロールも難しくなります。その結果、孤立感を強めたり、うつ病の発症と関連したりするといわれています。
睡眠不足とデジタル依存の落とし穴
睡眠リズムが心とからだに与える影響
中学生に必要な睡眠時間は8〜10時間といわれています。
しかし現実では、
- スマホやゲームでの夜ふかし
- 部活動・塾での帰宅の遅さ
- 宿題の多さ
によって、十分な睡眠がとれていない子どもが多くいます。さらに、スマホのブルーライトは眠気を促すホルモンの分泌を妨げ、寝つきを悪くしてしまいます。
規則正しい睡眠リズムを整えることで、
- 記憶力や集中力が高まる
- 感情が安定する
- 免疫力が強まる
といった効果が得られます。つまり、学校生活をより快適に過ごすための土台となるのです。
デジタル社会特有のリスク
そこに追い打ちをかけているのが、デジタル社会のリスクです。
インターネット依存、SNSでのトラブル、ネットいじめ、危険なサイトへのアクセス・・・
子どもたちは24時間つながっている環境の中で、心身を休める時間を奪われています。
インターネットは、子どもにとって重要な居場所のひとつです。
現実では居場所を見つけにくい子どもが、同じ悩みを抱える仲間と出会い、仲間意識や安心感を得られるというのは大きなメリットです。一方で、共感や同調が強まりすぎることでネガティブな感情が膨らみ、自傷行為などの深刻な行動につながってしまうというデメリットも指摘されています。
“健全な”デジタル環境づくり
とはいえ、スマホやインターネットを完全に禁止するのは現実的ではありません。大切なのは“健全なつきあい方”をご家庭でいっしょに学ぶことです。
- 時間の管理:平日は2時間、休日は3時間を目安に。SNSは使用時間を設定する。
- 場所の工夫:寝室や食卓ではなく、リビングなどの共有スペースで使用する。
- 休む日を設ける:週1日は「デジタルデトックスデー」とし、外出時はなるべくスマホを使わない。
- コンテンツを共有する:面白い動画や気になるニュースは家族で共有する。
一方的にルールを押し付けるのではなく、「なぜこのルールが必要なのか」をお子さまといっしょに考え、ご家庭に合ったルールをつくることが大切です。また、お子さまがどんなコンテンツに触れているか把握することも大切です。頭ごなしに否定するのではなく、「どんなところが面白いの?」「どう感じたの?」と問いかけることで、自然にお子さまの心を理解するきっかけにもなります。
学校に行きたくなる環境づくり
「行かせる」から「行きたくなる」へ
不登校の要因を取り除くには、睡眠やデジタル環境の改善だけではなく、“学校に行きたくなる理由”を増やすことも大切です。
子どもの登校を後押しする最大のきっかけは”時間割や授業内容の工夫”だとされています。子どもたちにとって、“学ぶ楽しさ”や“成長を実感できること”が学校に行くために重要なことなのです。
学校生活の中で「キラリと光る瞬間」
子どもが学校に行きたくなる理由は一人ひとり違います。
(例)
- 好きな先生の授業がある
- 仲良しの友達と会える
- 部活動で上達できる
- 行事で自分の役割がある
- 図書室で静かに本を読める
そのきっかけはさまざまです。
私自身の経験でも、「今日は○○の授業があるから行く」と言った子どもの表情は、とても前向きで生き生きとしていました。大切なのは“行かせること”ではなく、子どもの「行きたい」という気持ち。ご家庭では、その小さな楽しみや達成感を認めてあげましょう。
家庭は”安心できる基地”に
学校で頑張るには、家庭が安心できる場所であることが欠かせません。うまくいかない日があっても、「家に帰れば受け入れてもらえる」と思えることで、子どもはまた挑戦する力を取り戻します。
学習面のサポートでは、結果よりも過程を評価することが大切です。
「テストで80点取れたね!」よりも「毎日コツコツやってたね」「分からないところを質問できたね」といった声かけの方が、努力や成長をしっかり後押しできるのです。
学校と“ともに”支援する
子どもの成長をサポートするためには、家庭と学校が同じ方向を向くことが欠かせません。学校は敵ではありません。保護者と教師が連携することで、親の不安や焦りも和らぐといわれています。
大切なのは、子どもの良い変化を共有し、さらに伸ばす方法を一緒に考えることです。
連絡帳や電話でのやり取りでも、問題点だけではなく、「今日は友達に優しく声をかけていました」「授業で積極的に発言していました」といった前向きな情報を伝えてもらえると効果的です。そうした小さな出来事が、家庭での会話のきっかけになり、子ども自身も「学校っていいこともあるんだ」と思えるようになるのです。
保護者の成長が家族に与える影響
保護者の気持ちが家庭にもたらす力
子どもの不登校に直面すると、「私の育て方が悪かったのでは…」と自分を責めてしまう保護者は少なくありません。私自身も、子どもが学校に行かなくなった当初は、毎日のように自分を責め、将来への不安で眠れない夜を過ごしました。
保護者が心理的に安定していると、家庭の雰囲気は大きく改善するといわれています。
子どもは私たちが思っている以上に親の感情に敏感です。親が不安定だと子どもも不安になり、落ち着いていれば子どもも安心できるのです。
つまり、子どもを支えるためには、まず保護者自身が心の安定を取り戻すことが何よりも大切です。これは決して”自分勝手なこと”ではなく、子どものための大切なステップなのです。
“完璧な保護者”じゃなくていい
保護者が成長するための第一歩は、いまの現実を受け入れることです。
私の場合も、「今すぐ学校に行かせなければ」という焦りから、「この子のペースで成長すればいい」と思えるようになった瞬間、家庭の雰囲気が大きく変わりました。子どもも「責められない」「急かされない」という安心感で、少しずつ気持ちを話してくれるようになったのです。
また、自分自身を大切にすることも意識するようになりました。友人との時間、趣味に没頭する時間、十分な睡眠・・・これらは贅沢なことではなく、子どもを支えるために必要な“充電時間”だと考えるようになったのです。
同じ悩みを持つ仲間は支えになる
同じ悩みを抱える保護者との交流も大きな力になります。
人の体験から学ぶだけではなく、自分の経験を話すことで気持ちを整理できるからです。
「うちの子も頑張っている」「私も努力している」、そう実感できるようになると、不安が軽くなります。
私自身も、先輩保護者から「最初は心配だったけれど、今は高校に通っている」「大学に進学して夢を見つけた」といった体験談を聞くことで、数年後の希望を持てるようになりました。
専門家に相談する
スクールカウンセラーや臨床心理士など、専門家の力を借りることも大きな助けになります。
私の場合は、
- 「学校どうだった?」ではなく「今日はどんな気分?」と聞く
- 子どもの話を否定せず受け止める
といった具体的な方法を学ぶことができました。
最初は「相談するなんて親失格では」「プライベートを話すのは恥ずかしい」と思っていましたが、実際に相談してみると、”より良い選択”だったと実感できました。
まとめ
生活の土台を整える
子どもの不登校の対応で、まずはじめに取り組みたいのは、規則正しい生活リズムをつくることです。一見ささいなことに思えますが、これこそがもっとも大切な基盤となります。
(例)
- 就寝・起床時間を一定にする
- 食事の時間を決める
- 適度な運動を取り入れる
特に効果的なのが、“朝の光を浴びる習慣”です。朝、カーテンを開けて日光を浴びる、少し外に出るだけでも体内時計がリセットされ、夜の睡眠リズムが整います。
我が家では、学校に行かない日でも”朝のルーティン”を維持しています。起床・朝食・身支度の時間を変えないことで、生活のリズムが乱れにくく、再び学校に行こうと思ったときにスムーズに戻れるのです。
心をつなぐコミュニケーション
不登校に向き合ううえで欠かせないのが、子どもとのコミュニケーションです。
「学校どうだった?」「今日は行けそう?」といった質問は、子どもにプレッシャーを与えることがあります。
大切なのは否定せずに受け止めること。
(例)
- 共感を示す(「つらかったね」)
- 価値判断を避ける(「でも」「だけど」を使わない)
- 言葉をそのまま受け取る(勝手に解釈しない)
- 解決策を急がない(まずは気持ちを受け止める)
この積み重ねで「この人には本音を話してもいいんだ」と子どもが感じられるようになり、信頼関係が深まっていきます。
一人で抱えない
そして、専門機関の力を借りることも大切です。
(例)
- 学校:スクールカウンセラー、養護教諭、担任
- 教育機関:教育相談センター、適応指導教室
- 医療機関:児童精神科、心療内科、小児科
- 心理支援:臨床心理士、公認心理師によるカウンセリング
- 民間支援:不登校支援団体、フリースクール、保護者の会
これらを状況に応じて組み合わせるのも効果的です。学校は学習面、カウンセリングは心理面、保護者の会は情報交換や心の支え・・・とチーム体制で支えてもらうことで、より手厚いサポートを受けることができます。
希望を持って歩み続ける
はやめに支援を求めることは、苦しい状況を抜け出すための第一歩になります。
つい、「様子を見ていればそのうち・・・」と思いがちですが、問題がこじれる前に専門家に相談することが、解決に繋がります。大げさなことではなく、子どもの将来を考えた正しい判断です。
ただし、解決には時間がかかるもの。すぐにどうにかしようとするよりも、「子どものペースで成長していけばいい」とのんびり構えることが大切です。
そして何より、一人で抱え込まないでください。
経験者の保護者、理解のある家族や友人、専門家・・・多くの人が支えになってくれます。
その力を借りることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、誰よりも子どもの幸せを願っている保護者の”勇気ある選択“です。
小さな変化の積み重ねが、やがて大きな成長につながります。
焦らず、慌てず、諦めず、でも希望を持って・・・お子さんと一緒にゆっくりと歩んでいきましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
次回は、不登校の背景にある時代や社会の流れに目を向けながら、”不登校の初期段階でできる対応”についてご紹介します。
参考文献