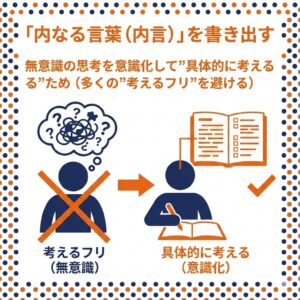不登校に悩む保護者にとって、子どもの口から「本音」を引き出すことは、最も難しく、そして最も切実な課題です(先の記事でも触れましたが、そもそも「原因」は追い求めないのが肝要です)。
これまでの勉強会を通じて、私たちは「”なぜ”学校に行かないの?」という一見素朴にしてシンプルな問いかけが、子どもに罪悪感と防衛心(ストレスとプレシャー)を生む最大のトリガーであり、不毛な「空中戦(原因のなすりつけ合い)」を誘発することを学んできました。
それでは、一体何について子どもと話せばよいのでしょう?一切学校のことには触れず話さず、ただ「放置」するのがよいでしょうか?
それでは、一体何について子どもと話せばよいのでしょう?一切学校のことには触れず話さず、ただ「放置」するのがよいでしょうか?
結論としては「No(できるだけ話したほうが良い)」であり、「”放置”でなく”放任(信じて任せる)”」が当サイト勉強会で導き出された合意点でした。
というわけでこのコラムでは、筆者(スガヤ)の長年の対話経験、および当サイト勉強会を通じて保護者の方々と行った「実践演習」に基づき生み出された専門技術「逆コナン戦術(真実はいつもひとつ以上、しかし事実はひとつ) ※仮」に基づき、その一旦の”最適解”を提示します(※これらは並行して開発中であり、その”理想形”は随時更新されていきます。また特定対象を非難するわけではなく、「コナン」は人生の愛読書です)。
これは言い換えれば、子どもの「言い訳」や「その場限り応答」を引き出す「なぜ?(Why:空中線)」を封印し、代わりに「いつ(When)/どこで(Where)/何を(What)/誰と(Who)」という「事実質問(地上戦)」によって、対話を現実の行動や感情に引き戻す技術です。
この具体的なフレームワークと実践を学ぶことで、あなたは子どもに”詰問”することなく、信頼関係を回復させ、解決に向けた第一歩を踏み出すための確かな糸口を掴むことができるでしょう。
1. 「なぜ?(Why)」が引き起こすプレッシャーとストレス
過去大好評だった「「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた 「なぜ」と聞かない質問術」を題材とした読書勉強会では、「なぜ?」「どうして?」と聞く質問を「よくない質問」の代表と見なしました。
その理由は二つ、
・第一に、「なぜ?」は、相手の「思い込み」を引き出し、それがコミュニケーションのねじれ(「誤解」にしかならない回答)につながるからです。子どもが語る「不登校の理由」は、往々にして親を納得させるための「抽象的でその場しのぎの答え」にすぎません。
第二に、「なぜ?」は最悪の答え、すなわち「言い訳」を引き出すからです。私たちは、自分でも「よくなかった」という行為に対して「なぜ?」と聞かれたら、とっさにそれを「詰問(自分を責めるための質問)」として心理的に強いストレスを感じ、会話を打ち切ろうとしてしまいがちです。
このように、曖昧で実りのない会話を「空中戦」とするならば、この空中戦を終結させ、「対話の継続」から「次(So next)」へと繋がる”具体的な行動”に焦点を当てることが、親子の対話における最初の目標となります。
2. 地上戦への移行:事実質問の原則と「いつ?」の力
空中戦から脱却し、現実と事実に立脚した「地上戦」に戻るために必要なのが「事実質問」術です。
事実質問の基本原則
事実質問に使える疑問詞は、5W1HのうちWhy(なぜ)以外の「いつ (When)」「どこ (Where)」「何を (What)」「誰が (Who)」です。その原則は、かのブルース・リー「考えるな、感じろ(Don’t think. Feel!)」…にも繋がる「考えさせるな、”即答”させろ」にありました。
- 時制を過去・現在進行形に変える: ー「〜しますか?」ではなく「〜しましたか?」 ー「今日の予定は何ですか?」でなはなく「今、何をしていますか?/次は、何をしますか?」
- 主語述語を曖昧にしない: ー「みんなはどうだったの?」ではなく「あなたはそのとき、何を感じたの?」 ー「普通はどうするの?」ではなく「あなたは何をしたいの?/どちらがいいの?」
最強の質問:「いつ?」
事実質問のなかでも特に強力なのが「いつ(When)」質問です。行動や感情は、時間というアンカーと結びつけることで、最も客観的かつ具体的に切り取ることができます。
例えば、子どもが「学校が嫌だ」と言ったとき、「なぜ嫌なの?」ではなく、「一番最近、いつ学校が嫌だと感じた?/その出来事は具体的に何?」と問うことで、抽象的な感情を具体的な出来事(事実)に引き戻すことができます。
3. 実践フレームワーク:問題を紐解く8つの公式
ここでは親子の対話でよく発生する「会話断絶の壁」を乗り越えるため、書籍(「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた 「なぜ」と聞かない質問術」)をもとに、みなさんの実践演習から導き出されたさらなる”具体的な知恵(※カッコ内)”を加えた「分析と解決の方程式」について、さらに詳しく紹介します。
- 相手の回答を自分の言葉で言い直すのは厳禁: まずは子どもが言ったとおりに「オウム返し」で受け止めます。「大人の/正しい言葉」にいちいち変換しない
→「先生みたい!」と言われない - 「問題」を語り始めたら、「いつ?」から始める:「学校が嫌だ」と言われたら、「いつからそう感じたの?」
→親の口癖って、いつもなんで「なんで?」 - 「どうしていいかわからない」と言われたら:「他の誰かに聞いてみた?/では誰に聞くとわかるかな?」と尋ね、対象/相手を特定する
→「わからない」「知らない」は格好の避難口 - 「本当に問題なの?」と聞きたくなったら:「誰が、どう困ったの?」と聞き、課題を特定/問題の当事者と影響範囲を明確にする
→「課題の分離/分解」が基本 - 「〇〇が足りない」と言われたら:「いくら/いくつ足りないの?」と聞き、要求を具体化させる
→「定性」は「定量」に - 「できない」と言われたら:「それをやるのは、誰が決めたの?/あなたがやらないと誰が…やるの?(困ったわね)/あなたにできる、他のやり方はない?」と尋ね、責任の所在を固定する
→主体性を引き出す、ただし柔らかく”一緒に困る” - 「一体なぜその選択をしたの?」と聞きたくなったら:「他にどんな選択肢があったの?」と聞き、本人の思考の幅を広げる
→「行動の間違い」ではなく、とっさの「選択の失敗」は誰にでもある - 「わかっているのにどうしてやめられないの?」と言いたくなったら: 軽く微笑みながら、しばらく相手の目を見つめ、沈黙で応じる
→「沈黙の笑顔」とは「ほっとけ様の輝き(信じて任せよ)」
4. 解決は「してはいけない」:当事者の気づきを信じる
この質問術を実践する上で、最も重要な大原則は「解決はしてはいけない、させるもの」です。
治療やカウンセリングの現場からも、「”治そう”という意志/目的を手放したとき、はじめて回復が可能になる」という逆説が指摘されています。親が先回りして解決策を提示することは、子どもの「自分で見つける」というエネルギーを奪います。
人が自分で見つけたもの以外は、ほとんど忘れてしまうものです(「Use it,or lose it」)。ニワトリが雛をかえすまで「信じて待つ」ように、保護者様の役割は、質問術によって子どもの「真実」を地上に引き戻し、当事者の気づきが行動変化のための大きなエネルギーとなるのを辛抱強く見守ることなのです。
…が、しかし!それでも「つい、やってしまいたくなる(余計な手や口を挟みがち)」のが「親の愛情(ショーワOS)」というのが参加の皆様の素直な感想でした。そこで筆者がオススメしたのが「親の愛情~レーワOS版 ※仮」でして
・「ほっとけ様」に徹する(子どもは”手のひら”で育てる感覚)
・「愚行権」を認めよ(子どもは失敗から学ぶ)
・「悪いことほど楽しい」のがそもそも子ども(「ホワイト家庭」にならない)
・「9割の悩みが人間関係」(「人の間」に生きるから人間)
・「雑談」ベター、「沈黙」ベスト(子は”育てる”でなく”勝手に育つ”)
・言いたくなったら「まず自分」(親(あなた)は言うほど、できてますか?)
などが、現在のところの行動指針です(アップデート更新は随時実施)。
また非認知的なところで言えば
・口癖(「~的な」「~みたいな」で”わかりづらさ”を加えがち)
・表情、しぐさ(「人は見た目が9割」「顔は口以上に物を言う」)
なども目下の改善目標です。
このため当サイトでは”実践”としての「演劇」を取り入れた勉強/読書会を随時開催中です(ちなみに演技指導は、元不登校を経験した学生です)。こと理論は「わかっちゃいるけどすぐやれない」、書籍は「読んで終わり」が最大の弱点です。これらは「実践」あって初めて身につきますし、苦手なことほど「繰り返し演習(親ドリル)」が必要になります。そのための「定期開催」でもあるのです。
なにより私たちは意外と「子育て」について、誰からも知恵/研修を授けられずいきなり「現場デビュー」となりがちです。中には”間違ったまま”のことも非常に多いわけで、親もまた「内省」が必要です。このとき、他者からの指摘はその気付きを促します。
当コラムは随時更新していきたいと思いますが、ぜひ読んで興味が湧きましたら当サイト主催の「勉強/読書会」にもご参加ください(いつでも、どなたでも大歓迎です)